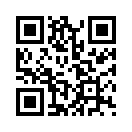2009年03月11日
自分たちのポジションを決めなあかん。
第15回 山田繊維株式会社 代表取締役 山田芳生 vol.3
――山田社長の経歴について教えてください。
大学を卒業して、アパレル大手のワールドに入社しました。
就職活動をはじめるときには、会社を継ぐことは決めていたので、
同じ繊維関係の会社にターゲットを絞り、就職活動をしました。
実は就職活動を始める前の私はほんとうに遊ぶことしか考えていないような感じで、
会社を継ぐよりも、軽い気持ちでショップやレストランなど自分で事業を起こしたいと考えていました。
ところが3回生の終わりになり就職活動をはじめるようになって、どうしようかなと悩んでいたときに、
かなり年上の先輩に「ほんまに自分でやりたいものがあるとしたら、
親父さんの会社をお前が自分でちゃんと経営ができれば、
そこで成功すれば、自分のやりたいことができる一番の近道ちゃうか」とアドバイスを受けて、
「そうか!」と納得したんですよ。
山田繊維という会社をちゃんと自分の土台にできれば、好きなことできる。
そういう邪まな気持ちが少なからずあったのですが、当時はそれですっきりしました。
自分で一から事業をはじめるにしても、土台があると強い。だから土台をしっかりさせよう。
そのための就職をしようと決心しました。

――山田繊維へはいつ入社されたのですか?
ワールドに入社したときはバブルの全盛の頃で、営業の仕事をしていました。
華やかな世界で刺激的でしたが、ほんとうに忙しい毎日でした。
それで5年たったときに東京に支店を出す話しがあり、
当時、社長だった父に「お前も東京にいけ」と言われ、「ええよ」という感じで山田繊維に入りました。
最初はワールドとの違いにカルチャーショックを受けました。
東京に支店を出したものの、風呂敷のマーケットは縮小傾向にあるような厳しい状況でしたし、
なんとかせなあかんけど、どうしていいかわからないような状態でした。
当時、風呂敷とあわせて和雑貨も扱っていたのですが、
最初は雑貨に光明を見出そうとしました。
ちょうど雑貨店、和雑貨店というのが増えていた頃で雑貨販売の大手さんと話しができるようになり、
取引先も増え、これならいけるんちゃうやろかと思ったのですが、
いろいろな問題があり、何年かたって雑貨は難しいという結論に至りました。
そこで、やはり自分たちのポジションを決めなあかん。
やっぱり風呂敷やろ、ということに気がつき、
もっと風呂敷について研究しないといけないのでは、
となったのが2000年くらいのことでした。
まず風呂敷の講習会をはじめました。最初は無料でやりますよと、
こちらから頼んで講習会を開催させてもらいました。
講習会では風呂敷の使い方はもちろん、
日本の伝統文化が凝縮されている柄や色についても話をするようになりました。
社長に就任したのはそうした活動が軌道にのりはじめた2004年のことです。
そういう蓄積があったのでアンテナショップ「むす美」がオープンしたときに
スムーズに風呂敷を提案することができました。
風呂敷と和雑貨の取り扱いが半々だった頃もあったのですが、
今は8対2くらいの割合になっています。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を山田社長が案内する場合、どこに案内しますか?
私は日本で唯一残っている唐紙屋の「唐長」さんへ案内したいと思います。
唐紙というのは壁紙や襖に使う紙のことです。
昔からある建築物にはたいていどこにいっても唐紙が使われています。
二条城や京都御所にもありますし、古くから残っている寺院にはほとんど唐紙が使われています。
「唐長」さんはモダンなインテリアのひとつとして唐紙を提案している会社です。
400年続く「唐長」さんの現在の主、千田堅吉さんは11代目になります。
奥さまとお子様が3人おられるのですが、皆さんが、唐紙や京都の文化を大切にしながら、
新しい世界を吸収し、唐紙をさらに価値のあるものにするために仕事に取り組んでいます。
目につくところでは四条烏丸のCOCON烏丸に外壁に使われている雲の模様が
唐長さんの持っていた柄です。
日本を代表する建築家の隈研吾さんが、
「ぜひ唐長さんの柄を使わせて欲しい」と頼まれたそうです。
そのCOCON烏丸には「唐長」さんのカードショップがはいっています。
そして三条両替町にあるショールーム。修学院には工房があって、
そこも見学できるようになっています。その3箇所にぜひ案内したいですね。
唐長さんが持っているコンテンツはたいへん素晴らしいものです。
それだけでなくご主人をはじめとする家族の方々からも京都の文化を強く感じます。
――それでは、次ぎに紹介していただく堀社長はどんな方ですか?
糸偏(繊維関係)の会社が続いたので、次は金属の会社を紹介させていただきます。
堀社長はものすごく正直やしで素直な方です。「困ったなあ、
かなわんなあ」というのも正直に言うようなところがあって、そういうところがすごく好ましい方です。
もちろん仕事に関してはたいへんシビアで、
業界では高品質な材料として広く認知されているのですが、
さらにいいものにするために常に努力をされています。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2009年2月4日取材)
■唐長HP
*********************************
 山田繊維株式会社
山田繊維株式会社
京都市中京区新町通二条南入頭町18
代表取締役 山田芳生
電話:(075)256-0123
FAX:(075)256-0256
HP:http://www.ymds.co.jp/
「むす美」HP:http://www.kyoto-musubi.com/
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――山田社長の経歴について教えてください。
大学を卒業して、アパレル大手のワールドに入社しました。
就職活動をはじめるときには、会社を継ぐことは決めていたので、
同じ繊維関係の会社にターゲットを絞り、就職活動をしました。
実は就職活動を始める前の私はほんとうに遊ぶことしか考えていないような感じで、
会社を継ぐよりも、軽い気持ちでショップやレストランなど自分で事業を起こしたいと考えていました。
ところが3回生の終わりになり就職活動をはじめるようになって、どうしようかなと悩んでいたときに、
かなり年上の先輩に「ほんまに自分でやりたいものがあるとしたら、
親父さんの会社をお前が自分でちゃんと経営ができれば、
そこで成功すれば、自分のやりたいことができる一番の近道ちゃうか」とアドバイスを受けて、
「そうか!」と納得したんですよ。
山田繊維という会社をちゃんと自分の土台にできれば、好きなことできる。
そういう邪まな気持ちが少なからずあったのですが、当時はそれですっきりしました。
自分で一から事業をはじめるにしても、土台があると強い。だから土台をしっかりさせよう。
そのための就職をしようと決心しました。
――山田繊維へはいつ入社されたのですか?
ワールドに入社したときはバブルの全盛の頃で、営業の仕事をしていました。
華やかな世界で刺激的でしたが、ほんとうに忙しい毎日でした。
それで5年たったときに東京に支店を出す話しがあり、
当時、社長だった父に「お前も東京にいけ」と言われ、「ええよ」という感じで山田繊維に入りました。
最初はワールドとの違いにカルチャーショックを受けました。
東京に支店を出したものの、風呂敷のマーケットは縮小傾向にあるような厳しい状況でしたし、
なんとかせなあかんけど、どうしていいかわからないような状態でした。
当時、風呂敷とあわせて和雑貨も扱っていたのですが、
最初は雑貨に光明を見出そうとしました。
ちょうど雑貨店、和雑貨店というのが増えていた頃で雑貨販売の大手さんと話しができるようになり、
取引先も増え、これならいけるんちゃうやろかと思ったのですが、
いろいろな問題があり、何年かたって雑貨は難しいという結論に至りました。
そこで、やはり自分たちのポジションを決めなあかん。
やっぱり風呂敷やろ、ということに気がつき、
もっと風呂敷について研究しないといけないのでは、
となったのが2000年くらいのことでした。
まず風呂敷の講習会をはじめました。最初は無料でやりますよと、
こちらから頼んで講習会を開催させてもらいました。
講習会では風呂敷の使い方はもちろん、
日本の伝統文化が凝縮されている柄や色についても話をするようになりました。
社長に就任したのはそうした活動が軌道にのりはじめた2004年のことです。
そういう蓄積があったのでアンテナショップ「むす美」がオープンしたときに
スムーズに風呂敷を提案することができました。
風呂敷と和雑貨の取り扱いが半々だった頃もあったのですが、
今は8対2くらいの割合になっています。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を山田社長が案内する場合、どこに案内しますか?
私は日本で唯一残っている唐紙屋の「唐長」さんへ案内したいと思います。
唐紙というのは壁紙や襖に使う紙のことです。
昔からある建築物にはたいていどこにいっても唐紙が使われています。
二条城や京都御所にもありますし、古くから残っている寺院にはほとんど唐紙が使われています。
「唐長」さんはモダンなインテリアのひとつとして唐紙を提案している会社です。
400年続く「唐長」さんの現在の主、千田堅吉さんは11代目になります。
奥さまとお子様が3人おられるのですが、皆さんが、唐紙や京都の文化を大切にしながら、
新しい世界を吸収し、唐紙をさらに価値のあるものにするために仕事に取り組んでいます。
目につくところでは四条烏丸のCOCON烏丸に外壁に使われている雲の模様が
唐長さんの持っていた柄です。
日本を代表する建築家の隈研吾さんが、
「ぜひ唐長さんの柄を使わせて欲しい」と頼まれたそうです。
そのCOCON烏丸には「唐長」さんのカードショップがはいっています。
そして三条両替町にあるショールーム。修学院には工房があって、
そこも見学できるようになっています。その3箇所にぜひ案内したいですね。
唐長さんが持っているコンテンツはたいへん素晴らしいものです。
それだけでなくご主人をはじめとする家族の方々からも京都の文化を強く感じます。
――それでは、次ぎに紹介していただく堀社長はどんな方ですか?
糸偏(繊維関係)の会社が続いたので、次は金属の会社を紹介させていただきます。
堀社長はものすごく正直やしで素直な方です。「困ったなあ、
かなわんなあ」というのも正直に言うようなところがあって、そういうところがすごく好ましい方です。
もちろん仕事に関してはたいへんシビアで、
業界では高品質な材料として広く認知されているのですが、
さらにいいものにするために常に努力をされています。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2009年2月4日取材)
■唐長HP
*********************************
京都市中京区新町通二条南入頭町18
代表取締役 山田芳生
電話:(075)256-0123
FAX:(075)256-0256
HP:http://www.ymds.co.jp/
「むす美」HP:http://www.kyoto-musubi.com/
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年03月10日
DVD「ふろしきレシピ」をリリースしました
第15回 山田繊維株式会社 代表取締役 山田芳生 vol.2

――今、風呂敷ブームというか、エコ的な観点から、風呂敷が見直されてきていますね
はい。ブームというにはまだ小さなものですが、
今までとは違うマーケットで風呂敷が売れています。
新しいマーケット、新しい顧客の開拓という部分で平成17年に東京でオープンした
アンテナショップ「むす美」のはたした役割は大きいですね。
実は今日(2月4日)が「むす美」のオープン記念日なのです。
毎年、公募展を開催しているのですが、昨日、東京でその授与式をやってきたところです。
今年は「ふろしき愛用フォト部門」「ふろしきエピソード部門」「手作りふろしき部門」の
三つの部門で117点の応募がありました。

――「むす美」がオープンしたとき他に風呂敷専門のショップはなかったそうですね?
そうですね。メーカーである弊社が専門店を運営する目的は、
小売に進出するということではなく、メーカーとして、
直接ユーザーと接することでいろいろ意味で緊張感をもち、
もっと質の高い風呂敷を提供するための情報収集と
風呂敷の使い方などの情報発信をしたいという考えがありました。
ただ正直なところ、最初はたった一軒のショップで情報発信ができるとは思っていませんでした。
ところがオープンしてみる当初、考えていた以上に風呂敷というものが
世の中にとっては非常に珍しいものであったようです。
オープンのレセプションを開いたところNHKが取材にきてくれて、
そのとき第1回の講習会を2月23日(風呂敷の日です)に
この「むす美」で開くと案内させていただきました。
その放送をみた多数のプレスや雑誌から講習会の取材オファーが届きました。
それ以降、多いときは月10件くらい取材がはいっていました。
今でも毎月、5件程の取材を受けています。

当時はちょうど小池百合子さんが環境大臣でした。
クールビズ・ウォームビズというのがあって、「次ぎは風呂敷よ」と
小池さんが言っていたときに「むす美」はオープン前の工事中でした。
それで、オープンして間もなく東京の三越で風呂敷のファッションショーを開催したときに
小池さんにコメントをいただいたりして、エコと風呂敷というものがうまく結びつきました。
風呂敷は工夫してものを大切に使うという面をもっています。
カバンや紙袋に比べて広い用途で使うことができます。
なにより使ったあとはコンパクトにまとめることができるので場所をとりません。
そういうところがエコロジーの考え方と共感したのでしょう。
しかし風呂敷が日本の伝統文化であり、環境にいいからと言っても、
それだけでは簡単に風呂敷を使ってもらえるものでもありません。
それ以上に、ほんまにかわいいとか、かっこいいと思ってもらえる、
ほんまにこれやったら使いたいと思ってもらえるような風呂敷を提案していかないと。
それで各イベントや講習会では環境にいいんですけど、
そんな理屈じゃなくて風呂敷をこうやって使ったらいいと思いませんか、
というような提案を続けています。
――風呂敷の結び方やつかい方を動画にまとめたDVDをリリースされたそうですね。
 はい。ちょうど「ふろしきレシピ」というDVDをリリースしたばかりです。
はい。ちょうど「ふろしきレシピ」というDVDをリリースしたばかりです。
自分で風呂敷を使うひとは問題ないのですが、風呂敷を誰かにプレゼントするとき、その相手は風呂敷の使い方や結び方を知らないかもしれません。そういうとき、風呂敷の使い方から結び方まで映像で案内できるDVDをあわせてプレゼントしてあげるといいかなと思いました。
風呂敷に特化して考えていると、いろいろアイデアが湧いてきます。和文化というと大層ですが、風呂敷が現代の生活のなかで生きているものにし続けたいですね。それこそが我々の使命であり、仕事であると今は考えています。
■山田繊維株式会社HP
■むす美HP
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――今、風呂敷ブームというか、エコ的な観点から、風呂敷が見直されてきていますね
はい。ブームというにはまだ小さなものですが、
今までとは違うマーケットで風呂敷が売れています。
新しいマーケット、新しい顧客の開拓という部分で平成17年に東京でオープンした
アンテナショップ「むす美」のはたした役割は大きいですね。
実は今日(2月4日)が「むす美」のオープン記念日なのです。
毎年、公募展を開催しているのですが、昨日、東京でその授与式をやってきたところです。
今年は「ふろしき愛用フォト部門」「ふろしきエピソード部門」「手作りふろしき部門」の
三つの部門で117点の応募がありました。

――「むす美」がオープンしたとき他に風呂敷専門のショップはなかったそうですね?
そうですね。メーカーである弊社が専門店を運営する目的は、
小売に進出するということではなく、メーカーとして、
直接ユーザーと接することでいろいろ意味で緊張感をもち、
もっと質の高い風呂敷を提供するための情報収集と
風呂敷の使い方などの情報発信をしたいという考えがありました。
ただ正直なところ、最初はたった一軒のショップで情報発信ができるとは思っていませんでした。
ところがオープンしてみる当初、考えていた以上に風呂敷というものが
世の中にとっては非常に珍しいものであったようです。
オープンのレセプションを開いたところNHKが取材にきてくれて、
そのとき第1回の講習会を2月23日(風呂敷の日です)に
この「むす美」で開くと案内させていただきました。
その放送をみた多数のプレスや雑誌から講習会の取材オファーが届きました。
それ以降、多いときは月10件くらい取材がはいっていました。
今でも毎月、5件程の取材を受けています。

当時はちょうど小池百合子さんが環境大臣でした。
クールビズ・ウォームビズというのがあって、「次ぎは風呂敷よ」と
小池さんが言っていたときに「むす美」はオープン前の工事中でした。
それで、オープンして間もなく東京の三越で風呂敷のファッションショーを開催したときに
小池さんにコメントをいただいたりして、エコと風呂敷というものがうまく結びつきました。
風呂敷は工夫してものを大切に使うという面をもっています。
カバンや紙袋に比べて広い用途で使うことができます。
なにより使ったあとはコンパクトにまとめることができるので場所をとりません。
そういうところがエコロジーの考え方と共感したのでしょう。
しかし風呂敷が日本の伝統文化であり、環境にいいからと言っても、
それだけでは簡単に風呂敷を使ってもらえるものでもありません。
それ以上に、ほんまにかわいいとか、かっこいいと思ってもらえる、
ほんまにこれやったら使いたいと思ってもらえるような風呂敷を提案していかないと。
それで各イベントや講習会では環境にいいんですけど、
そんな理屈じゃなくて風呂敷をこうやって使ったらいいと思いませんか、
というような提案を続けています。
――風呂敷の結び方やつかい方を動画にまとめたDVDをリリースされたそうですね。
 はい。ちょうど「ふろしきレシピ」というDVDをリリースしたばかりです。
はい。ちょうど「ふろしきレシピ」というDVDをリリースしたばかりです。自分で風呂敷を使うひとは問題ないのですが、風呂敷を誰かにプレゼントするとき、その相手は風呂敷の使い方や結び方を知らないかもしれません。そういうとき、風呂敷の使い方から結び方まで映像で案内できるDVDをあわせてプレゼントしてあげるといいかなと思いました。
風呂敷に特化して考えていると、いろいろアイデアが湧いてきます。和文化というと大層ですが、風呂敷が現代の生活のなかで生きているものにし続けたいですね。それこそが我々の使命であり、仕事であると今は考えています。
■山田繊維株式会社HP
■むす美HP
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年03月09日
ものがなく不便な時代に風呂敷はたいへん便利なものでした
第15回 山田繊維株式会社 代表取締役 山田芳生 vol.1

京朋株式会社の室木社長から、たいへんおしゃれでスマートな方と
紹介をいただいた山田繊維の山田社長です。
山田繊維株式会社は風呂敷を中心した和雑貨の製造メーカーです。
原宿に出店したアンテナショップ「むす美」が各メディアで取り上げられるなど、
“ふろしき”の新しい使い方を提案しています。
――創業は戦前の昭和12年ということですが、当時から風呂敷を中心に扱われていたのですか?
私の祖父が創業した当時は風呂敷や綿の反物など、綿素材のものを中心に扱っていました。
祖父は岐阜の農家の次男だったのですが、商売が好きだったので京都に丁稚として出てきて、
それからのれんわけをして独立しました。
ところが、それからすぐに戦争が始まったので、岐阜の田舎へ疎開することになります。
疎開先ではパンや文房具など、とにかく商売になるものであればなんでも売っていました。
というより商売をすること自体難しい時代だったのでしょう。
いろいろ役にたてることがあればということで、なんでも屋みたいな感じだったようです。
戦争が終わり、また京都で商売をしたいということで昭和20何年かに京都に戻り再スタートを切り、
昭和34年に山田繊維という会社組織を立ち上げることとなりました。
そのとき祖父は丁稚奉公に出していた私の父を家に戻し、
従業員をあわせて5~6名の会社でした。
そのときの取扱い商品は100%風呂敷でした。
――前回、室木社長に呉服は70年代に売上のピークを迎えたとうかがったのですが、風呂敷も同じような状況だったのですか?
いえ。会社の創業当時の方が風呂敷は売れていました。正確なデータはないのですが、
風呂敷は戦後まもなく売上のピークを迎えていたのではないでしょうか。
もしかすると戦前の方が売れていたかも知れません。
今、風呂敷を買おうと思ったら、百貨店の呉服売り場などを思い浮かべますよね。
ところが祖父が創業した当時、風呂敷は鍋や釜、軍手などと一緒に
日用雑貨品として売られていました。
もちろん当時も婚礼やセレモニーではシルクなどの高級素材をつかった風呂敷が
使われていたのですが、一般的に風呂敷といえば日用雑貨品でした。
ものがなく不便な時代には、なんでも包むことができ、手に提げたり、
大きな荷物になるとそのまま背中に背負うことができる風呂敷はたいへん便利なものでした。
ところが戦後、社会的なインフラが整備されると、
わざわざ自分で荷物を提げて持っていくようなことがだんだん少なくなりました。
何を運ぶにも自家用車に積み込むようになり、カバンもどんどん便利になってきます。
教科書や弁当を風呂敷に包んでいた時代と比べると、
風呂敷の流通が極端に減ったのは容易に想像ができますよね。
誰もが使うような日用雑貨品ではなくなったのです。
■山田繊維株式会社HP
■むす美HP
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】

京朋株式会社の室木社長から、たいへんおしゃれでスマートな方と
紹介をいただいた山田繊維の山田社長です。
山田繊維株式会社は風呂敷を中心した和雑貨の製造メーカーです。
原宿に出店したアンテナショップ「むす美」が各メディアで取り上げられるなど、
“ふろしき”の新しい使い方を提案しています。
――創業は戦前の昭和12年ということですが、当時から風呂敷を中心に扱われていたのですか?
私の祖父が創業した当時は風呂敷や綿の反物など、綿素材のものを中心に扱っていました。
祖父は岐阜の農家の次男だったのですが、商売が好きだったので京都に丁稚として出てきて、
それからのれんわけをして独立しました。
ところが、それからすぐに戦争が始まったので、岐阜の田舎へ疎開することになります。
疎開先ではパンや文房具など、とにかく商売になるものであればなんでも売っていました。
というより商売をすること自体難しい時代だったのでしょう。
いろいろ役にたてることがあればということで、なんでも屋みたいな感じだったようです。
戦争が終わり、また京都で商売をしたいということで昭和20何年かに京都に戻り再スタートを切り、
昭和34年に山田繊維という会社組織を立ち上げることとなりました。
そのとき祖父は丁稚奉公に出していた私の父を家に戻し、
従業員をあわせて5~6名の会社でした。
そのときの取扱い商品は100%風呂敷でした。
――前回、室木社長に呉服は70年代に売上のピークを迎えたとうかがったのですが、風呂敷も同じような状況だったのですか?
いえ。会社の創業当時の方が風呂敷は売れていました。正確なデータはないのですが、
風呂敷は戦後まもなく売上のピークを迎えていたのではないでしょうか。
もしかすると戦前の方が売れていたかも知れません。
今、風呂敷を買おうと思ったら、百貨店の呉服売り場などを思い浮かべますよね。
ところが祖父が創業した当時、風呂敷は鍋や釜、軍手などと一緒に
日用雑貨品として売られていました。
もちろん当時も婚礼やセレモニーではシルクなどの高級素材をつかった風呂敷が
使われていたのですが、一般的に風呂敷といえば日用雑貨品でした。
ものがなく不便な時代には、なんでも包むことができ、手に提げたり、
大きな荷物になるとそのまま背中に背負うことができる風呂敷はたいへん便利なものでした。
ところが戦後、社会的なインフラが整備されると、
わざわざ自分で荷物を提げて持っていくようなことがだんだん少なくなりました。
何を運ぶにも自家用車に積み込むようになり、カバンもどんどん便利になってきます。
教科書や弁当を風呂敷に包んでいた時代と比べると、
風呂敷の流通が極端に減ったのは容易に想像ができますよね。
誰もが使うような日用雑貨品ではなくなったのです。
■山田繊維株式会社HP
■むす美HP
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】