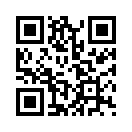2008年12月15日
「和のスタイル」が中心にあります。
第13回 株式会社三才 専務取締役 斉藤上太郎 vol.3
――今後も着物以外のデザインに挑戦するほか、どのようなビジネスを展開していきたいとお考えですか?
 ほかのことに挑戦すれば挑戦するほど、京都ブランドの価値をありがたいと思いますし、着物をやっていてよかったと思いますね。
ほかのことに挑戦すれば挑戦するほど、京都ブランドの価値をありがたいと思いますし、着物をやっていてよかったと思いますね。
最近は着物雑誌より建築雑誌に声をかけてもらい取材されることが多くて、「いろんなことやっていますね」と言われるけれど、結局、「和のスタイル」が中心にあって、たくさんある枝葉の中から、これならプラスになる、これならやっていけると思ったことだけやっています。
「和のスタイル」に拘って掘り下げるときに基本が大事になりますよね。間違えてほりさげてしまうとチープになってしまいます。モダンジャポニズムを新しければよいという風に履き違えると難しいですね。
やっぱり着物は絹であるべきだと思います。ポリではどうしても安っぽくなります。しわをのばす為に、前の晩から衣文掛けや、ハンガーにかけるなど、手間をかけることも大切です。手間のかかる仕種も着物を着る楽しみのひとつですし、そういう手間を、着物を着るストーリーとして楽しめるようなマニアの方を増やしていきたいですね。
私どもは京都で活動し、生産しているので、他所の着物や、海外はもとより国内のほかの産地にも値段では勝負になりません。でも京都だからこそ勝てるポイントやアピールできるポイントもあって、そこを大切にしていきたいですね。私はチープじゃないものを提案したいと考えていますし、実際安い着物ではなく、ステキな着物が欲しいというお客さまが私のところへ来てくれています。
私はやっぱり自分の会社らしいことしかしていません。斉藤さんのとこならではとか、三才さんとこならやりそうやなあ、ということしかやっていません。逆に他所でもやれることをやろうとは思いませんし、これからも弊社にしかできないことをやっていきたいですね。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を斉藤専務が案内する場合、どこに案内しますか?
誰を案内するかによりますよね、男性なのか、女性なのかでかわりますよね(笑)。
そのなかでひとつといえば、黒谷さん、金戒光明寺からずっと歩いて、
真如堂へ抜けてという散歩道ですね。
いわゆる京都の観光コースではなく、生活と密着したエリアです。
立派な観光案内や解説はできないのですが、ずっとあの辺で育ったので、
ここに亀がいっぱいいて、この砂場でアリジゴクを掘ったことがあるとか、
自分のエピソードがたくさんあります。
そういうエピソードを話しながら、自分のルーツを辿る旅みたいな感じで案内したいですね。
――それでは、次ぎに紹介していただく室木社長はどんな方ですか?
きものの加工元卸業の最大手の会社に紆余曲折を経て社長に就任された27歳の若き社長です。
業界に旋風を起こした伝説的なカリスマ創業者・大江茂様(現相談役)のお孫さんにあたります。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年11月18日取材)
■金戒光明寺HP
■真如堂HP
*********************************
 株式会社三才
株式会社三才
京都市北区出雲路俵町43
専務取締役 斉藤上太郎
電話:(075)256-2011
FAX:(075)256-2013
HP:http://www.san-sai.com/(株式会社三才)
http://www.jotaro.net/(斉藤上太郎)
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――今後も着物以外のデザインに挑戦するほか、どのようなビジネスを展開していきたいとお考えですか?
最近は着物雑誌より建築雑誌に声をかけてもらい取材されることが多くて、「いろんなことやっていますね」と言われるけれど、結局、「和のスタイル」が中心にあって、たくさんある枝葉の中から、これならプラスになる、これならやっていけると思ったことだけやっています。
「和のスタイル」に拘って掘り下げるときに基本が大事になりますよね。間違えてほりさげてしまうとチープになってしまいます。モダンジャポニズムを新しければよいという風に履き違えると難しいですね。
やっぱり着物は絹であるべきだと思います。ポリではどうしても安っぽくなります。しわをのばす為に、前の晩から衣文掛けや、ハンガーにかけるなど、手間をかけることも大切です。手間のかかる仕種も着物を着る楽しみのひとつですし、そういう手間を、着物を着るストーリーとして楽しめるようなマニアの方を増やしていきたいですね。
私どもは京都で活動し、生産しているので、他所の着物や、海外はもとより国内のほかの産地にも値段では勝負になりません。でも京都だからこそ勝てるポイントやアピールできるポイントもあって、そこを大切にしていきたいですね。私はチープじゃないものを提案したいと考えていますし、実際安い着物ではなく、ステキな着物が欲しいというお客さまが私のところへ来てくれています。
私はやっぱり自分の会社らしいことしかしていません。斉藤さんのとこならではとか、三才さんとこならやりそうやなあ、ということしかやっていません。逆に他所でもやれることをやろうとは思いませんし、これからも弊社にしかできないことをやっていきたいですね。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を斉藤専務が案内する場合、どこに案内しますか?
誰を案内するかによりますよね、男性なのか、女性なのかでかわりますよね(笑)。
そのなかでひとつといえば、黒谷さん、金戒光明寺からずっと歩いて、
真如堂へ抜けてという散歩道ですね。
いわゆる京都の観光コースではなく、生活と密着したエリアです。
立派な観光案内や解説はできないのですが、ずっとあの辺で育ったので、
ここに亀がいっぱいいて、この砂場でアリジゴクを掘ったことがあるとか、
自分のエピソードがたくさんあります。
そういうエピソードを話しながら、自分のルーツを辿る旅みたいな感じで案内したいですね。
――それでは、次ぎに紹介していただく室木社長はどんな方ですか?
きものの加工元卸業の最大手の会社に紆余曲折を経て社長に就任された27歳の若き社長です。
業界に旋風を起こした伝説的なカリスマ創業者・大江茂様(現相談役)のお孫さんにあたります。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年11月18日取材)
■金戒光明寺HP
■真如堂HP
*********************************
京都市北区出雲路俵町43
専務取締役 斉藤上太郎
電話:(075)256-2011
FAX:(075)256-2013
HP:http://www.san-sai.com/(株式会社三才)
http://www.jotaro.net/(斉藤上太郎)
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年12月12日
世界のなかで弊社が踊れる踊り場を見つけました。
第13回 株式会社三才 専務取締役 斉藤上太郎 vol.2
――さきほど着姿を重視して着物をデザインしているという話しがあったのですが、他に大切にしていることはありますか?
 昔から「なんで着物を着ないんですか?」といったアンケートをすると、たいがい高いから、着られないから、着る場所がないからという答えが集まるのですが、そうではないと思うのです。
昔から「なんで着物を着ないんですか?」といったアンケートをすると、たいがい高いから、着られないから、着る場所がないからという答えが集まるのですが、そうではないと思うのです。
実際、今の日本の女性は美しくなるために月に十万くらい化粧品にお金をかけている方がたくさんいらっしゃいますし、スタイルがよくみえる何十万もするボディスーツや、足首が細くみえる5万円のパンストがよく売れたりしています。
やっぱりステキな着物を作らないと。「あのひとは洋服もステキやけど和服姿もステキやねぇ、私も和ダンスをあけてみようかな」と思わせたり、生活のリズムのなかで和の心を楽しむようなスタイルを提案していかないといけないと思います。ステキということがなにより説得力があって、そのために何をすべきなのかは常に考えています。
日本に古くから脈々と繋がる文化や技術は世界から非常にリスペクトされています。京都にいるとなかなかわからないのですが、外に出て客観的にみるとこんなにすごいことはなくて、今でも日常的にその国の伝統的な衣装を着る先進国は日本以外に見当たりません。少なくはなっているのですが、現在も着物で生活をされている方が大勢いらっしゃいます。世界の片田舎の島国で、独自の文化ができあがり、それが残っているということは実はすごいことなのです。
 日本の侘びさびや禅スタイルについては昔からジャポニズムとして、尊敬されていました。また近年はゲームやアニメ、コスプレを通じて、また日本マニアが増えてきていますが、それとは別にその文化の奥や背景を知りたい、取り入れたいという強い欲求があって、そのときに京都のほんものに頼みたいと言われることが多いです。
日本の侘びさびや禅スタイルについては昔からジャポニズムとして、尊敬されていました。また近年はゲームやアニメ、コスプレを通じて、また日本マニアが増えてきていますが、それとは別にその文化の奥や背景を知りたい、取り入れたいという強い欲求があって、そのときに京都のほんものに頼みたいと言われることが多いです。
だから私は今の日本っぽいものではなく、これからの新しいジャポニズムを作りたいと思っています。着物はもちろんインテリアもこれまであったものの焼き直しではなく、新しいジャポニズムスタイルの暮らしや、空間を提案していきたいですね。
文化や伝統を継承することはもちろん大切なことですが、それだけではなく今の感覚なり、時代性を取り入れ次の世代の禅スタイルや侘びさび、次ぎの世代につながる新しいジャポニズムスタイルの提案ができるのは京都では私のところだけだという自負はあります。だからそれを追求しようと思うし、それの一番になりたいと思っています。
※写真は「2008 Collection GOTHIC CAMELLIA」より
――「和を楽しむライフスタイルを提案したい」という理念に繋がると思うのですが、着物だけでなく、インテリアなどさまざまなデザインにも手がけられていますね。
インテリアなど、着物以外のことに取り組みはじめて4年目になります。
当時は古いマンションをホテルにリノベーションすることがはやった時期で、
そのホテルのロビーに置くソファに着物を張りたいという依頼がありました。
昔から西陣織を椅子に張ったりとか、
きれいな帯地をつかってランプシェードをつくったりしたらという発想はありました。
ただ、そういう織りや着物は基本的に工芸品なので、
朝から晩まで一日中、電気の明かりにさらされて、
色やけしたり、色がとんでしまうかも知れません。
それに西陣織が帯に向いていても、椅子にしたときに強度はどうなるのかという問題もありました。
最初は「高くつきますし、やれいわれたらやりますけどねえ」という返事しかできなかったのですが、
偶然そういう依頼がぽんぽんとふたつ続いて、本気で取り組んでみる気になりました。
まずはシルクをポリエステルに全部かえるところからはじめました。
糸の素材をかえるだけでも、織る際に静電気が起こって
糸がプチプチきれやすくなるなど、様々な問題が発生しました。
生地の強度についても、最初をどのあたりを基準にすればいいのかわかりませんでした。
ちょうどそのとき高級なイタリアの椅子のメーカーさんから、コラボしないかという話しがあって、
生地の強度についての基準をいただいたのです。
試行錯誤を重ねた結果、一回目に完成した生地にそこそこ強度があり、
クオリティの高いものをつくることができました。
これまでにない特殊な織物を使うことにより、
インテリアの分野にもデザインの幅を広げることが可能になりました。

「SOFA Collaborated with ROCKSTONE」
新しい生地をもとに、直接いろんなところへ販売したいと考えて、
まあ右も左もわからない状態で、ある見本市に出展しました。
開催者もHPをみたら着物しかないですけど、
何を出展されるのですかと問い合わせがあったくらいでした。
でも、見本市に出ることによって、世界の名だたるメーカーと
京都のいちメーカーが同じ立場にたつことができました。
視察だけではやはりわからない部分があって、出展し、横並びになることで、
ここがあかんのやなあとか、他にはない弊社の特徴を確認するなど、
いろいろな意見を頂くことにより、これまでにない見方のも発見がありました。
なにより世界の服飾・テキスタイルのなかで
弊社が踊れる踊り場がちゃんとあると理解できました。
二回目以降はもっとかしこくなって、狙いを定めて出展することにより、
お客さまに仕事をいただくようになりました。ずいぶんお金はかかったのですが・・・(笑)。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――さきほど着姿を重視して着物をデザインしているという話しがあったのですが、他に大切にしていることはありますか?
 昔から「なんで着物を着ないんですか?」といったアンケートをすると、たいがい高いから、着られないから、着る場所がないからという答えが集まるのですが、そうではないと思うのです。
昔から「なんで着物を着ないんですか?」といったアンケートをすると、たいがい高いから、着られないから、着る場所がないからという答えが集まるのですが、そうではないと思うのです。実際、今の日本の女性は美しくなるために月に十万くらい化粧品にお金をかけている方がたくさんいらっしゃいますし、スタイルがよくみえる何十万もするボディスーツや、足首が細くみえる5万円のパンストがよく売れたりしています。
やっぱりステキな着物を作らないと。「あのひとは洋服もステキやけど和服姿もステキやねぇ、私も和ダンスをあけてみようかな」と思わせたり、生活のリズムのなかで和の心を楽しむようなスタイルを提案していかないといけないと思います。ステキということがなにより説得力があって、そのために何をすべきなのかは常に考えています。
日本に古くから脈々と繋がる文化や技術は世界から非常にリスペクトされています。京都にいるとなかなかわからないのですが、外に出て客観的にみるとこんなにすごいことはなくて、今でも日常的にその国の伝統的な衣装を着る先進国は日本以外に見当たりません。少なくはなっているのですが、現在も着物で生活をされている方が大勢いらっしゃいます。世界の片田舎の島国で、独自の文化ができあがり、それが残っているということは実はすごいことなのです。
 日本の侘びさびや禅スタイルについては昔からジャポニズムとして、尊敬されていました。また近年はゲームやアニメ、コスプレを通じて、また日本マニアが増えてきていますが、それとは別にその文化の奥や背景を知りたい、取り入れたいという強い欲求があって、そのときに京都のほんものに頼みたいと言われることが多いです。
日本の侘びさびや禅スタイルについては昔からジャポニズムとして、尊敬されていました。また近年はゲームやアニメ、コスプレを通じて、また日本マニアが増えてきていますが、それとは別にその文化の奥や背景を知りたい、取り入れたいという強い欲求があって、そのときに京都のほんものに頼みたいと言われることが多いです。だから私は今の日本っぽいものではなく、これからの新しいジャポニズムを作りたいと思っています。着物はもちろんインテリアもこれまであったものの焼き直しではなく、新しいジャポニズムスタイルの暮らしや、空間を提案していきたいですね。
文化や伝統を継承することはもちろん大切なことですが、それだけではなく今の感覚なり、時代性を取り入れ次の世代の禅スタイルや侘びさび、次ぎの世代につながる新しいジャポニズムスタイルの提案ができるのは京都では私のところだけだという自負はあります。だからそれを追求しようと思うし、それの一番になりたいと思っています。
※写真は「2008 Collection GOTHIC CAMELLIA」より
――「和を楽しむライフスタイルを提案したい」という理念に繋がると思うのですが、着物だけでなく、インテリアなどさまざまなデザインにも手がけられていますね。
インテリアなど、着物以外のことに取り組みはじめて4年目になります。
当時は古いマンションをホテルにリノベーションすることがはやった時期で、
そのホテルのロビーに置くソファに着物を張りたいという依頼がありました。
昔から西陣織を椅子に張ったりとか、
きれいな帯地をつかってランプシェードをつくったりしたらという発想はありました。
ただ、そういう織りや着物は基本的に工芸品なので、
朝から晩まで一日中、電気の明かりにさらされて、
色やけしたり、色がとんでしまうかも知れません。
それに西陣織が帯に向いていても、椅子にしたときに強度はどうなるのかという問題もありました。
最初は「高くつきますし、やれいわれたらやりますけどねえ」という返事しかできなかったのですが、
偶然そういう依頼がぽんぽんとふたつ続いて、本気で取り組んでみる気になりました。
まずはシルクをポリエステルに全部かえるところからはじめました。
糸の素材をかえるだけでも、織る際に静電気が起こって
糸がプチプチきれやすくなるなど、様々な問題が発生しました。
生地の強度についても、最初をどのあたりを基準にすればいいのかわかりませんでした。
ちょうどそのとき高級なイタリアの椅子のメーカーさんから、コラボしないかという話しがあって、
生地の強度についての基準をいただいたのです。
試行錯誤を重ねた結果、一回目に完成した生地にそこそこ強度があり、
クオリティの高いものをつくることができました。
これまでにない特殊な織物を使うことにより、
インテリアの分野にもデザインの幅を広げることが可能になりました。

「SOFA Collaborated with ROCKSTONE」
新しい生地をもとに、直接いろんなところへ販売したいと考えて、
まあ右も左もわからない状態で、ある見本市に出展しました。
開催者もHPをみたら着物しかないですけど、
何を出展されるのですかと問い合わせがあったくらいでした。
でも、見本市に出ることによって、世界の名だたるメーカーと
京都のいちメーカーが同じ立場にたつことができました。
視察だけではやはりわからない部分があって、出展し、横並びになることで、
ここがあかんのやなあとか、他にはない弊社の特徴を確認するなど、
いろいろな意見を頂くことにより、これまでにない見方のも発見がありました。
なにより世界の服飾・テキスタイルのなかで
弊社が踊れる踊り場がちゃんとあると理解できました。
二回目以降はもっとかしこくなって、狙いを定めて出展することにより、
お客さまに仕事をいただくようになりました。ずいぶんお金はかかったのですが・・・(笑)。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年12月11日
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案しています。
第13回 株式会社三才 専務取締役 斉藤上太郎 vol.1

株式会社福永念珠舗の福永荘三社長から、古き良きものを知り大切にしながら、なによりも豊かな感性で新しい着物を作り上げている着物デザイナーです、と紹介をいただいた株式会社三才の斉藤上太郎専務取締役です。株式会社三才は鴨川の出雲路橋の近く、閑静な住宅街にあり、「斉藤三才」「斉藤上太郎」の二大ブランドを主体としたキモノ・和装品のトータルな製造・企画を行っている会社です。
――株式会社三才は斉藤専務の祖父が創業されたそうですね。
はい。私の祖父、先代の三才が染色加工業として昭和8年に創業しました。
着物を染めるいわゆる染屋ですね。戦時中は休業している時期もあったのですが、
戦後の昭和24年に再開して、現在は私の父が三才の名前を継いで、社長に就任しています。
基本的に着物は着物屋さんや染屋さんが作って、
帯は帯屋さんが作ってという風に完全な分業制のため、
着物と帯の組み合わせをトータルで考えてデザインをすることはありませんでした。
結果的になんでもあわせやすい着物や帯が多くなり、同じような柄の着物や帯ばかりでした。
そういったなかで父の三才が着物のデザインをはじめました。
ものづくりの世界では着物に限らずデザインをする作家と、
ものをつくる職人はわかれているのですが、
父は着物をワンピース、帯をベルトとして考え、
こういう柄のワンピースに合うのはこういうベルトという感じで同じ柄でデザインするなど、
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案したはじめての作家でした。
たとえば日本人は小柄で背が低いので、帯で着物を上下にわけるより、
着物と同系や同色、同柄のデザインで一体化させ
すきっとしたスタイルをみせた方がよりおしゃれな着姿になります。
父や弊社の工場はそういう提案をするのが同業の中でも早く、
僕もそういう形でデザインをしています。
――斉藤専務は27歳の若さで作家としてデビューされたのですね。
そうですね。京都造形芸術大学の前身の京都芸短を20歳で卒業して、すぐに三才に入社しました。
でも最初は親父に洋服をやらせてくれ頼み、着物ではなくアパレルをやっていました。
当時はまだバブルの頃で会社にも余裕があったのだと思います。
「やれるものならやってみいや」と言われまして、
アパレルのブランドを立ち上げて、デザインから取引先の開拓まで全部自分でやりました。
最初は高級ブティックに飛び込みで営業もしました。
ほかにも洋服の素材として絹以外の様々なコットンやレーヨン、ポリを触ったのは
よい経験になりました。組成も理解できるようになりました。
着物は工芸品という側面もあるのですが、洋服というのはやはり工業製品であって、
例えば洗濯に耐えられる強度があるのか、というところから着物とは違う問題があるのです。
そういうことも含めて独学でトライしたことは、すごいプラスになっています。
まあ、たいした儲けもあがらなかったのですが、
大きなメーカーさんとも付き合いができたし、自信になりました。
結局、7年ほどアパレルの方で頑張っていたのですが、
27歳のときにそろそろ着物をせえへんかと言われたんですね。
当時、27歳といえばまだまだ作家の前例がない年齢で、
今でこそ30歳前後の作家がいるのですが、10年前といえば、
私の上は40代のなかばくらいの方でした。
着物作家としてデビューするときに、着物業界のさる御方に
「着物と洋服の二束の草鞋を履くことはあいならん」と言われました。
そのときアパレルの方は、次ぎの展開を考えると、直営店を出店したり、
人を増やしたり、本気で続けるのであれば、かなり費用もかかることだったので、
その方に後押しをして頂いたのは渡りに船だと思い完全に着物に切り替えることにしました。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社福永念珠舗の福永荘三社長から、古き良きものを知り大切にしながら、なによりも豊かな感性で新しい着物を作り上げている着物デザイナーです、と紹介をいただいた株式会社三才の斉藤上太郎専務取締役です。株式会社三才は鴨川の出雲路橋の近く、閑静な住宅街にあり、「斉藤三才」「斉藤上太郎」の二大ブランドを主体としたキモノ・和装品のトータルな製造・企画を行っている会社です。
――株式会社三才は斉藤専務の祖父が創業されたそうですね。
はい。私の祖父、先代の三才が染色加工業として昭和8年に創業しました。
着物を染めるいわゆる染屋ですね。戦時中は休業している時期もあったのですが、
戦後の昭和24年に再開して、現在は私の父が三才の名前を継いで、社長に就任しています。
基本的に着物は着物屋さんや染屋さんが作って、
帯は帯屋さんが作ってという風に完全な分業制のため、
着物と帯の組み合わせをトータルで考えてデザインをすることはありませんでした。
結果的になんでもあわせやすい着物や帯が多くなり、同じような柄の着物や帯ばかりでした。
そういったなかで父の三才が着物のデザインをはじめました。
ものづくりの世界では着物に限らずデザインをする作家と、
ものをつくる職人はわかれているのですが、
父は着物をワンピース、帯をベルトとして考え、
こういう柄のワンピースに合うのはこういうベルトという感じで同じ柄でデザインするなど、
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案したはじめての作家でした。
たとえば日本人は小柄で背が低いので、帯で着物を上下にわけるより、
着物と同系や同色、同柄のデザインで一体化させ
すきっとしたスタイルをみせた方がよりおしゃれな着姿になります。
父や弊社の工場はそういう提案をするのが同業の中でも早く、
僕もそういう形でデザインをしています。
――斉藤専務は27歳の若さで作家としてデビューされたのですね。
そうですね。京都造形芸術大学の前身の京都芸短を20歳で卒業して、すぐに三才に入社しました。
でも最初は親父に洋服をやらせてくれ頼み、着物ではなくアパレルをやっていました。
当時はまだバブルの頃で会社にも余裕があったのだと思います。
「やれるものならやってみいや」と言われまして、
アパレルのブランドを立ち上げて、デザインから取引先の開拓まで全部自分でやりました。
最初は高級ブティックに飛び込みで営業もしました。
ほかにも洋服の素材として絹以外の様々なコットンやレーヨン、ポリを触ったのは
よい経験になりました。組成も理解できるようになりました。
着物は工芸品という側面もあるのですが、洋服というのはやはり工業製品であって、
例えば洗濯に耐えられる強度があるのか、というところから着物とは違う問題があるのです。
そういうことも含めて独学でトライしたことは、すごいプラスになっています。
まあ、たいした儲けもあがらなかったのですが、
大きなメーカーさんとも付き合いができたし、自信になりました。
結局、7年ほどアパレルの方で頑張っていたのですが、
27歳のときにそろそろ着物をせえへんかと言われたんですね。
当時、27歳といえばまだまだ作家の前例がない年齢で、
今でこそ30歳前後の作家がいるのですが、10年前といえば、
私の上は40代のなかばくらいの方でした。
着物作家としてデビューするときに、着物業界のさる御方に
「着物と洋服の二束の草鞋を履くことはあいならん」と言われました。
そのときアパレルの方は、次ぎの展開を考えると、直営店を出店したり、
人を増やしたり、本気で続けるのであれば、かなり費用もかかることだったので、
その方に後押しをして頂いたのは渡りに船だと思い完全に着物に切り替えることにしました。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】