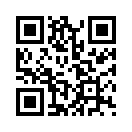2008年10月09日
本物を極めていくのが京都の文化だと思います。
第11回 株式会社土井志ば漬本舗 土井健資社長 vol.3

――社長の経歴にについて教えてください。
大学を卒業して、すぐに入社したのですが、最初の勤務先は東京の日本橋の三越でした。
当時、「京の味どころ」というコーナーがあり、そのコーナー全体の管理者として配属になりました。
弊社の製品だけでなく、京都の十数社の製品をお預かりして、一緒に販売をしていました。
東京には2年半か、3年くらい勤務して京都に戻り、漬物茶屋の「花ぢり」の店長を任されました。
――2001年の創業100周年の年に社長に就任されたそうですね。
はい。私が28歳のときに父が亡くなったあと、叔父とコンビを組んで経営に取り組んでいました。
そして、創業100周年の節目の年に社長に就任したのです。
実は同じ年に京都の青年会議所の理事長にも就任しました。
ちょうど京都の青年会議所も50周年の節目で、
両方のビジョンを考えないといけないハードな一年でした。
ただ21世紀を迎える世紀の変わり目にそういう役がまわってきたことは、チャンスだとも思いました。
一日は24時間あるのだから精一杯、時間の工夫をして、取り組みました。
私自身、追い込まれると強いタイプなので、創意工夫を凝らして、
できひんこともやってしまったような感じです(笑)。
――京都の活性化ついてはどのようにお考えですか?
京都っていうのはそれぞれの商売がいい意味で完全に分業しています。
皆んなで全部いっしょにやるのは京都では難しいのではないでしょうか。
まず自分のところをしっかりと活性化していく。
古いものを大事しながら、チャレンジ精神を忘れずにそれぞれが頑張ることです。
京都は玄関を掃いても、自分のとこだけ。水うちをするのも自分のとこだけというところがあります。
でも隣がやっていたら、うちもやる。そうして自然に拡がっていくのが理想だと思います。
また新しいものよりも、本物を極めていくのが京都の文化だと思います。
東京のように新しいものがどんどん出来て、変化し続けるのではなく、
変化が早いこの時代にも焦る必要はないし、
今のように経済が鈍いときはゆっくり商売をしたらいいと思います。
京都にはそういったあいもかわらずという姿勢がいちばん大事なのではないでしょうか。
いつの時代も土井はここに在るし、変わらぬご愛顧を賜っている。それが大切な姿勢ですね。
これからの若い世代のひとは、絆を大事にしながら自分がどんな位置にいるのか、
この時代にやらないといけないのか把握してやっていかないと。
弊社に例えると、父親がものすごく大きな花を咲かしました。
その畑を自分がまた平らにしています。そして息子の時代に、
また大きな花が咲いたらいいと思っています。
それが私の経営観であり人生観であり、京都に思うことです。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を土井社長が案内する場合、どこに案内しますか?
自分の好き嫌いで決まらないことなので、ひとつを選ぶのは難しいですね。
あえて言うなら、やはり三千院の紅葉かなぁ。ほんまにきれいやしね。
あと、今、大原で朝市が繁盛しているのですよ。
里の人々は夜中から起きて朝市の準備をしています。私も早いときは5時半に起きるけど、
そのときにはもう野菜がたくさん並んでいるような状態です。
9時か10時になると、もう売り切れて何も残っていません。
ぜひ早起きして、一度、朝市に足を運んでみてください。
――それでは、次ぎに紹介していただく福永社長はどんな方ですか?
いつも明るく、元気のよいバイタリティあふれた社長さんです。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年9月12日取材)
■三千院HP
*********************************
 株式会社 土井志ば漬本舗
株式会社 土井志ば漬本舗
京都市左京区八瀬花尻町41
代表取締役 土井 健資
電話:(075)744-2311
FAX:(075)744-2317
HP:http://www.doishibazuke.co.jp/
<
■株式会社土井志ば漬本舗 土井健資 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――社長の経歴にについて教えてください。
大学を卒業して、すぐに入社したのですが、最初の勤務先は東京の日本橋の三越でした。
当時、「京の味どころ」というコーナーがあり、そのコーナー全体の管理者として配属になりました。
弊社の製品だけでなく、京都の十数社の製品をお預かりして、一緒に販売をしていました。
東京には2年半か、3年くらい勤務して京都に戻り、漬物茶屋の「花ぢり」の店長を任されました。
――2001年の創業100周年の年に社長に就任されたそうですね。
はい。私が28歳のときに父が亡くなったあと、叔父とコンビを組んで経営に取り組んでいました。
そして、創業100周年の節目の年に社長に就任したのです。
実は同じ年に京都の青年会議所の理事長にも就任しました。
ちょうど京都の青年会議所も50周年の節目で、
両方のビジョンを考えないといけないハードな一年でした。
ただ21世紀を迎える世紀の変わり目にそういう役がまわってきたことは、チャンスだとも思いました。
一日は24時間あるのだから精一杯、時間の工夫をして、取り組みました。
私自身、追い込まれると強いタイプなので、創意工夫を凝らして、
できひんこともやってしまったような感じです(笑)。
――京都の活性化ついてはどのようにお考えですか?
京都っていうのはそれぞれの商売がいい意味で完全に分業しています。
皆んなで全部いっしょにやるのは京都では難しいのではないでしょうか。
まず自分のところをしっかりと活性化していく。
古いものを大事しながら、チャレンジ精神を忘れずにそれぞれが頑張ることです。
京都は玄関を掃いても、自分のとこだけ。水うちをするのも自分のとこだけというところがあります。
でも隣がやっていたら、うちもやる。そうして自然に拡がっていくのが理想だと思います。
また新しいものよりも、本物を極めていくのが京都の文化だと思います。
東京のように新しいものがどんどん出来て、変化し続けるのではなく、
変化が早いこの時代にも焦る必要はないし、
今のように経済が鈍いときはゆっくり商売をしたらいいと思います。
京都にはそういったあいもかわらずという姿勢がいちばん大事なのではないでしょうか。
いつの時代も土井はここに在るし、変わらぬご愛顧を賜っている。それが大切な姿勢ですね。
これからの若い世代のひとは、絆を大事にしながら自分がどんな位置にいるのか、
この時代にやらないといけないのか把握してやっていかないと。
弊社に例えると、父親がものすごく大きな花を咲かしました。
その畑を自分がまた平らにしています。そして息子の時代に、
また大きな花が咲いたらいいと思っています。
それが私の経営観であり人生観であり、京都に思うことです。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を土井社長が案内する場合、どこに案内しますか?
自分の好き嫌いで決まらないことなので、ひとつを選ぶのは難しいですね。
あえて言うなら、やはり三千院の紅葉かなぁ。ほんまにきれいやしね。
あと、今、大原で朝市が繁盛しているのですよ。
里の人々は夜中から起きて朝市の準備をしています。私も早いときは5時半に起きるけど、
そのときにはもう野菜がたくさん並んでいるような状態です。
9時か10時になると、もう売り切れて何も残っていません。
ぜひ早起きして、一度、朝市に足を運んでみてください。
――それでは、次ぎに紹介していただく福永社長はどんな方ですか?
いつも明るく、元気のよいバイタリティあふれた社長さんです。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年9月12日取材)
■三千院HP
*********************************
 株式会社 土井志ば漬本舗
株式会社 土井志ば漬本舗京都市左京区八瀬花尻町41
代表取締役 土井 健資
電話:(075)744-2311
FAX:(075)744-2317
HP:http://www.doishibazuke.co.jp/
<
■株式会社土井志ば漬本舗 土井健資 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年10月08日
弊社の社章はナスが上を向いた形になっています。
第11回 株式会社土井志ば漬本舗 土井健資社長 vol.2

――大原という土地に根ざした経営をされているのですね。
弊社は1901年(明治34年)に自家栽培で漬け込んだ先祖伝来のしば漬や木の芽煮など、
大原で採れる山菜の販売をはじめたところからスタートしています。
弊社の志ば漬は大原の農家でつくっているものと違いはありません。
また大原の玄関口に本社があるので、
町並みを損なわないよう紫の色と白い壁をモチーフにしたデザインの本館と熟成館を建てました。
おかげさまで両館とも京都市の美観風致賞をいただきました。
また人材に関してもできるだけ、地域の方を優先して採用しています。
地域と足並みを揃えた地道な活動が、地域への貢献や活性化につながるのではないかと思います。
――乳酸発酵についても研究しているそうですね。
はい。しば漬は健康によいと昔から言われていました。
そこで何が健康に良く、どう作用しているのかを解明したいと思っていました。
しば漬の酸味は乳酸菌の乳酸発酵によるものです。
乳酸菌のなかにラクトバチルス・ブレビスというすごい菌があって、
それを抽出して土井44菌という株菌を取り出しました。
その菌が、人間が健康的な生活を送るために必要なアミノ酸のひとつである
ギャバの成長を促進させるスターターとして作用することが解りました。
そこで、その菌を取り出して、ぬか漬けなどの他の製品にいれなおして、
健康でからだによいものをというコンセプトのもとに製品化しました。
――温故一新という言葉を経営理念に掲げていますね。
はい。「伝統を大切に、先人の智恵に学び心一新。新たな“志”を胸に研鑽を重ね、
精進し愛される商品づくりを目指す」ということです。
“志”という部分では、社員全員が企業にぶらさがるのではなく、
たえず上を向いて、向上心をもって仕事に取り組みましょうということで、
弊社の社章はナスが上を向いた形になっています。それが企業の姿勢であり、
社名を「土井志ば漬本舗」にしているのも“志”がしっかりありますよというメッセージです。
何かをよりよくするためには、どうしていたらいいのか探り続けないといけません。
固定概念を捨て、違う角度で見るようにしないと新しいものはうまれてきません。
商品開発でも、社内で何回テストしても、
「これ売れるのかな」という商品が意外に売り上げを伸ばし、
お客様からの声で定番化されることがあります。お客様の反応を大切にしながら、
古い技術と新しい技術を合体させたときにはじめて新しい商品が完成するのです。
■土井志ば漬本舗HP
■株式会社土井志ば漬本舗 土井健資 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――大原という土地に根ざした経営をされているのですね。
弊社は1901年(明治34年)に自家栽培で漬け込んだ先祖伝来のしば漬や木の芽煮など、
大原で採れる山菜の販売をはじめたところからスタートしています。
弊社の志ば漬は大原の農家でつくっているものと違いはありません。
また大原の玄関口に本社があるので、
町並みを損なわないよう紫の色と白い壁をモチーフにしたデザインの本館と熟成館を建てました。
おかげさまで両館とも京都市の美観風致賞をいただきました。
また人材に関してもできるだけ、地域の方を優先して採用しています。
地域と足並みを揃えた地道な活動が、地域への貢献や活性化につながるのではないかと思います。
――乳酸発酵についても研究しているそうですね。
はい。しば漬は健康によいと昔から言われていました。
そこで何が健康に良く、どう作用しているのかを解明したいと思っていました。
しば漬の酸味は乳酸菌の乳酸発酵によるものです。
乳酸菌のなかにラクトバチルス・ブレビスというすごい菌があって、
それを抽出して土井44菌という株菌を取り出しました。
その菌が、人間が健康的な生活を送るために必要なアミノ酸のひとつである
ギャバの成長を促進させるスターターとして作用することが解りました。
そこで、その菌を取り出して、ぬか漬けなどの他の製品にいれなおして、
健康でからだによいものをというコンセプトのもとに製品化しました。
――温故一新という言葉を経営理念に掲げていますね。
はい。「伝統を大切に、先人の智恵に学び心一新。新たな“志”を胸に研鑽を重ね、
精進し愛される商品づくりを目指す」ということです。
“志”という部分では、社員全員が企業にぶらさがるのではなく、
たえず上を向いて、向上心をもって仕事に取り組みましょうということで、
弊社の社章はナスが上を向いた形になっています。それが企業の姿勢であり、
社名を「土井志ば漬本舗」にしているのも“志”がしっかりありますよというメッセージです。
何かをよりよくするためには、どうしていたらいいのか探り続けないといけません。
固定概念を捨て、違う角度で見るようにしないと新しいものはうまれてきません。
商品開発でも、社内で何回テストしても、
「これ売れるのかな」という商品が意外に売り上げを伸ばし、
お客様からの声で定番化されることがあります。お客様の反応を大切にしながら、
古い技術と新しい技術を合体させたときにはじめて新しい商品が完成するのです。
■土井志ば漬本舗HP
■株式会社土井志ば漬本舗 土井健資 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年10月07日
なにも足さないほんまもんです。
第11回 株式会社土井志ば漬本舗 土井健資社長 vol.1
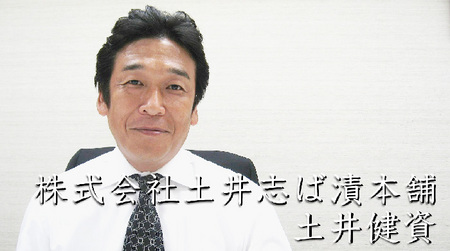
有限会社晦庵 河道屋の植田健社長から、私より年齢がひとまわり下になるのですが、
若くて仕事を熱心にやってはる社長さんです、と紹介をいただいた
株式会社土井志ば漬本舗の土井健資社長です。
株式会社土井志ば漬本舗は京都市の北部、大原の里にあります。
京都から福井県小浜へ抜ける鯖街道沿いに本社をかまえています。
――京都はお漬物がおいしいところで、その中でも大原といえば、
やはりしば漬のイメージが強いのですが?
はい。大原のしば漬の起源はいまから800年以上も前にまでさかのぼります。
壇ノ浦の戦いに敗れ、平家一族の数少ない生き残りとなった建礼門院は
この大原で平家一族の冥福を祈りながら過ごしていました。
そんな建礼門院の悲しんでおられる姿をみた大原の里人は、何か献上できるものはないかと、
夏野菜の残りものを漬けた漬け物をお持ちしたところ、
「なんときれいな紫の葉漬け」と言われたということです。
そこから紫葉漬(しばづけ)と呼ばれるようになったということです。
それ以来、しば漬は大原の里でどこの家でも当たり前のように漬けて、
普段からよく食べられています。それが地域の名産となり、
現在では京ブランドの認定も受けています。
――夏になると緑の水田と紫の紫蘇畑のコントラストがきれいですよね。
この大原の地で育つ紫蘇は中国古来の赤紫蘇の原種に近いものです。
おそらく山々に囲まれた盆地特有の地形によって、別種との交配が防がれたのではないでしょうか。
しば漬に使う紫蘇はちりめん赤紫蘇といって、ぐちゅぐちゅと縮れたような葉が特徴です。
これは昼夜の温度差によって紫蘇の葉が大きくなったり、
小さくなったりして、よくもまれているからなのです。
大葉と紫蘇は同じ品種ですが、香りの強さがまったく違います。
武田薬品で成分分析をしてもらった結果、大原で採れる紫蘇がもっとも香りが強く、
この地での栽培がもっとも適していると証明されました。
また気温の差は、しば漬を漬ける際の乳酸発酵も促進させます。
夏の暑い時期に日中と夜間の気温の差があることで、より赤く染まるように作用します。
京都市内に本社のある大手の漬物メーカーも、しば漬に関しては、
特定の農家などと契約して大原で漬けています。
大原の地形や気候、気温が乳酸発酵に適しているのです。
当社ではしば漬に使用する紫蘇を毎日、必要な分だけ刈り取るようにしています。
例えば、京田辺の契約農家から千両なすが4トン届くとすると、
それに必要な紫蘇を直営の農場で刈り取って、樽に漬けていきます。
もちろん合成保存料や着色料は使いません。
自然発酵したものに、なにも足さないほんまもんです。
■土井志ば漬本舗HP
■株式会社土井志ば漬本舗 土井健資 【1】 >> 【2】 >> 【3】
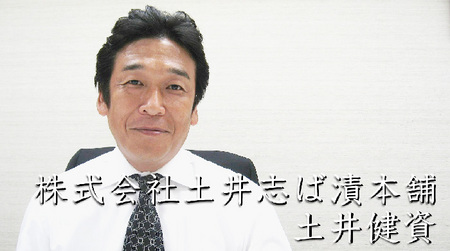
有限会社晦庵 河道屋の植田健社長から、私より年齢がひとまわり下になるのですが、
若くて仕事を熱心にやってはる社長さんです、と紹介をいただいた
株式会社土井志ば漬本舗の土井健資社長です。
株式会社土井志ば漬本舗は京都市の北部、大原の里にあります。
京都から福井県小浜へ抜ける鯖街道沿いに本社をかまえています。
――京都はお漬物がおいしいところで、その中でも大原といえば、
やはりしば漬のイメージが強いのですが?
はい。大原のしば漬の起源はいまから800年以上も前にまでさかのぼります。
壇ノ浦の戦いに敗れ、平家一族の数少ない生き残りとなった建礼門院は
この大原で平家一族の冥福を祈りながら過ごしていました。
そんな建礼門院の悲しんでおられる姿をみた大原の里人は、何か献上できるものはないかと、
夏野菜の残りものを漬けた漬け物をお持ちしたところ、
「なんときれいな紫の葉漬け」と言われたということです。
そこから紫葉漬(しばづけ)と呼ばれるようになったということです。
それ以来、しば漬は大原の里でどこの家でも当たり前のように漬けて、
普段からよく食べられています。それが地域の名産となり、
現在では京ブランドの認定も受けています。
――夏になると緑の水田と紫の紫蘇畑のコントラストがきれいですよね。
この大原の地で育つ紫蘇は中国古来の赤紫蘇の原種に近いものです。
おそらく山々に囲まれた盆地特有の地形によって、別種との交配が防がれたのではないでしょうか。
しば漬に使う紫蘇はちりめん赤紫蘇といって、ぐちゅぐちゅと縮れたような葉が特徴です。
これは昼夜の温度差によって紫蘇の葉が大きくなったり、
小さくなったりして、よくもまれているからなのです。
大葉と紫蘇は同じ品種ですが、香りの強さがまったく違います。
武田薬品で成分分析をしてもらった結果、大原で採れる紫蘇がもっとも香りが強く、
この地での栽培がもっとも適していると証明されました。
また気温の差は、しば漬を漬ける際の乳酸発酵も促進させます。
夏の暑い時期に日中と夜間の気温の差があることで、より赤く染まるように作用します。
京都市内に本社のある大手の漬物メーカーも、しば漬に関しては、
特定の農家などと契約して大原で漬けています。
大原の地形や気候、気温が乳酸発酵に適しているのです。
当社ではしば漬に使用する紫蘇を毎日、必要な分だけ刈り取るようにしています。
例えば、京田辺の契約農家から千両なすが4トン届くとすると、
それに必要な紫蘇を直営の農場で刈り取って、樽に漬けていきます。
もちろん合成保存料や着色料は使いません。
自然発酵したものに、なにも足さないほんまもんです。
■土井志ば漬本舗HP
■株式会社土井志ば漬本舗 土井健資 【1】 >> 【2】 >> 【3】