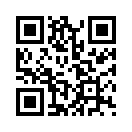2008年09月10日
京都は町にリピーターが付いています。
第10回 有限会社晦庵 河道屋 植田健社長 vol.3

――植田社長は商社に勤めていたとうかがったのですが?
はい。私は同志社大学を卒業して、東京の商社に就職しました。
私が東京へ行くのと入れかわるようにして、東京の蕎麦屋で働いていた兄が京都に戻りました。
私は商社で働いていたのですが、結局3年で京都に呼び戻され、
父の右腕だった大番頭に蕎麦の打ち方を習いました。
私はよその蕎麦屋に修行にいかなかったので、河道屋の蕎麦しか知りません。
そういう意味では頑固です。食の嗜好が多様化している現在では、
私のように古いものばかりに固執していてはいけないのですが、
逆に流行りに流されてはいけないと思っています。
――観光客も多いんですね。
そうですね。昔から馴染みのお客さまももちろん大事なのですが、
わざわざ調べて食べに来てくれる観光客の方はありがたいですね。
京都は町にリピーターが付いているので、
修学旅行で当店の蕎麦を食べていただいた方が、また観光で来てくれたり、
新婚旅行で来てくれたカップルが、何年も経って、
また銀婚式で京都を訪れた際に食べに来てくれます。
この頃は海外の方も多いですね。特に欧州からの方が多いように思われます。
やはり欧州の方は京都の文化や歴史に深い興味を持っていただいているのでしょうか。
この九月には、昭和40年頃に建てた新館を改装します。
一階に厨房があって、二階に座敷の部屋があったのですが、その座敷を改装して椅子席にします。
ちょっと二階にあがって頂くのは手間なのですが、
ざっくり30人はいる座敷を、ゆったりと24人の椅子席にするので、
団塊の世代の方や年配の方にも、ゆっくり蕎麦を味わっていただきたいと思っています。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を植田社長が案内する場合、どこに案内しますか?
ここという場所はありません。そのひとにあわせます。
何がみたいか?何に興味を持っているのか?それを聴いてからです。
何を求めているか分からないと案内することはできません。
「禅」に興味があるのか、「わびさび」に興味があるのか、
「お茶」に興味があるのか、「お花」に興味があるのか。
まず、どんなところに行きたいのか聴かないといけません。
この人はここ、この人やったらここ。みんな違うと思います。
みんな違っても、それに対応できるのが京都のよさだと思います。
――それでは、次ぎに紹介していただく土井社長はどんな方ですか?
私より年齢がひとまわりしたになるのですが、若くて仕事を熱心にやってはる社長さんです。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年8月8日取材)
*********************************
 有限会社晦庵河道屋
有限会社晦庵河道屋
京都市中京区麩屋町通三条上ル
代表取締役 植田健
電話:(075)221-2525
FAX:(075)231-8507
HP:http://www.kawamichiya.co.jp/soba/
■有限会社晦庵 河道屋 植田健 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――植田社長は商社に勤めていたとうかがったのですが?
はい。私は同志社大学を卒業して、東京の商社に就職しました。
私が東京へ行くのと入れかわるようにして、東京の蕎麦屋で働いていた兄が京都に戻りました。
私は商社で働いていたのですが、結局3年で京都に呼び戻され、
父の右腕だった大番頭に蕎麦の打ち方を習いました。
私はよその蕎麦屋に修行にいかなかったので、河道屋の蕎麦しか知りません。
そういう意味では頑固です。食の嗜好が多様化している現在では、
私のように古いものばかりに固執していてはいけないのですが、
逆に流行りに流されてはいけないと思っています。
――観光客も多いんですね。
そうですね。昔から馴染みのお客さまももちろん大事なのですが、
わざわざ調べて食べに来てくれる観光客の方はありがたいですね。
京都は町にリピーターが付いているので、
修学旅行で当店の蕎麦を食べていただいた方が、また観光で来てくれたり、
新婚旅行で来てくれたカップルが、何年も経って、
また銀婚式で京都を訪れた際に食べに来てくれます。
この頃は海外の方も多いですね。特に欧州からの方が多いように思われます。
やはり欧州の方は京都の文化や歴史に深い興味を持っていただいているのでしょうか。
この九月には、昭和40年頃に建てた新館を改装します。
一階に厨房があって、二階に座敷の部屋があったのですが、その座敷を改装して椅子席にします。
ちょっと二階にあがって頂くのは手間なのですが、
ざっくり30人はいる座敷を、ゆったりと24人の椅子席にするので、
団塊の世代の方や年配の方にも、ゆっくり蕎麦を味わっていただきたいと思っています。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を植田社長が案内する場合、どこに案内しますか?
ここという場所はありません。そのひとにあわせます。
何がみたいか?何に興味を持っているのか?それを聴いてからです。
何を求めているか分からないと案内することはできません。
「禅」に興味があるのか、「わびさび」に興味があるのか、
「お茶」に興味があるのか、「お花」に興味があるのか。
まず、どんなところに行きたいのか聴かないといけません。
この人はここ、この人やったらここ。みんな違うと思います。
みんな違っても、それに対応できるのが京都のよさだと思います。
――それでは、次ぎに紹介していただく土井社長はどんな方ですか?
私より年齢がひとまわりしたになるのですが、若くて仕事を熱心にやってはる社長さんです。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年8月8日取材)
*********************************
京都市中京区麩屋町通三条上ル
代表取締役 植田健
電話:(075)221-2525
FAX:(075)231-8507
HP:http://www.kawamichiya.co.jp/soba/
■有限会社晦庵 河道屋 植田健 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年09月09日
「芳香炉(ほうこうろ)」は蕎麦屋の鍋料理のさきがけでした。
第10回 有限会社晦庵 河道屋 植田健社長 vol.2
――蕎麦について教えてください。
蕎麦は最澄さんが中国から伝えたという説もあるのですが、もっと古くから日本にあるようです。
蕎麦はいわゆる五穀に入らないのですが、荒れ地でも育ち、高たんぱくで栄養価が高く、
飢饉があっても植えてから75日で収穫できるので、飢饉食としても有用でした。
五穀断ちをする延暦寺の千日回峰行でも、蕎麦を食べて栄養を採るそうです。
延暦寺といえば、毎年、桓武天皇の命日である5月17日には延暦寺に登り、
手打ち蕎麦を献供するのが当家のならわしとなっていて、江戸期より100年以上も続いています。

――河道屋といえば「芳香炉(ほうこうろ)」と「辛味大根」が有名ですね。
「芳香炉(ほうこうろ)」は昭和7年にこの晦庵が出来たときから、メニューにありました。
当時は座敷で大勢がいっしょに召し上がっていただくものがなく、
みんなで一緒に食べていただきたいということで作ったのが「芳香炉(ほうこうろ)」です。
昭和7年からここの名物で、蕎麦屋の鍋料理のさきがけでした。
中央に煙突のついた特徴のある鍋を使うのですが、
元々その鍋は満州のおみやげで「火鍋子(ほうこうず)」と言いました。
それを「芳香炉(ほうこうろ)」として売り出したわけです。
お野菜や鶏肉、湯葉をいれ、煮ながら召し上がっていただき、
最後にお蕎麦で締めていただきます。
これが当店のおすすめというか、成り立ちからの看板商品ですね。
辛味大根は鷹峰の農家の方が作ったものを使用しています。
実は、鷹峰の辛味大根は一時、消費量が減って、生産農家が一軒になってしまったのを、
父が全部買い取るからと約束して、生産を続けてもらったのです。
今もその方に大根を作ってもらっていて、私も4代からの付き合いになります。
昨今は京野菜のブームもあって、他の農家の方も作るようになりました。
京都の他にも長野あたりでも作っていて市場にまわっています。
当店では鷹峰の辛味大根を新蕎麦の出る10月から、
年が明けて3月20日まで扱うようにしています。
3月20日は大石内蔵助の命日で、祇園の「一力亭」で大石忌が営まれ、
その行事に当店の蕎麦の薬味として出しています。
――吉田神社の節分祭りでの年越し蕎麦は何年続いてるんですか?
吉田神社の節分祭りに店を出すようになったのは昭和26年のことで、
父が言い出してはじめたのがきっかけです。今年で56回目になるのかな。
私が生まれた年にはじまったのですよ。
料理の神様を奉っている山蔭神社の前の参道に店を出しているのですが、
河道屋ののれんわけしたお店や、取引先の方にも声をかけ、
年に一度、河道屋の結束を固めています。
■晦庵 河道屋HP
■比叡山延暦寺HP
■吉田神社HP
■有限会社晦庵 河道屋 植田健 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――蕎麦について教えてください。
蕎麦は最澄さんが中国から伝えたという説もあるのですが、もっと古くから日本にあるようです。
蕎麦はいわゆる五穀に入らないのですが、荒れ地でも育ち、高たんぱくで栄養価が高く、
飢饉があっても植えてから75日で収穫できるので、飢饉食としても有用でした。
五穀断ちをする延暦寺の千日回峰行でも、蕎麦を食べて栄養を採るそうです。
延暦寺といえば、毎年、桓武天皇の命日である5月17日には延暦寺に登り、
手打ち蕎麦を献供するのが当家のならわしとなっていて、江戸期より100年以上も続いています。
――河道屋といえば「芳香炉(ほうこうろ)」と「辛味大根」が有名ですね。
「芳香炉(ほうこうろ)」は昭和7年にこの晦庵が出来たときから、メニューにありました。
当時は座敷で大勢がいっしょに召し上がっていただくものがなく、
みんなで一緒に食べていただきたいということで作ったのが「芳香炉(ほうこうろ)」です。
昭和7年からここの名物で、蕎麦屋の鍋料理のさきがけでした。
中央に煙突のついた特徴のある鍋を使うのですが、
元々その鍋は満州のおみやげで「火鍋子(ほうこうず)」と言いました。
それを「芳香炉(ほうこうろ)」として売り出したわけです。
お野菜や鶏肉、湯葉をいれ、煮ながら召し上がっていただき、
最後にお蕎麦で締めていただきます。
これが当店のおすすめというか、成り立ちからの看板商品ですね。
辛味大根は鷹峰の農家の方が作ったものを使用しています。
実は、鷹峰の辛味大根は一時、消費量が減って、生産農家が一軒になってしまったのを、
父が全部買い取るからと約束して、生産を続けてもらったのです。
今もその方に大根を作ってもらっていて、私も4代からの付き合いになります。
昨今は京野菜のブームもあって、他の農家の方も作るようになりました。
京都の他にも長野あたりでも作っていて市場にまわっています。
当店では鷹峰の辛味大根を新蕎麦の出る10月から、
年が明けて3月20日まで扱うようにしています。
3月20日は大石内蔵助の命日で、祇園の「一力亭」で大石忌が営まれ、
その行事に当店の蕎麦の薬味として出しています。
――吉田神社の節分祭りでの年越し蕎麦は何年続いてるんですか?
吉田神社の節分祭りに店を出すようになったのは昭和26年のことで、
父が言い出してはじめたのがきっかけです。今年で56回目になるのかな。
私が生まれた年にはじまったのですよ。
料理の神様を奉っている山蔭神社の前の参道に店を出しているのですが、
河道屋ののれんわけしたお店や、取引先の方にも声をかけ、
年に一度、河道屋の結束を固めています。
■晦庵 河道屋HP
■比叡山延暦寺HP
■吉田神社HP
■有限会社晦庵 河道屋 植田健 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年09月08日
数寄者だった祖父が、晦庵をスタートさせました。
第10回 有限会社晦庵 河道屋 植田健社長 vol.1

株式会社三嶋亭の三嶌太郎社長から、正業の職に真面目にとりくんだほがらかな方で、
人柄もよく、仕事に一生懸命はげんでおられる社長さんです、
と紹介をいただいた有限会社晦庵河道屋の植田健社長です。
晦庵河道屋は江戸時代から続く生そばの老舗です。
――蕎麦ほうるで有名な「総本家河道屋」とは元々同じ会社だったそうですね。
はい。もとはひとつの会社だったのを私の父が会社組織としては
“蕎麦ほうる”を扱う「株式会社総本家 河道屋」と
“蕎麦”の「有限会社晦庵 河道屋」とに分けたのです。
父が存命中は、父が会長として「晦庵 河道屋」の社長を兼任していました。
父が亡くなってから「晦庵 河道屋」の社長に私がなりました。
「総本家 河道屋」の社長は兄が継いでいます。
――「河道屋」は江戸時代から続いているそうですね?
河道屋の成り立ちは現存する記録としては享保8年(1723年)になります。
当時の町内の書きつけが残っています。
また明治の頃に書かれた家伝の書には、
元禄(1688~1703年)から宝永(1704~1710年)年間には
上京の方で商いをしていたとされています。
それが火事にあって、現在の場所に移ってきたということです。
この場所に来て何年経っていたかは分からないのですが、
享保8年にはこの場所にあったということです。
そこで創業300年くらいといっています。
――当時からお菓子とお蕎麦で商売をされていたのですか?
当店は高価な砂糖をつかうような上物の菓子屋ではなく庶民の菓子屋だったそうです。
そういう菓子屋では、菓子と並んで蕎麦切りを売っていました。
お菓子の傍らで蕎麦などの麺類を売るのは、
江戸時代には、わりと一般的な形態だったようです。
なのでお菓子とお蕎麦、どっちが本業だったのかは厳密にはわからないのです。
明治期には、お蕎麦の方が繁盛していたのですが、
明治から大正の頃に「蕎麦ほうる」を復活させ、評判になったということです。
――晦庵が分かれたのはいつになるのですか?
私の祖父が「総本家 河道屋」で「蕎麦ほうる」と両方やっていた蕎麦の部門をきりはなし、
昭和7年に蕎麦屋を現在の晦庵のある地に移しました。
祖父はお茶をよく嗜むような数寄者だったので、
数奇屋作りの建物をたてて、晦庵をスタートさせました。
今の建物は昭和7年に建てられたものなので、
古くはなっているのですが、この風情を大切にしたいですね。
■晦庵 河道屋HP
■河道屋HP
■有限会社晦庵 河道屋 植田健 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社三嶋亭の三嶌太郎社長から、正業の職に真面目にとりくんだほがらかな方で、
人柄もよく、仕事に一生懸命はげんでおられる社長さんです、
と紹介をいただいた有限会社晦庵河道屋の植田健社長です。
晦庵河道屋は江戸時代から続く生そばの老舗です。
――蕎麦ほうるで有名な「総本家河道屋」とは元々同じ会社だったそうですね。
はい。もとはひとつの会社だったのを私の父が会社組織としては
“蕎麦ほうる”を扱う「株式会社総本家 河道屋」と
“蕎麦”の「有限会社晦庵 河道屋」とに分けたのです。
父が存命中は、父が会長として「晦庵 河道屋」の社長を兼任していました。
父が亡くなってから「晦庵 河道屋」の社長に私がなりました。
「総本家 河道屋」の社長は兄が継いでいます。
――「河道屋」は江戸時代から続いているそうですね?
河道屋の成り立ちは現存する記録としては享保8年(1723年)になります。
当時の町内の書きつけが残っています。
また明治の頃に書かれた家伝の書には、
元禄(1688~1703年)から宝永(1704~1710年)年間には
上京の方で商いをしていたとされています。
それが火事にあって、現在の場所に移ってきたということです。
この場所に来て何年経っていたかは分からないのですが、
享保8年にはこの場所にあったということです。
そこで創業300年くらいといっています。
――当時からお菓子とお蕎麦で商売をされていたのですか?
当店は高価な砂糖をつかうような上物の菓子屋ではなく庶民の菓子屋だったそうです。
そういう菓子屋では、菓子と並んで蕎麦切りを売っていました。
お菓子の傍らで蕎麦などの麺類を売るのは、
江戸時代には、わりと一般的な形態だったようです。
なのでお菓子とお蕎麦、どっちが本業だったのかは厳密にはわからないのです。
明治期には、お蕎麦の方が繁盛していたのですが、
明治から大正の頃に「蕎麦ほうる」を復活させ、評判になったということです。
――晦庵が分かれたのはいつになるのですか?
私の祖父が「総本家 河道屋」で「蕎麦ほうる」と両方やっていた蕎麦の部門をきりはなし、
昭和7年に蕎麦屋を現在の晦庵のある地に移しました。
祖父はお茶をよく嗜むような数寄者だったので、
数奇屋作りの建物をたてて、晦庵をスタートさせました。
今の建物は昭和7年に建てられたものなので、
古くはなっているのですが、この風情を大切にしたいですね。
■晦庵 河道屋HP
■河道屋HP
■有限会社晦庵 河道屋 植田健 【1】 >> 【2】 >> 【3】