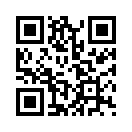2008年11月13日
おもてなしは当たり前のサービスではありません。
第12回 株式会社福永念珠舗 福永荘三社長 vol.3

――社長の経歴にについて教えてください。
七代目の祖母の横で9歳の頃から数珠を作り始めました。
「上手にできたなあ、あんたは跡取りさんやねぇ」
と頭を撫でられ褒めて頂いていたことを覚えています。
祖母がもっている千代紙の貼られた箱の中にはいったほのかに甘い菓子や、
仕事台の横には寒い季節にかじかんだ手を温めるために置いていた
手火鉢の上で焼いたくれたお餅に引き寄せられ、祖母の傍に寄り、
見よう見まねで数珠作りをしていました。
それで、中学時代までにはある程度のことはできていたのですが、
友達と外で遊ぶ方がおもしろくなって数珠を作ることから離れていた時代もありました。
特に高校・大学時代はクロスカントリースキー競技をずっと続けていて、
卒業の折にはスキーショップからサービスマンとして誘われていました。
私としては、選手としての契約ではなくても、選手の育成に関わることができれば、
また雪山に行けると考えていました。
ところがいざ就職という時分になって、同級生たちが希望する会社に入社することの難しさをしり、
数珠を作ってお客様に感謝して頂ける家業のすばらしさに気づきました。
また、八代目の父親から「いままで好きなことをやってきたのだから、
わしのいうとおり丁稚奉公に行ってこい」と言われ、跡継ぎの道を進むことにしました。
父の知り合いの関係で愛知にある仏壇屋に修行にいき、
3年間仏壇の販売と製造をさせて頂きました。
それで、京都に戻って来てから、父の弟子に入り30歳の時に技を認めて頂き専務役に、
また、父の体の都合もあり35歳で社長に就任しました。
――京都の活性化ついてはどのようにお考えですか?
今年も12月に開催される京都検定にも通じるのですが、
京都人が京都のことをよく知るということが大切だと思います。
そして京都を訪れるひとを心からおもてなしすることです。
京都は周囲を山に囲まれた盆地なので、京都に入るには山や峠を越えないと入れませんでした。
「おこしやす」という言葉は山を越えてようこそ来てくれはったという意味があります。
京都を訪れる方が、また京都に来たいという気持ちを持っていただくように、
心からのおもてなしをする。
おもてなしは当たり前のサービスではありません。
ひとりひとりが自信をもって京都のよさを伝えることです。
それだけの伝統と、ほんものが今も生きている京の町なのですから。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を福永社長が案内する場合、どこに案内しますか?
う~ん、悩みますねぇ。京都にはたくさんいい所があるからね。
それに訪れられるひとりひとり求めているものが違うだろうし。
京都で食を楽しみたいひと、その場所を楽しんだり、ほっこりしたいひと…。
あえていうなら東本願寺周辺です。
京都の玄関口、京都駅の近くは周辺に観光スポットが多くないので見逃されがちですが、
いかに大きな寺院であるのか、ぜひ足を運んで山門をくぐって欲しいですね。
観光寺院ではないので、誰でも無料で入れます。
御影堂は木造建築物では世界最大なのです。
今、瓦の葺き替えをしているのですが、
瓦を外すと瓦の重さと土の重さで数メートル高くなったそうです。
また、東本願寺の東向かいにある渉成園(しょうせいえん)もおすすめです。
園内で四季が楽しめるように庭が造られており、
それぞれの季節や趣を感じることのできる茶室がたくさんあります。
みなさんはこんなところにこんな庭園があったのと驚かれることでしょう。
――それでは、次ぎに紹介していただく斉藤さまはどんな方ですか?
着物のデザイナーでもある彼は、古き良きものを知り、大切にしています。
そして、何よりも豊かな感性で新しい着物を作り上げています。
まだまだ彼は若いのですが、私は「温故知新」を彼に感じています。
ふだんからのライフスタイルも憎らしいぐらいお洒落ですし、
ラグビーを愛するスポーツマンでもあります。
一度会えば、彼の魅力がわかって頂けると思います。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年10月7日取材)
■東本願寺HP ~渉成園~
*********************************
 株式会社福永念珠舗
株式会社福永念珠舗
京都市下京区東本願寺前 上珠数屋町角340
代表取締役九代目社長 福永荘三
電話:(075)343-0541
FAX:(075)351-0018
HP:http://www.juzz.net/
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――社長の経歴にについて教えてください。
七代目の祖母の横で9歳の頃から数珠を作り始めました。
「上手にできたなあ、あんたは跡取りさんやねぇ」
と頭を撫でられ褒めて頂いていたことを覚えています。
祖母がもっている千代紙の貼られた箱の中にはいったほのかに甘い菓子や、
仕事台の横には寒い季節にかじかんだ手を温めるために置いていた
手火鉢の上で焼いたくれたお餅に引き寄せられ、祖母の傍に寄り、
見よう見まねで数珠作りをしていました。
それで、中学時代までにはある程度のことはできていたのですが、
友達と外で遊ぶ方がおもしろくなって数珠を作ることから離れていた時代もありました。
特に高校・大学時代はクロスカントリースキー競技をずっと続けていて、
卒業の折にはスキーショップからサービスマンとして誘われていました。
私としては、選手としての契約ではなくても、選手の育成に関わることができれば、
また雪山に行けると考えていました。
ところがいざ就職という時分になって、同級生たちが希望する会社に入社することの難しさをしり、
数珠を作ってお客様に感謝して頂ける家業のすばらしさに気づきました。
また、八代目の父親から「いままで好きなことをやってきたのだから、
わしのいうとおり丁稚奉公に行ってこい」と言われ、跡継ぎの道を進むことにしました。
父の知り合いの関係で愛知にある仏壇屋に修行にいき、
3年間仏壇の販売と製造をさせて頂きました。
それで、京都に戻って来てから、父の弟子に入り30歳の時に技を認めて頂き専務役に、
また、父の体の都合もあり35歳で社長に就任しました。
――京都の活性化ついてはどのようにお考えですか?
今年も12月に開催される京都検定にも通じるのですが、
京都人が京都のことをよく知るということが大切だと思います。
そして京都を訪れるひとを心からおもてなしすることです。
京都は周囲を山に囲まれた盆地なので、京都に入るには山や峠を越えないと入れませんでした。
「おこしやす」という言葉は山を越えてようこそ来てくれはったという意味があります。
京都を訪れる方が、また京都に来たいという気持ちを持っていただくように、
心からのおもてなしをする。
おもてなしは当たり前のサービスではありません。
ひとりひとりが自信をもって京都のよさを伝えることです。
それだけの伝統と、ほんものが今も生きている京の町なのですから。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を福永社長が案内する場合、どこに案内しますか?
う~ん、悩みますねぇ。京都にはたくさんいい所があるからね。
それに訪れられるひとりひとり求めているものが違うだろうし。
京都で食を楽しみたいひと、その場所を楽しんだり、ほっこりしたいひと…。
あえていうなら東本願寺周辺です。
京都の玄関口、京都駅の近くは周辺に観光スポットが多くないので見逃されがちですが、
いかに大きな寺院であるのか、ぜひ足を運んで山門をくぐって欲しいですね。
観光寺院ではないので、誰でも無料で入れます。
御影堂は木造建築物では世界最大なのです。
今、瓦の葺き替えをしているのですが、
瓦を外すと瓦の重さと土の重さで数メートル高くなったそうです。
また、東本願寺の東向かいにある渉成園(しょうせいえん)もおすすめです。
園内で四季が楽しめるように庭が造られており、
それぞれの季節や趣を感じることのできる茶室がたくさんあります。
みなさんはこんなところにこんな庭園があったのと驚かれることでしょう。
――それでは、次ぎに紹介していただく斉藤さまはどんな方ですか?
着物のデザイナーでもある彼は、古き良きものを知り、大切にしています。
そして、何よりも豊かな感性で新しい着物を作り上げています。
まだまだ彼は若いのですが、私は「温故知新」を彼に感じています。
ふだんからのライフスタイルも憎らしいぐらいお洒落ですし、
ラグビーを愛するスポーツマンでもあります。
一度会えば、彼の魅力がわかって頂けると思います。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年10月7日取材)
■東本願寺HP ~渉成園~
*********************************
 株式会社福永念珠舗
株式会社福永念珠舗京都市下京区東本願寺前 上珠数屋町角340
代表取締役九代目社長 福永荘三
電話:(075)343-0541
FAX:(075)351-0018
HP:http://www.juzz.net/
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年11月12日
「感謝の気持ちを珠にこめて」
第12回 株式会社福永念珠舗 福永荘三社長 vol.2
――修学旅行生に数珠の手作り教室を開いているそうですね。
そうですね、もう10年以上続けています。修学旅行シーズンの春と秋は申込みが多くなりますね。
1回の教室で教えるのは、場所の都合でだいたい6~12人くらい。
ひとクラス全部が一度に来るというより、
京都観光などで班別行動している1班~2班で申込みがあるという感じですね。
体験される皆さんにひとつひとつ声をかけながら教えるので、その位の人数が丁度いいです。
今の学生さんだとビーズを作る感覚でしょうか。
それぞれの感性で色に凝ってきれいに並べる子もいておもしろいですね。
数珠を作る前に必ず数珠の歴史や意味について少し話しをします。
そして数珠を作り終えた後には「数珠は必ず輪になってますよね、
こんな意味もあるんです」とお話しします。
皆さんが10分も20分もかかって苦労をし、紐を通し終えた数珠にハサミを入れると、
いとも簡単にばらばらになってしまいます。ひとのご縁も同じです。
縁を結ぶのはたくさん時間を必要とします。
今、ここにおられる皆さんは中学や高校生の頃から数年をかけて仲良くなってこられたことでしょう。
そのご縁は数珠と同じで、その縁を自ら断つのは一瞬のことになります、と。
数珠の玉を指して、「あなたの位置する玉はどれですか?
お父さん、お母さんはどの玉?友だちは?」と訊ねると銘々が自分の玉を探し、
両親はこれ、なになに君はこれという風になります。
そこでご縁の大切さの話をすると、よく理解してもらえます。
みなさんとてもいい顔、生き生きとした眼でお戻りいただけることは、大変嬉しく思います。

――ホームページを見ると地方の百貨店やデパートの催事にも出店されているんですね。
「京都物産展」それと全国の「職人展」というのがあって、その二つに参加しています。
京都に居るとわからないのですが、
京都以外の地方では「京都物産展」がかなり頻繁に開催されています。
地方ではそれだけ京都の人気があるのでしょう。
しかし、京都ブランドに胡坐をかいではいけません。
京都のブランドというのは平安京の時代から、
そのときどきの職人がそれぞれに試行錯誤をし、伝統を残しながらも、
その時代のニーズにあったものに改革改良してきたからこそ伝統として残っていると思います。
新しいものに常に挑戦していくという側面を忘れてはいけません。
そういう伝統の技を多くのひとに知っていただきたいですね。
それと地方ではよっぽど大きな仏具屋さんでないと数珠をいくつも揃えているところは少ないのです。
たとえば10数種類の数珠が並んでいたとしても500円くらいのものから数万円のものまであって、
結局、デザインではなく、数珠の値段で、購入するものを選択されていることだと思います。
そうではなく数珠も自分の好みにあったものを、正式念珠や省略念珠等いくつもの種類の中から、
本来の数珠の形や意味を知って頂き選んで欲しいですね。
地方の催事などで数珠を購入いただいたお客さまには
京都に来たらぜひお越しください、と声をかけるようにしています。
そうしたら、京都に観光やお参りにきたときに、うちに寄ってくださるお客さまも居て、
「糸がゆるんでませんか?」と声をおかけし、
お時間が許されるなら直させていただけるようにしています。
また、お茶を飲んで頂き、話しをしているうちに、これからどこどこに行くというお話しになると、
その近くにあるおすすめのスポットや美味しい和菓子屋さん等を教えてあげます。
そうやって数珠を買っていただいたお客さまとの間にできた縁をうちの店だけでなく
京都全体のお客様として大切にしています。
――縁を大切にするというのは御社の経営理念にも繋がりますね。
「感謝の気持ちを珠にこめて」という経営理念を私の代にかかげました。
京都にあるたくさんの数珠屋のなかから、
時間の御足労と旅費を使ってまで、うちを選んで来ていただいた。
なおかついくつもある商品の中からひとつの数珠を手にとってもらえる、
そういうお客さまに対する感謝の気持ち。
また職場で共に助け合い働いている仲間に対する感謝、材料を供給してくれる職人さんだけでなく、
自然の中で大きく育ち我々の人間の手によって数珠に加工させて頂いている素材への感謝、
そして今、ここに存在する自分を生んでくれた親への感謝。
自分を取り巻くあたりまえに感じるものでさえ感謝の気持ちを忘れてはなりません。
数珠はお経を唱えた数を数えるためのものでもあるといいましたが、
在家一般の方にとっては、自然に手を合わすための法具でもあります。
ご先祖さまに対して、自分に命を繋いでくれてありがとうというのが本当の合掌なのかもしれません。
合掌は手のひらを合わすと書きます。掌は「たなごころ」ともお読みします。
ひとの心は手の平に宿っているという意味があるからなのです。
葬儀の時や先祖のお墓を前にして、手を合わすというのは心より感謝するということなのです。
そのようにお使いになるお数珠であるからこそ、
あらゆる感謝の気持ちをひとつひとつの珠にこめて数珠をつくっています。
■福永念珠舗HP
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――修学旅行生に数珠の手作り教室を開いているそうですね。
そうですね、もう10年以上続けています。修学旅行シーズンの春と秋は申込みが多くなりますね。
1回の教室で教えるのは、場所の都合でだいたい6~12人くらい。
ひとクラス全部が一度に来るというより、
京都観光などで班別行動している1班~2班で申込みがあるという感じですね。
体験される皆さんにひとつひとつ声をかけながら教えるので、その位の人数が丁度いいです。
今の学生さんだとビーズを作る感覚でしょうか。
それぞれの感性で色に凝ってきれいに並べる子もいておもしろいですね。
数珠を作る前に必ず数珠の歴史や意味について少し話しをします。
そして数珠を作り終えた後には「数珠は必ず輪になってますよね、
こんな意味もあるんです」とお話しします。
皆さんが10分も20分もかかって苦労をし、紐を通し終えた数珠にハサミを入れると、
いとも簡単にばらばらになってしまいます。ひとのご縁も同じです。
縁を結ぶのはたくさん時間を必要とします。
今、ここにおられる皆さんは中学や高校生の頃から数年をかけて仲良くなってこられたことでしょう。
そのご縁は数珠と同じで、その縁を自ら断つのは一瞬のことになります、と。
数珠の玉を指して、「あなたの位置する玉はどれですか?
お父さん、お母さんはどの玉?友だちは?」と訊ねると銘々が自分の玉を探し、
両親はこれ、なになに君はこれという風になります。
そこでご縁の大切さの話をすると、よく理解してもらえます。
みなさんとてもいい顔、生き生きとした眼でお戻りいただけることは、大変嬉しく思います。
――ホームページを見ると地方の百貨店やデパートの催事にも出店されているんですね。
「京都物産展」それと全国の「職人展」というのがあって、その二つに参加しています。
京都に居るとわからないのですが、
京都以外の地方では「京都物産展」がかなり頻繁に開催されています。
地方ではそれだけ京都の人気があるのでしょう。
しかし、京都ブランドに胡坐をかいではいけません。
京都のブランドというのは平安京の時代から、
そのときどきの職人がそれぞれに試行錯誤をし、伝統を残しながらも、
その時代のニーズにあったものに改革改良してきたからこそ伝統として残っていると思います。
新しいものに常に挑戦していくという側面を忘れてはいけません。
そういう伝統の技を多くのひとに知っていただきたいですね。
それと地方ではよっぽど大きな仏具屋さんでないと数珠をいくつも揃えているところは少ないのです。
たとえば10数種類の数珠が並んでいたとしても500円くらいのものから数万円のものまであって、
結局、デザインではなく、数珠の値段で、購入するものを選択されていることだと思います。
そうではなく数珠も自分の好みにあったものを、正式念珠や省略念珠等いくつもの種類の中から、
本来の数珠の形や意味を知って頂き選んで欲しいですね。
地方の催事などで数珠を購入いただいたお客さまには
京都に来たらぜひお越しください、と声をかけるようにしています。
そうしたら、京都に観光やお参りにきたときに、うちに寄ってくださるお客さまも居て、
「糸がゆるんでませんか?」と声をおかけし、
お時間が許されるなら直させていただけるようにしています。
また、お茶を飲んで頂き、話しをしているうちに、これからどこどこに行くというお話しになると、
その近くにあるおすすめのスポットや美味しい和菓子屋さん等を教えてあげます。
そうやって数珠を買っていただいたお客さまとの間にできた縁をうちの店だけでなく
京都全体のお客様として大切にしています。
――縁を大切にするというのは御社の経営理念にも繋がりますね。
「感謝の気持ちを珠にこめて」という経営理念を私の代にかかげました。
京都にあるたくさんの数珠屋のなかから、
時間の御足労と旅費を使ってまで、うちを選んで来ていただいた。
なおかついくつもある商品の中からひとつの数珠を手にとってもらえる、
そういうお客さまに対する感謝の気持ち。
また職場で共に助け合い働いている仲間に対する感謝、材料を供給してくれる職人さんだけでなく、
自然の中で大きく育ち我々の人間の手によって数珠に加工させて頂いている素材への感謝、
そして今、ここに存在する自分を生んでくれた親への感謝。
自分を取り巻くあたりまえに感じるものでさえ感謝の気持ちを忘れてはなりません。
数珠はお経を唱えた数を数えるためのものでもあるといいましたが、
在家一般の方にとっては、自然に手を合わすための法具でもあります。
ご先祖さまに対して、自分に命を繋いでくれてありがとうというのが本当の合掌なのかもしれません。
合掌は手のひらを合わすと書きます。掌は「たなごころ」ともお読みします。
ひとの心は手の平に宿っているという意味があるからなのです。
葬儀の時や先祖のお墓を前にして、手を合わすというのは心より感謝するということなのです。
そのようにお使いになるお数珠であるからこそ、
あらゆる感謝の気持ちをひとつひとつの珠にこめて数珠をつくっています。
■福永念珠舗HP
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年11月11日
伝統工芸についてさまざまな発信をすることが大切なのです。
第12回 株式会社福永念珠舗 福永荘三社長 vol.1

株式会社土井志ば漬本舗の土井健資社長から、いつも明るく、
元気のよいバイタリティあふれた社長さんです、
と紹介をいただいた株式会社福永念珠舗の福永荘三社長です。
株式会社福永念珠舗は東本願寺の向側にあり、
数珠(念珠)の製造・販売を行う専門店です。
――東本願寺が正面に見えるのですが、以前より東本願寺の職人だったそうですね。
はい。初代は長浜市新庄馬場町にある誓伝寺の出身です。
誓伝寺の次男である弊社初代は真宗大谷派の本山、
東本願寺でお役にたてればと京都に出てきました。
手先が器用だったのか最初は小間物商として、江戸中期に創業し、
数珠を含めていろいろなものを作っていたのですが、
寛政9年(1797年初代亡)には数珠専門になりました。
当時は自分で商いをするというより、お寺より依頼されたものをつくっていました。
寺の周りには数珠を作る職人の他にも、宮大工や掛軸職人、仏壇・仏具職人など、
専門の分野に分かれた職人が住んでいました。
現在の様子は烏丸通をはさんで弊社の社屋が建っているので、
門前町のように思われがちですが、江戸時代の東本願寺領地はずっと広く、
現在の場所も敷地のなかでした。
この辺りを「寺内町」とよんだ江戸時代の資料も残っています。
――一般的には数珠と呼ぶのだと思うのですが、御社は福永「念珠」舗なんですね。
数珠は元来、仏教の行に使う法具でした。
たとえば、お経を唱えた回数を数えることに使われていました。
仏教の起源はインドからシルクロードを経て中国にはいってきた仏教はさらに日本をはじめ、
朝鮮半島や台湾、沖縄に同じ頃に伝わりました。
日本に伝来してきたときに、現在の各宗派が経典を日本語に訳すのですが、
それぞれその解釈と伝え方が違っていました。
その違いは信仰や行の方法にもあらわれ、
数珠はその宗派に合った形に平安・鎌倉時代のころに変化していきました。
数珠の主玉(おもだま)108個を数えたら、そのことを記録するために小さな珠(たま)をつけたり、
行にあわせてある宗派では房の形を独特のものにしたり、
108個の数は基本的には変えずに各宗派が使いやすように法具として、
より機能的に進化していったのです。
浄土真宗各派では数を数える数珠ではなく、念珠とよぶようになりました。
――今は宗派に関わらず、各宗派の数珠を製造をしているんですね?
はい。今は各宗派の数珠を制作しています。
いまでも日本で使われている数珠の90%以上が京都で作られているようです。
なぜ京都が数珠の伝統継承される本場なのかわかりますか?
もちろん本山がたくさんあって、必要とされてきたということもあるのですが、
なにより技を持つ職人が居て、さらに数珠を作ることに必要な房や糸などの材料が
京都の伝統産業に揃っていました。
西陣織に使う織り機は、はたを織る過程で、最後に1メートルほど糸が余ってしまいます。
はし糸といって、もう織りには使えないそうです、
そのあまり糸をいただき染め直して数珠の組紐や房の制作に使っていました。
染色についても京都には伝統があるので、糸を必要とする色に染めあげることができました。
現代のように交通網が発達しているわけではないので、
近所で材料が全て揃うということはひとつの産業が育つ上で非常に重要なことだと思います。
お数珠を制作するのも、現在ではいくつもの工程に伝統工芸の技が携わっています。
たくさんの行程の中でひとつでも欠けたら伝統工芸ではなくなります。
海外に制作をゆだねるのではなく、我々が伝統を継承していく人間を育てないといけないのです。
こんな時代なので、大量生産で少しでも安いものを作ることも可能ですが、
そればかりに眼を向けてしまえば伝統工芸品と呼べるものはなくなってしまいます。
良いものが欲しい、本物が欲しい、あの人が作ったものが欲しいと思ってもらえるように、
伝統工芸についてさまざまな発信をすることが大切になってくるのです。
人間の魅力と伝統の魅力がいきているから日本はものだけでなく心も豊かなのだと思います。
■福永念珠舗HP
■東本願寺HP
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
株式会社土井志ば漬本舗の土井健資社長から、いつも明るく、
元気のよいバイタリティあふれた社長さんです、
と紹介をいただいた株式会社福永念珠舗の福永荘三社長です。
株式会社福永念珠舗は東本願寺の向側にあり、
数珠(念珠)の製造・販売を行う専門店です。
――東本願寺が正面に見えるのですが、以前より東本願寺の職人だったそうですね。
はい。初代は長浜市新庄馬場町にある誓伝寺の出身です。
誓伝寺の次男である弊社初代は真宗大谷派の本山、
東本願寺でお役にたてればと京都に出てきました。
手先が器用だったのか最初は小間物商として、江戸中期に創業し、
数珠を含めていろいろなものを作っていたのですが、
寛政9年(1797年初代亡)には数珠専門になりました。
当時は自分で商いをするというより、お寺より依頼されたものをつくっていました。
寺の周りには数珠を作る職人の他にも、宮大工や掛軸職人、仏壇・仏具職人など、
専門の分野に分かれた職人が住んでいました。
現在の様子は烏丸通をはさんで弊社の社屋が建っているので、
門前町のように思われがちですが、江戸時代の東本願寺領地はずっと広く、
現在の場所も敷地のなかでした。
この辺りを「寺内町」とよんだ江戸時代の資料も残っています。
――一般的には数珠と呼ぶのだと思うのですが、御社は福永「念珠」舗なんですね。
数珠は元来、仏教の行に使う法具でした。
たとえば、お経を唱えた回数を数えることに使われていました。
仏教の起源はインドからシルクロードを経て中国にはいってきた仏教はさらに日本をはじめ、
朝鮮半島や台湾、沖縄に同じ頃に伝わりました。
日本に伝来してきたときに、現在の各宗派が経典を日本語に訳すのですが、
それぞれその解釈と伝え方が違っていました。
その違いは信仰や行の方法にもあらわれ、
数珠はその宗派に合った形に平安・鎌倉時代のころに変化していきました。
数珠の主玉(おもだま)108個を数えたら、そのことを記録するために小さな珠(たま)をつけたり、
行にあわせてある宗派では房の形を独特のものにしたり、
108個の数は基本的には変えずに各宗派が使いやすように法具として、
より機能的に進化していったのです。
浄土真宗各派では数を数える数珠ではなく、念珠とよぶようになりました。
――今は宗派に関わらず、各宗派の数珠を製造をしているんですね?
はい。今は各宗派の数珠を制作しています。
いまでも日本で使われている数珠の90%以上が京都で作られているようです。
なぜ京都が数珠の伝統継承される本場なのかわかりますか?
もちろん本山がたくさんあって、必要とされてきたということもあるのですが、
なにより技を持つ職人が居て、さらに数珠を作ることに必要な房や糸などの材料が
京都の伝統産業に揃っていました。
西陣織に使う織り機は、はたを織る過程で、最後に1メートルほど糸が余ってしまいます。
はし糸といって、もう織りには使えないそうです、
そのあまり糸をいただき染め直して数珠の組紐や房の制作に使っていました。
染色についても京都には伝統があるので、糸を必要とする色に染めあげることができました。
現代のように交通網が発達しているわけではないので、
近所で材料が全て揃うということはひとつの産業が育つ上で非常に重要なことだと思います。
お数珠を制作するのも、現在ではいくつもの工程に伝統工芸の技が携わっています。
たくさんの行程の中でひとつでも欠けたら伝統工芸ではなくなります。
海外に制作をゆだねるのではなく、我々が伝統を継承していく人間を育てないといけないのです。
こんな時代なので、大量生産で少しでも安いものを作ることも可能ですが、
そればかりに眼を向けてしまえば伝統工芸品と呼べるものはなくなってしまいます。
良いものが欲しい、本物が欲しい、あの人が作ったものが欲しいと思ってもらえるように、
伝統工芸についてさまざまな発信をすることが大切になってくるのです。
人間の魅力と伝統の魅力がいきているから日本はものだけでなく心も豊かなのだと思います。
■福永念珠舗HP
■東本願寺HP
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】