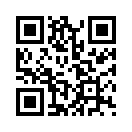2008年11月12日
「感謝の気持ちを珠にこめて」
第12回 株式会社福永念珠舗 福永荘三社長 vol.2
――修学旅行生に数珠の手作り教室を開いているそうですね。
そうですね、もう10年以上続けています。修学旅行シーズンの春と秋は申込みが多くなりますね。
1回の教室で教えるのは、場所の都合でだいたい6~12人くらい。
ひとクラス全部が一度に来るというより、
京都観光などで班別行動している1班~2班で申込みがあるという感じですね。
体験される皆さんにひとつひとつ声をかけながら教えるので、その位の人数が丁度いいです。
今の学生さんだとビーズを作る感覚でしょうか。
それぞれの感性で色に凝ってきれいに並べる子もいておもしろいですね。
数珠を作る前に必ず数珠の歴史や意味について少し話しをします。
そして数珠を作り終えた後には「数珠は必ず輪になってますよね、
こんな意味もあるんです」とお話しします。
皆さんが10分も20分もかかって苦労をし、紐を通し終えた数珠にハサミを入れると、
いとも簡単にばらばらになってしまいます。ひとのご縁も同じです。
縁を結ぶのはたくさん時間を必要とします。
今、ここにおられる皆さんは中学や高校生の頃から数年をかけて仲良くなってこられたことでしょう。
そのご縁は数珠と同じで、その縁を自ら断つのは一瞬のことになります、と。
数珠の玉を指して、「あなたの位置する玉はどれですか?
お父さん、お母さんはどの玉?友だちは?」と訊ねると銘々が自分の玉を探し、
両親はこれ、なになに君はこれという風になります。
そこでご縁の大切さの話をすると、よく理解してもらえます。
みなさんとてもいい顔、生き生きとした眼でお戻りいただけることは、大変嬉しく思います。

――ホームページを見ると地方の百貨店やデパートの催事にも出店されているんですね。
「京都物産展」それと全国の「職人展」というのがあって、その二つに参加しています。
京都に居るとわからないのですが、
京都以外の地方では「京都物産展」がかなり頻繁に開催されています。
地方ではそれだけ京都の人気があるのでしょう。
しかし、京都ブランドに胡坐をかいではいけません。
京都のブランドというのは平安京の時代から、
そのときどきの職人がそれぞれに試行錯誤をし、伝統を残しながらも、
その時代のニーズにあったものに改革改良してきたからこそ伝統として残っていると思います。
新しいものに常に挑戦していくという側面を忘れてはいけません。
そういう伝統の技を多くのひとに知っていただきたいですね。
それと地方ではよっぽど大きな仏具屋さんでないと数珠をいくつも揃えているところは少ないのです。
たとえば10数種類の数珠が並んでいたとしても500円くらいのものから数万円のものまであって、
結局、デザインではなく、数珠の値段で、購入するものを選択されていることだと思います。
そうではなく数珠も自分の好みにあったものを、正式念珠や省略念珠等いくつもの種類の中から、
本来の数珠の形や意味を知って頂き選んで欲しいですね。
地方の催事などで数珠を購入いただいたお客さまには
京都に来たらぜひお越しください、と声をかけるようにしています。
そうしたら、京都に観光やお参りにきたときに、うちに寄ってくださるお客さまも居て、
「糸がゆるんでませんか?」と声をおかけし、
お時間が許されるなら直させていただけるようにしています。
また、お茶を飲んで頂き、話しをしているうちに、これからどこどこに行くというお話しになると、
その近くにあるおすすめのスポットや美味しい和菓子屋さん等を教えてあげます。
そうやって数珠を買っていただいたお客さまとの間にできた縁をうちの店だけでなく
京都全体のお客様として大切にしています。
――縁を大切にするというのは御社の経営理念にも繋がりますね。
「感謝の気持ちを珠にこめて」という経営理念を私の代にかかげました。
京都にあるたくさんの数珠屋のなかから、
時間の御足労と旅費を使ってまで、うちを選んで来ていただいた。
なおかついくつもある商品の中からひとつの数珠を手にとってもらえる、
そういうお客さまに対する感謝の気持ち。
また職場で共に助け合い働いている仲間に対する感謝、材料を供給してくれる職人さんだけでなく、
自然の中で大きく育ち我々の人間の手によって数珠に加工させて頂いている素材への感謝、
そして今、ここに存在する自分を生んでくれた親への感謝。
自分を取り巻くあたりまえに感じるものでさえ感謝の気持ちを忘れてはなりません。
数珠はお経を唱えた数を数えるためのものでもあるといいましたが、
在家一般の方にとっては、自然に手を合わすための法具でもあります。
ご先祖さまに対して、自分に命を繋いでくれてありがとうというのが本当の合掌なのかもしれません。
合掌は手のひらを合わすと書きます。掌は「たなごころ」ともお読みします。
ひとの心は手の平に宿っているという意味があるからなのです。
葬儀の時や先祖のお墓を前にして、手を合わすというのは心より感謝するということなのです。
そのようにお使いになるお数珠であるからこそ、
あらゆる感謝の気持ちをひとつひとつの珠にこめて数珠をつくっています。
■福永念珠舗HP
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――修学旅行生に数珠の手作り教室を開いているそうですね。
そうですね、もう10年以上続けています。修学旅行シーズンの春と秋は申込みが多くなりますね。
1回の教室で教えるのは、場所の都合でだいたい6~12人くらい。
ひとクラス全部が一度に来るというより、
京都観光などで班別行動している1班~2班で申込みがあるという感じですね。
体験される皆さんにひとつひとつ声をかけながら教えるので、その位の人数が丁度いいです。
今の学生さんだとビーズを作る感覚でしょうか。
それぞれの感性で色に凝ってきれいに並べる子もいておもしろいですね。
数珠を作る前に必ず数珠の歴史や意味について少し話しをします。
そして数珠を作り終えた後には「数珠は必ず輪になってますよね、
こんな意味もあるんです」とお話しします。
皆さんが10分も20分もかかって苦労をし、紐を通し終えた数珠にハサミを入れると、
いとも簡単にばらばらになってしまいます。ひとのご縁も同じです。
縁を結ぶのはたくさん時間を必要とします。
今、ここにおられる皆さんは中学や高校生の頃から数年をかけて仲良くなってこられたことでしょう。
そのご縁は数珠と同じで、その縁を自ら断つのは一瞬のことになります、と。
数珠の玉を指して、「あなたの位置する玉はどれですか?
お父さん、お母さんはどの玉?友だちは?」と訊ねると銘々が自分の玉を探し、
両親はこれ、なになに君はこれという風になります。
そこでご縁の大切さの話をすると、よく理解してもらえます。
みなさんとてもいい顔、生き生きとした眼でお戻りいただけることは、大変嬉しく思います。
――ホームページを見ると地方の百貨店やデパートの催事にも出店されているんですね。
「京都物産展」それと全国の「職人展」というのがあって、その二つに参加しています。
京都に居るとわからないのですが、
京都以外の地方では「京都物産展」がかなり頻繁に開催されています。
地方ではそれだけ京都の人気があるのでしょう。
しかし、京都ブランドに胡坐をかいではいけません。
京都のブランドというのは平安京の時代から、
そのときどきの職人がそれぞれに試行錯誤をし、伝統を残しながらも、
その時代のニーズにあったものに改革改良してきたからこそ伝統として残っていると思います。
新しいものに常に挑戦していくという側面を忘れてはいけません。
そういう伝統の技を多くのひとに知っていただきたいですね。
それと地方ではよっぽど大きな仏具屋さんでないと数珠をいくつも揃えているところは少ないのです。
たとえば10数種類の数珠が並んでいたとしても500円くらいのものから数万円のものまであって、
結局、デザインではなく、数珠の値段で、購入するものを選択されていることだと思います。
そうではなく数珠も自分の好みにあったものを、正式念珠や省略念珠等いくつもの種類の中から、
本来の数珠の形や意味を知って頂き選んで欲しいですね。
地方の催事などで数珠を購入いただいたお客さまには
京都に来たらぜひお越しください、と声をかけるようにしています。
そうしたら、京都に観光やお参りにきたときに、うちに寄ってくださるお客さまも居て、
「糸がゆるんでませんか?」と声をおかけし、
お時間が許されるなら直させていただけるようにしています。
また、お茶を飲んで頂き、話しをしているうちに、これからどこどこに行くというお話しになると、
その近くにあるおすすめのスポットや美味しい和菓子屋さん等を教えてあげます。
そうやって数珠を買っていただいたお客さまとの間にできた縁をうちの店だけでなく
京都全体のお客様として大切にしています。
――縁を大切にするというのは御社の経営理念にも繋がりますね。
「感謝の気持ちを珠にこめて」という経営理念を私の代にかかげました。
京都にあるたくさんの数珠屋のなかから、
時間の御足労と旅費を使ってまで、うちを選んで来ていただいた。
なおかついくつもある商品の中からひとつの数珠を手にとってもらえる、
そういうお客さまに対する感謝の気持ち。
また職場で共に助け合い働いている仲間に対する感謝、材料を供給してくれる職人さんだけでなく、
自然の中で大きく育ち我々の人間の手によって数珠に加工させて頂いている素材への感謝、
そして今、ここに存在する自分を生んでくれた親への感謝。
自分を取り巻くあたりまえに感じるものでさえ感謝の気持ちを忘れてはなりません。
数珠はお経を唱えた数を数えるためのものでもあるといいましたが、
在家一般の方にとっては、自然に手を合わすための法具でもあります。
ご先祖さまに対して、自分に命を繋いでくれてありがとうというのが本当の合掌なのかもしれません。
合掌は手のひらを合わすと書きます。掌は「たなごころ」ともお読みします。
ひとの心は手の平に宿っているという意味があるからなのです。
葬儀の時や先祖のお墓を前にして、手を合わすというのは心より感謝するということなのです。
そのようにお使いになるお数珠であるからこそ、
あらゆる感謝の気持ちをひとつひとつの珠にこめて数珠をつくっています。
■福永念珠舗HP
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
Posted by 京の社長と数珠紐 at 12:00│Comments(0)
│株式会社福永念珠舗 福永荘三