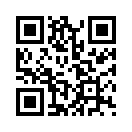2008年05月16日
京都の伝統工芸は奥が深いです。
■第6回 株式会社みす武 大久保武社長 vol.3

――「翠簾(みす)」にも京都の伝統工芸が集まっていますね。
京都で生産されている真竹を業者から仕入れて加工します。
織の部分は西陣織の錦や金らんを使います。
「京の社長数珠つなぎブログ」で紹介された伴戸さんのところとも取引をさせていただいています。
「翠簾」に使用する金らんは柄や紋が大きなものを主に使用します。
房や金具も専門の職人さんがいます。
その専門性が細分化されているのが京都の伝統工芸の奥深いところであり、
良さではないでしょうか。
代々続いている取引先との信用も裏切ってはいけないものです。
取引先との信頼関係もふくめて、京都に残っている伝統は今後も大切に残していきたいですね。

――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を大久保社長が案内する場合、どこに案内しますか?
いいところがたくさんあるのでひとつに絞るのは難しいですね。あえて言うなら京都御苑です。
京都の真ん中にあって、あれだけ広大でゆったりとできるところはないですね。
子どもの頃からよく遊んだ馴染みの場所ということもあるのですが・・・。
京都御所の周りの堀でザリガニを取ったりもしてました(笑)。
――それでは、次ぎに紹介していただく栗栖社長はどんな方ですか?
みんなが「パパ」と呼んでいる、優しくて何でも教えてもらえる素晴らしい先輩です。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年5月1日取材)
■株式会社伴戸商店HP
■京都御苑HP
*********************************
 株式会社みす武
株式会社みす武
京都府京都市中京区衣棚通二条下る
代表取締役 大久保武
電話:(075)231-3822
FAX:(075)231-8029
HP:http://www.misu.co.jp/
■株式会社みす武 大久保武 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――「翠簾(みす)」にも京都の伝統工芸が集まっていますね。
京都で生産されている真竹を業者から仕入れて加工します。
織の部分は西陣織の錦や金らんを使います。
「京の社長数珠つなぎブログ」で紹介された伴戸さんのところとも取引をさせていただいています。
「翠簾」に使用する金らんは柄や紋が大きなものを主に使用します。
房や金具も専門の職人さんがいます。
その専門性が細分化されているのが京都の伝統工芸の奥深いところであり、
良さではないでしょうか。
代々続いている取引先との信用も裏切ってはいけないものです。
取引先との信頼関係もふくめて、京都に残っている伝統は今後も大切に残していきたいですね。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を大久保社長が案内する場合、どこに案内しますか?
いいところがたくさんあるのでひとつに絞るのは難しいですね。あえて言うなら京都御苑です。
京都の真ん中にあって、あれだけ広大でゆったりとできるところはないですね。
子どもの頃からよく遊んだ馴染みの場所ということもあるのですが・・・。
京都御所の周りの堀でザリガニを取ったりもしてました(笑)。
――それでは、次ぎに紹介していただく栗栖社長はどんな方ですか?
みんなが「パパ」と呼んでいる、優しくて何でも教えてもらえる素晴らしい先輩です。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年5月1日取材)
■株式会社伴戸商店HP
■京都御苑HP
*********************************
京都府京都市中京区衣棚通二条下る
代表取締役 大久保武
電話:(075)231-3822
FAX:(075)231-8029
HP:http://www.misu.co.jp/
■株式会社みす武 大久保武 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年05月15日
代々、大久保武右衛門(ぶえもん)を襲名しています。
■第6回 株式会社みす武 大久保武社長 vol.2
――寛保元年の創業ということですが、創業された場所はどちらですか?
 創業は寺町丸太町をさがったところになります。
創業は寺町丸太町をさがったところになります。
下御霊神社の南です。ちょうど竹屋町通のところですね。古くから御所の周りに同業が集まっていました。御所に出入りする為の手形も残っています。あの辺りはかって竹を扱う業者が多かったので竹屋町通りいうのですよ。
創業者から代々、大久保武右衛門(ぶえもん)を襲名しているのですが、
私も仕事上では武右衛門(ぶえもん)を名乗っています。両親は最初、戸籍上の名前も武右衛門と名づけることも考えたのですが、さすがに小さい子が武右衛門ちゃんではかわいそうだというので、「武右衛門」から「武」の一字をとって名づけたそうです。
――先代の社長が早くに亡くなられて、社長は若くして家業を継いだそうですね。
 はい。親父が病に倒れたのは私が24歳のときでした。当時、私は西陣の織屋さんで働いていたのですが、急遽呼び戻されました。それまで親父から直接、「翠簾(みす)」の作り方の指導を受けたことがなく不安もいっぱいでした。
はい。親父が病に倒れたのは私が24歳のときでした。当時、私は西陣の織屋さんで働いていたのですが、急遽呼び戻されました。それまで親父から直接、「翠簾(みす)」の作り方の指導を受けたことがなく不安もいっぱいでした。
小さな頃から「翠簾」を作っているところを近くで見ていたので、母親に教えてもらいながらどうにかなったのですが、細かい部分に関しては入院している親父にきく為にノートを抱えて何度も病院に通いました。
とにかくそれから数年は必死でした。何代も続いている取引先や家族、従業員の皆なに助けられました。
この頃になって「武右衛門」の名前のありがたさを強く感じます。
戸籍上の名前も「武右衛門」に変えようかと考えているところです。
――何代も続く家業を継ぐのはやはり大変なことなんですね。
親父が死んだのは53歳だったので、本当にまだまだこれからというときでした。
私自身、高校を卒業する頃までは家業は継ぎたいという気持ちはあまりありませんでした。
小さい頃は両親だけでなく祖父母も年中休みもなく働いていました。
特に12月は大晦日まで忙しくしていました。
年末は年始の初詣に合わせて神社からの発注がまとめて入ってきました。
元旦に新しい翠簾を揃えて初詣の参拝者を迎えることは各神社にとって重要なことでしたので、
決して納期を遅らせることはできませんでした。
子どもの時分はそういうのが只々、大変だと思っていたのですが、
お正月に新しい竹の香りがする新しい「翠簾(みす)」は、新年に合っていいものです。

■株式会社みす武HP
■株式会社みす武 大久保武 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――寛保元年の創業ということですが、創業された場所はどちらですか?
 創業は寺町丸太町をさがったところになります。
創業は寺町丸太町をさがったところになります。下御霊神社の南です。ちょうど竹屋町通のところですね。古くから御所の周りに同業が集まっていました。御所に出入りする為の手形も残っています。あの辺りはかって竹を扱う業者が多かったので竹屋町通りいうのですよ。
創業者から代々、大久保武右衛門(ぶえもん)を襲名しているのですが、
私も仕事上では武右衛門(ぶえもん)を名乗っています。両親は最初、戸籍上の名前も武右衛門と名づけることも考えたのですが、さすがに小さい子が武右衛門ちゃんではかわいそうだというので、「武右衛門」から「武」の一字をとって名づけたそうです。
――先代の社長が早くに亡くなられて、社長は若くして家業を継いだそうですね。
 はい。親父が病に倒れたのは私が24歳のときでした。当時、私は西陣の織屋さんで働いていたのですが、急遽呼び戻されました。それまで親父から直接、「翠簾(みす)」の作り方の指導を受けたことがなく不安もいっぱいでした。
はい。親父が病に倒れたのは私が24歳のときでした。当時、私は西陣の織屋さんで働いていたのですが、急遽呼び戻されました。それまで親父から直接、「翠簾(みす)」の作り方の指導を受けたことがなく不安もいっぱいでした。小さな頃から「翠簾」を作っているところを近くで見ていたので、母親に教えてもらいながらどうにかなったのですが、細かい部分に関しては入院している親父にきく為にノートを抱えて何度も病院に通いました。
とにかくそれから数年は必死でした。何代も続いている取引先や家族、従業員の皆なに助けられました。
この頃になって「武右衛門」の名前のありがたさを強く感じます。
戸籍上の名前も「武右衛門」に変えようかと考えているところです。
――何代も続く家業を継ぐのはやはり大変なことなんですね。
親父が死んだのは53歳だったので、本当にまだまだこれからというときでした。
私自身、高校を卒業する頃までは家業は継ぎたいという気持ちはあまりありませんでした。
小さい頃は両親だけでなく祖父母も年中休みもなく働いていました。
特に12月は大晦日まで忙しくしていました。
年末は年始の初詣に合わせて神社からの発注がまとめて入ってきました。
元旦に新しい翠簾を揃えて初詣の参拝者を迎えることは各神社にとって重要なことでしたので、
決して納期を遅らせることはできませんでした。
子どもの時分はそういうのが只々、大変だと思っていたのですが、
お正月に新しい竹の香りがする新しい「翠簾(みす)」は、新年に合っていいものです。

■株式会社みす武HP
■株式会社みす武 大久保武 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年05月14日
葵祭の牛車にもつかわれています。
■第6回 株式会社みす武 大久保武社長 vol.1

株式会社負野薫玉堂の負野和夫社長から笑顔の素敵なおっちゃんですと、
紹介いただいたのは株式会社みす武(みすぶ)の大久保武社長です。
株式会社みす武は寛保元年(1741年)創業。
翠簾(みす)屋としては日本でいちばん古い歴史を誇る老舗です。
――翠簾(みす)とはどういうものなのですか?
「翠簾」は「すだれ」のルーツといわれています。
「すだれ」は座敷すだれや軒先に吊るすすだれがあります。
主に夏場に日除けとして使用されることが多いのですが、
「翠簾」の目的は宮中や神社・寺院などで、「結界」として場所を区切ることがいちばんの目的です。
「翠簾」の翠はみどりの意味があり、
それは「翠簾」の材料として青竹の皮を使うところから来ています。
神社や寺院で使用する「翠簾」は青竹の皮を黄色く染めたものを使います。
――みす武さんは日本最古の翠簾屋と言われているんですね。
そうですね。日本一古いというか、現存している中では、ということですね。
京都では現在、弊社も含めて「翠簾」専門店は4軒になります。
京都すだれ組合に加盟しているのは11軒。
かっては20軒以上の加盟があったのですが随分減りました。
――みす武さんの方で受注から生産、納品まで一環してされてるんですか?
伏見稲荷や伊勢神宮など、直接取引をしている神社や寺院は全体の1割もないくらいです。
ほとんどは全国の神具屋さんや仏具屋さんから発注を受ける形になります。
その神具屋さんや仏具屋さんが、神社や寺院からの注文を受けるわけです。
それぞれの神社や寺院はもちろんその大きさや規模が違うので、
「翠簾」の寸法も全て違ってきます。幅が何センチで高さが何センチ、
どういう柄の織をつけて、房の形や房を付ける場所を決めていただくので、
基本的に全てオーダーメイドということになります。
全国の仏具屋さんを通じて一般家庭で使用する「翠簾」の注文もあります。
最近、多いのは仏壇と長押の隙間を隠すためのものですね。
そういう小さいものだと製作にかかるのは4~5日というところでしょうか。
明日(5月15日)開催される葵祭の牛車にもうちの「翠簾」が使われてるんですよ。

■株式会社みす武HP
■伏見稲荷大社HP
■株式会社みす武 大久保武 【1】 >> 【2】 >> 【3】
株式会社負野薫玉堂の負野和夫社長から笑顔の素敵なおっちゃんですと、
紹介いただいたのは株式会社みす武(みすぶ)の大久保武社長です。
株式会社みす武は寛保元年(1741年)創業。
翠簾(みす)屋としては日本でいちばん古い歴史を誇る老舗です。
――翠簾(みす)とはどういうものなのですか?
「翠簾」は「すだれ」のルーツといわれています。
「すだれ」は座敷すだれや軒先に吊るすすだれがあります。
主に夏場に日除けとして使用されることが多いのですが、
「翠簾」の目的は宮中や神社・寺院などで、「結界」として場所を区切ることがいちばんの目的です。
「翠簾」の翠はみどりの意味があり、
それは「翠簾」の材料として青竹の皮を使うところから来ています。
神社や寺院で使用する「翠簾」は青竹の皮を黄色く染めたものを使います。
――みす武さんは日本最古の翠簾屋と言われているんですね。
そうですね。日本一古いというか、現存している中では、ということですね。
京都では現在、弊社も含めて「翠簾」専門店は4軒になります。
京都すだれ組合に加盟しているのは11軒。
かっては20軒以上の加盟があったのですが随分減りました。
――みす武さんの方で受注から生産、納品まで一環してされてるんですか?
伏見稲荷や伊勢神宮など、直接取引をしている神社や寺院は全体の1割もないくらいです。
ほとんどは全国の神具屋さんや仏具屋さんから発注を受ける形になります。
その神具屋さんや仏具屋さんが、神社や寺院からの注文を受けるわけです。
それぞれの神社や寺院はもちろんその大きさや規模が違うので、
「翠簾」の寸法も全て違ってきます。幅が何センチで高さが何センチ、
どういう柄の織をつけて、房の形や房を付ける場所を決めていただくので、
基本的に全てオーダーメイドということになります。
全国の仏具屋さんを通じて一般家庭で使用する「翠簾」の注文もあります。
最近、多いのは仏壇と長押の隙間を隠すためのものですね。
そういう小さいものだと製作にかかるのは4~5日というところでしょうか。
明日(5月15日)開催される葵祭の牛車にもうちの「翠簾」が使われてるんですよ。

■株式会社みす武HP
■伏見稲荷大社HP
■株式会社みす武 大久保武 【1】 >> 【2】 >> 【3】