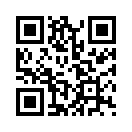2008年11月11日
伝統工芸についてさまざまな発信をすることが大切なのです。
第12回 株式会社福永念珠舗 福永荘三社長 vol.1

株式会社土井志ば漬本舗の土井健資社長から、いつも明るく、
元気のよいバイタリティあふれた社長さんです、
と紹介をいただいた株式会社福永念珠舗の福永荘三社長です。
株式会社福永念珠舗は東本願寺の向側にあり、
数珠(念珠)の製造・販売を行う専門店です。
――東本願寺が正面に見えるのですが、以前より東本願寺の職人だったそうですね。
はい。初代は長浜市新庄馬場町にある誓伝寺の出身です。
誓伝寺の次男である弊社初代は真宗大谷派の本山、
東本願寺でお役にたてればと京都に出てきました。
手先が器用だったのか最初は小間物商として、江戸中期に創業し、
数珠を含めていろいろなものを作っていたのですが、
寛政9年(1797年初代亡)には数珠専門になりました。
当時は自分で商いをするというより、お寺より依頼されたものをつくっていました。
寺の周りには数珠を作る職人の他にも、宮大工や掛軸職人、仏壇・仏具職人など、
専門の分野に分かれた職人が住んでいました。
現在の様子は烏丸通をはさんで弊社の社屋が建っているので、
門前町のように思われがちですが、江戸時代の東本願寺領地はずっと広く、
現在の場所も敷地のなかでした。
この辺りを「寺内町」とよんだ江戸時代の資料も残っています。
――一般的には数珠と呼ぶのだと思うのですが、御社は福永「念珠」舗なんですね。
数珠は元来、仏教の行に使う法具でした。
たとえば、お経を唱えた回数を数えることに使われていました。
仏教の起源はインドからシルクロードを経て中国にはいってきた仏教はさらに日本をはじめ、
朝鮮半島や台湾、沖縄に同じ頃に伝わりました。
日本に伝来してきたときに、現在の各宗派が経典を日本語に訳すのですが、
それぞれその解釈と伝え方が違っていました。
その違いは信仰や行の方法にもあらわれ、
数珠はその宗派に合った形に平安・鎌倉時代のころに変化していきました。
数珠の主玉(おもだま)108個を数えたら、そのことを記録するために小さな珠(たま)をつけたり、
行にあわせてある宗派では房の形を独特のものにしたり、
108個の数は基本的には変えずに各宗派が使いやすように法具として、
より機能的に進化していったのです。
浄土真宗各派では数を数える数珠ではなく、念珠とよぶようになりました。
――今は宗派に関わらず、各宗派の数珠を製造をしているんですね?
はい。今は各宗派の数珠を制作しています。
いまでも日本で使われている数珠の90%以上が京都で作られているようです。
なぜ京都が数珠の伝統継承される本場なのかわかりますか?
もちろん本山がたくさんあって、必要とされてきたということもあるのですが、
なにより技を持つ職人が居て、さらに数珠を作ることに必要な房や糸などの材料が
京都の伝統産業に揃っていました。
西陣織に使う織り機は、はたを織る過程で、最後に1メートルほど糸が余ってしまいます。
はし糸といって、もう織りには使えないそうです、
そのあまり糸をいただき染め直して数珠の組紐や房の制作に使っていました。
染色についても京都には伝統があるので、糸を必要とする色に染めあげることができました。
現代のように交通網が発達しているわけではないので、
近所で材料が全て揃うということはひとつの産業が育つ上で非常に重要なことだと思います。
お数珠を制作するのも、現在ではいくつもの工程に伝統工芸の技が携わっています。
たくさんの行程の中でひとつでも欠けたら伝統工芸ではなくなります。
海外に制作をゆだねるのではなく、我々が伝統を継承していく人間を育てないといけないのです。
こんな時代なので、大量生産で少しでも安いものを作ることも可能ですが、
そればかりに眼を向けてしまえば伝統工芸品と呼べるものはなくなってしまいます。
良いものが欲しい、本物が欲しい、あの人が作ったものが欲しいと思ってもらえるように、
伝統工芸についてさまざまな発信をすることが大切になってくるのです。
人間の魅力と伝統の魅力がいきているから日本はものだけでなく心も豊かなのだと思います。
■福永念珠舗HP
■東本願寺HP
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
株式会社土井志ば漬本舗の土井健資社長から、いつも明るく、
元気のよいバイタリティあふれた社長さんです、
と紹介をいただいた株式会社福永念珠舗の福永荘三社長です。
株式会社福永念珠舗は東本願寺の向側にあり、
数珠(念珠)の製造・販売を行う専門店です。
――東本願寺が正面に見えるのですが、以前より東本願寺の職人だったそうですね。
はい。初代は長浜市新庄馬場町にある誓伝寺の出身です。
誓伝寺の次男である弊社初代は真宗大谷派の本山、
東本願寺でお役にたてればと京都に出てきました。
手先が器用だったのか最初は小間物商として、江戸中期に創業し、
数珠を含めていろいろなものを作っていたのですが、
寛政9年(1797年初代亡)には数珠専門になりました。
当時は自分で商いをするというより、お寺より依頼されたものをつくっていました。
寺の周りには数珠を作る職人の他にも、宮大工や掛軸職人、仏壇・仏具職人など、
専門の分野に分かれた職人が住んでいました。
現在の様子は烏丸通をはさんで弊社の社屋が建っているので、
門前町のように思われがちですが、江戸時代の東本願寺領地はずっと広く、
現在の場所も敷地のなかでした。
この辺りを「寺内町」とよんだ江戸時代の資料も残っています。
――一般的には数珠と呼ぶのだと思うのですが、御社は福永「念珠」舗なんですね。
数珠は元来、仏教の行に使う法具でした。
たとえば、お経を唱えた回数を数えることに使われていました。
仏教の起源はインドからシルクロードを経て中国にはいってきた仏教はさらに日本をはじめ、
朝鮮半島や台湾、沖縄に同じ頃に伝わりました。
日本に伝来してきたときに、現在の各宗派が経典を日本語に訳すのですが、
それぞれその解釈と伝え方が違っていました。
その違いは信仰や行の方法にもあらわれ、
数珠はその宗派に合った形に平安・鎌倉時代のころに変化していきました。
数珠の主玉(おもだま)108個を数えたら、そのことを記録するために小さな珠(たま)をつけたり、
行にあわせてある宗派では房の形を独特のものにしたり、
108個の数は基本的には変えずに各宗派が使いやすように法具として、
より機能的に進化していったのです。
浄土真宗各派では数を数える数珠ではなく、念珠とよぶようになりました。
――今は宗派に関わらず、各宗派の数珠を製造をしているんですね?
はい。今は各宗派の数珠を制作しています。
いまでも日本で使われている数珠の90%以上が京都で作られているようです。
なぜ京都が数珠の伝統継承される本場なのかわかりますか?
もちろん本山がたくさんあって、必要とされてきたということもあるのですが、
なにより技を持つ職人が居て、さらに数珠を作ることに必要な房や糸などの材料が
京都の伝統産業に揃っていました。
西陣織に使う織り機は、はたを織る過程で、最後に1メートルほど糸が余ってしまいます。
はし糸といって、もう織りには使えないそうです、
そのあまり糸をいただき染め直して数珠の組紐や房の制作に使っていました。
染色についても京都には伝統があるので、糸を必要とする色に染めあげることができました。
現代のように交通網が発達しているわけではないので、
近所で材料が全て揃うということはひとつの産業が育つ上で非常に重要なことだと思います。
お数珠を制作するのも、現在ではいくつもの工程に伝統工芸の技が携わっています。
たくさんの行程の中でひとつでも欠けたら伝統工芸ではなくなります。
海外に制作をゆだねるのではなく、我々が伝統を継承していく人間を育てないといけないのです。
こんな時代なので、大量生産で少しでも安いものを作ることも可能ですが、
そればかりに眼を向けてしまえば伝統工芸品と呼べるものはなくなってしまいます。
良いものが欲しい、本物が欲しい、あの人が作ったものが欲しいと思ってもらえるように、
伝統工芸についてさまざまな発信をすることが大切になってくるのです。
人間の魅力と伝統の魅力がいきているから日本はものだけでなく心も豊かなのだと思います。
■福永念珠舗HP
■東本願寺HP
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】