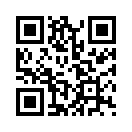2008年12月11日
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案しています。
第13回 株式会社三才 専務取締役 斉藤上太郎 vol.1

株式会社福永念珠舗の福永荘三社長から、古き良きものを知り大切にしながら、なによりも豊かな感性で新しい着物を作り上げている着物デザイナーです、と紹介をいただいた株式会社三才の斉藤上太郎専務取締役です。株式会社三才は鴨川の出雲路橋の近く、閑静な住宅街にあり、「斉藤三才」「斉藤上太郎」の二大ブランドを主体としたキモノ・和装品のトータルな製造・企画を行っている会社です。
――株式会社三才は斉藤専務の祖父が創業されたそうですね。
はい。私の祖父、先代の三才が染色加工業として昭和8年に創業しました。
着物を染めるいわゆる染屋ですね。戦時中は休業している時期もあったのですが、
戦後の昭和24年に再開して、現在は私の父が三才の名前を継いで、社長に就任しています。
基本的に着物は着物屋さんや染屋さんが作って、
帯は帯屋さんが作ってという風に完全な分業制のため、
着物と帯の組み合わせをトータルで考えてデザインをすることはありませんでした。
結果的になんでもあわせやすい着物や帯が多くなり、同じような柄の着物や帯ばかりでした。
そういったなかで父の三才が着物のデザインをはじめました。
ものづくりの世界では着物に限らずデザインをする作家と、
ものをつくる職人はわかれているのですが、
父は着物をワンピース、帯をベルトとして考え、
こういう柄のワンピースに合うのはこういうベルトという感じで同じ柄でデザインするなど、
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案したはじめての作家でした。
たとえば日本人は小柄で背が低いので、帯で着物を上下にわけるより、
着物と同系や同色、同柄のデザインで一体化させ
すきっとしたスタイルをみせた方がよりおしゃれな着姿になります。
父や弊社の工場はそういう提案をするのが同業の中でも早く、
僕もそういう形でデザインをしています。
――斉藤専務は27歳の若さで作家としてデビューされたのですね。
そうですね。京都造形芸術大学の前身の京都芸短を20歳で卒業して、すぐに三才に入社しました。
でも最初は親父に洋服をやらせてくれ頼み、着物ではなくアパレルをやっていました。
当時はまだバブルの頃で会社にも余裕があったのだと思います。
「やれるものならやってみいや」と言われまして、
アパレルのブランドを立ち上げて、デザインから取引先の開拓まで全部自分でやりました。
最初は高級ブティックに飛び込みで営業もしました。
ほかにも洋服の素材として絹以外の様々なコットンやレーヨン、ポリを触ったのは
よい経験になりました。組成も理解できるようになりました。
着物は工芸品という側面もあるのですが、洋服というのはやはり工業製品であって、
例えば洗濯に耐えられる強度があるのか、というところから着物とは違う問題があるのです。
そういうことも含めて独学でトライしたことは、すごいプラスになっています。
まあ、たいした儲けもあがらなかったのですが、
大きなメーカーさんとも付き合いができたし、自信になりました。
結局、7年ほどアパレルの方で頑張っていたのですが、
27歳のときにそろそろ着物をせえへんかと言われたんですね。
当時、27歳といえばまだまだ作家の前例がない年齢で、
今でこそ30歳前後の作家がいるのですが、10年前といえば、
私の上は40代のなかばくらいの方でした。
着物作家としてデビューするときに、着物業界のさる御方に
「着物と洋服の二束の草鞋を履くことはあいならん」と言われました。
そのときアパレルの方は、次ぎの展開を考えると、直営店を出店したり、
人を増やしたり、本気で続けるのであれば、かなり費用もかかることだったので、
その方に後押しをして頂いたのは渡りに船だと思い完全に着物に切り替えることにしました。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社福永念珠舗の福永荘三社長から、古き良きものを知り大切にしながら、なによりも豊かな感性で新しい着物を作り上げている着物デザイナーです、と紹介をいただいた株式会社三才の斉藤上太郎専務取締役です。株式会社三才は鴨川の出雲路橋の近く、閑静な住宅街にあり、「斉藤三才」「斉藤上太郎」の二大ブランドを主体としたキモノ・和装品のトータルな製造・企画を行っている会社です。
――株式会社三才は斉藤専務の祖父が創業されたそうですね。
はい。私の祖父、先代の三才が染色加工業として昭和8年に創業しました。
着物を染めるいわゆる染屋ですね。戦時中は休業している時期もあったのですが、
戦後の昭和24年に再開して、現在は私の父が三才の名前を継いで、社長に就任しています。
基本的に着物は着物屋さんや染屋さんが作って、
帯は帯屋さんが作ってという風に完全な分業制のため、
着物と帯の組み合わせをトータルで考えてデザインをすることはありませんでした。
結果的になんでもあわせやすい着物や帯が多くなり、同じような柄の着物や帯ばかりでした。
そういったなかで父の三才が着物のデザインをはじめました。
ものづくりの世界では着物に限らずデザインをする作家と、
ものをつくる職人はわかれているのですが、
父は着物をワンピース、帯をベルトとして考え、
こういう柄のワンピースに合うのはこういうベルトという感じで同じ柄でデザインするなど、
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案したはじめての作家でした。
たとえば日本人は小柄で背が低いので、帯で着物を上下にわけるより、
着物と同系や同色、同柄のデザインで一体化させ
すきっとしたスタイルをみせた方がよりおしゃれな着姿になります。
父や弊社の工場はそういう提案をするのが同業の中でも早く、
僕もそういう形でデザインをしています。
――斉藤専務は27歳の若さで作家としてデビューされたのですね。
そうですね。京都造形芸術大学の前身の京都芸短を20歳で卒業して、すぐに三才に入社しました。
でも最初は親父に洋服をやらせてくれ頼み、着物ではなくアパレルをやっていました。
当時はまだバブルの頃で会社にも余裕があったのだと思います。
「やれるものならやってみいや」と言われまして、
アパレルのブランドを立ち上げて、デザインから取引先の開拓まで全部自分でやりました。
最初は高級ブティックに飛び込みで営業もしました。
ほかにも洋服の素材として絹以外の様々なコットンやレーヨン、ポリを触ったのは
よい経験になりました。組成も理解できるようになりました。
着物は工芸品という側面もあるのですが、洋服というのはやはり工業製品であって、
例えば洗濯に耐えられる強度があるのか、というところから着物とは違う問題があるのです。
そういうことも含めて独学でトライしたことは、すごいプラスになっています。
まあ、たいした儲けもあがらなかったのですが、
大きなメーカーさんとも付き合いができたし、自信になりました。
結局、7年ほどアパレルの方で頑張っていたのですが、
27歳のときにそろそろ着物をせえへんかと言われたんですね。
当時、27歳といえばまだまだ作家の前例がない年齢で、
今でこそ30歳前後の作家がいるのですが、10年前といえば、
私の上は40代のなかばくらいの方でした。
着物作家としてデビューするときに、着物業界のさる御方に
「着物と洋服の二束の草鞋を履くことはあいならん」と言われました。
そのときアパレルの方は、次ぎの展開を考えると、直営店を出店したり、
人を増やしたり、本気で続けるのであれば、かなり費用もかかることだったので、
その方に後押しをして頂いたのは渡りに船だと思い完全に着物に切り替えることにしました。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
Posted by 京の社長と数珠紐 at 12:00│Comments(0)
│株式会社三才 斉藤上太郎