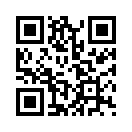2009年01月21日
素材や染色作家さんをコーディネート、プロデュースします。
第14回 京朋株式会社 代表取締役 室木英人 vol.1

株式会社三才の斉藤専務から、着物の加工元卸業の最大手の会社に紆余曲折を経て
社長に就任された27歳の若き社長です、と紹介をいただいた京朋の室木社長です。
京朋株式会社は振袖では着物業界でもトップのシェアを誇り、
昨今は特に若い世代(20代後半~30代)の女性をターゲットにした
商品開発に力を注いでいます。
――創業は昭和30年ということですが、呉服、着物メーカーとしては比較的新しい会社なのですね。
はい。私の祖父であり、現相談役の大江茂が1955年に起こした会社です。
100年以上の歴史がある老舗が多い着物業界では、創業53年の歴史は新しい会社といえます。
創業当時、呉服は給料の何倍もするようなたいへん高価な商品でした。
祖父はもっとたくさんの女性に着物を着てもらいたいとの思いから、
大衆商品化を目指し、商品開発に全力を注いだ結果、
付下という大ヒット商品を世に送りだすことができました。
戦後の高度成長期とも重なり、ちょうど団塊の世代が成人し、
結婚する1970年前後にピークを迎えました。
当時は嫁入りのときに和ダンス一式といわれていた時代で、
その流れにもうまく乗って会社は急成長を遂げました。
その後も着物業界でキャラクターブランド商品の先駆けとなった「秋山庄太郎のきもの」などを
次々と発表し、業界に一大センセーションを巻き起こすなど、
祖父は積極的に事業展開を行いました。
――前回の株式会社三才の斉藤専務は着物デザイナーということでしたが、京朋は着物メーカーになるのですね?
はい。弊社は製造卸しの会社です。
メーカーとはいいますが、弊社が工場を持っているわけではありません。
着物を作るためにはまず、丹後地方や長浜の方で織られた白生地を扱う問屋さんから
生地を買い付けます。
着物は、紬などの先に糸を染めているものもありますが、
うちの場合は真っ白な状態の生地を買ってきます。
市内の染色工場で柄などを指示して染めてもらいます。
そうして染められた生地が加工されて製品になります。素材や染工場、染色作家さんには、
それぞれ特色があるので、そのカラーをうまく組み合わせて、どう引き出すかが我々の役目です。
要はコーディネーター、プロデュースする立場ですね。
製品は問屋を通して、小売店に並び、消費者の手に届くようになります。
現在は着物の流通も過渡期で流通形態が徐々に変化してきています。
着物のデザインについても、これまでは作家とよばれる着物デザイナーは社外に居たのですが、
弊社では社内にデザイン部署を作り、社内デザイナーによる商品の開発にも取り組んでいます。
2008年10月には四条河原町近くに「コエトイロ -coetoiro-」という
アンテナショップも出店しました。
■京朋株式会社HP
■「コエトイロ -coetoiro-」HP
■京朋株式会社 室木英人 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社三才の斉藤専務から、着物の加工元卸業の最大手の会社に紆余曲折を経て
社長に就任された27歳の若き社長です、と紹介をいただいた京朋の室木社長です。
京朋株式会社は振袖では着物業界でもトップのシェアを誇り、
昨今は特に若い世代(20代後半~30代)の女性をターゲットにした
商品開発に力を注いでいます。
――創業は昭和30年ということですが、呉服、着物メーカーとしては比較的新しい会社なのですね。
はい。私の祖父であり、現相談役の大江茂が1955年に起こした会社です。
100年以上の歴史がある老舗が多い着物業界では、創業53年の歴史は新しい会社といえます。
創業当時、呉服は給料の何倍もするようなたいへん高価な商品でした。
祖父はもっとたくさんの女性に着物を着てもらいたいとの思いから、
大衆商品化を目指し、商品開発に全力を注いだ結果、
付下という大ヒット商品を世に送りだすことができました。
戦後の高度成長期とも重なり、ちょうど団塊の世代が成人し、
結婚する1970年前後にピークを迎えました。
当時は嫁入りのときに和ダンス一式といわれていた時代で、
その流れにもうまく乗って会社は急成長を遂げました。
その後も着物業界でキャラクターブランド商品の先駆けとなった「秋山庄太郎のきもの」などを
次々と発表し、業界に一大センセーションを巻き起こすなど、
祖父は積極的に事業展開を行いました。
――前回の株式会社三才の斉藤専務は着物デザイナーということでしたが、京朋は着物メーカーになるのですね?
はい。弊社は製造卸しの会社です。
メーカーとはいいますが、弊社が工場を持っているわけではありません。
着物を作るためにはまず、丹後地方や長浜の方で織られた白生地を扱う問屋さんから
生地を買い付けます。
着物は、紬などの先に糸を染めているものもありますが、
うちの場合は真っ白な状態の生地を買ってきます。
市内の染色工場で柄などを指示して染めてもらいます。
そうして染められた生地が加工されて製品になります。素材や染工場、染色作家さんには、
それぞれ特色があるので、そのカラーをうまく組み合わせて、どう引き出すかが我々の役目です。
要はコーディネーター、プロデュースする立場ですね。
製品は問屋を通して、小売店に並び、消費者の手に届くようになります。
現在は着物の流通も過渡期で流通形態が徐々に変化してきています。
着物のデザインについても、これまでは作家とよばれる着物デザイナーは社外に居たのですが、
弊社では社内にデザイン部署を作り、社内デザイナーによる商品の開発にも取り組んでいます。
2008年10月には四条河原町近くに「コエトイロ -coetoiro-」という
アンテナショップも出店しました。
■京朋株式会社HP
■「コエトイロ -coetoiro-」HP
■京朋株式会社 室木英人 【1】 >> 【2】 >> 【3】
Posted by 京の社長と数珠紐 at 12:00│Comments(0)
│京朋株式会社 室木英人