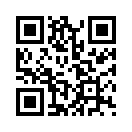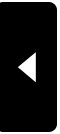2009年06月03日
風呂敷をもっと生活の中で使ってもらいたいですね。
第18回 株式会社マルタカ 代表取締役 林 利治 vol.1

株式会社井助商店の沖野社長から、「温厚な方でみんなの意見をちゃんと聞いてひとつのものを作り上げていくところがあって、たいへん信頼できます」と紹介をいただいたマルタカの林社長です。マルタカは風呂敷の製造・卸・販売を主に手がけ、早くからネット販売にも積極的に取り組んでいます。また林社長は異業種交流会Kyoohoo!?(キョフー)の会長も務めています。
――林社長はマルタカの他に、丸和商業株式会社の代表も務められているのですね?
はい。元は丸和商業が母体なのです。
丸和商業は風呂敷の製造・卸の会社なのですが、
販売ルートを新しく開拓するために立ち上げたのがマルタカです。
販売先を変えて、ふたつの会社の役割を分担しています。
丸和商業の創業は戦後の昭和24年。
先代の社長が亡くなったあと、当時、丸和商業に勤めていた私の父が会社を継ぐ形になりました。
――ずっと風呂敷をメインでやっているのですか?
マルタカに私が入社した頃は風呂敷以外にタオルや寝装品などギフト商品を多く扱っていました。
ギフトの分野と風呂敷でちょうど50%ずつくらいだったと思います。
でもうちはやっぱり風呂敷屋なので、自社の強い分野でたたかうべきだということで、
風呂敷に重点を置くようになりました。
ちょうど中国から安いタオルが入ってくるようになって、
値段ではとても適わなくなったというのもあります。
風呂敷中心に業態をシフトしていく上で、
当然、風呂敷ではどこへ行っても負けないという気概もあります。
――以前、風呂敷が日用品だった時代があったと聞いたことがあるのですが?
そうですね。なんでも風呂敷で包んでいた時代がありました。
残念なことなのですが、そうした戦前戦後の頃の日用品としての風呂敷は
もうなくなってしまったではないかと思います。
最近でこそ、いろいろな和物屋さんとかで風呂敷をみかけるようになりましたが、
一時はいったいどこで売っているの?というような感じでした。
ただ現在もお店に並んでいるのを見かけても、
町なかで風呂敷を使っている人は殆ど見ることがありません。
和の文化が見直されていることもあって、
最近は様々な方が風呂敷包み方考えて発表されています。
それに加えて、どういうシーンで風呂敷を使うことができるのか?
風呂敷で何かできないかと私たちも常に考えています。
たとえば結納のときに風呂敷を使うシーンはイメージできるのですが、
他のシーンでも、もっともっと使うイメージが出来なければなりません。
やっぱり風呂敷をもっと生活の中で使ってもらいたいですね。
■株式会社マルタカHP 「京都・いーふろしきや」
■丸和商業株式会社HP
■株式会社マルタカ 林利治 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社井助商店の沖野社長から、「温厚な方でみんなの意見をちゃんと聞いてひとつのものを作り上げていくところがあって、たいへん信頼できます」と紹介をいただいたマルタカの林社長です。マルタカは風呂敷の製造・卸・販売を主に手がけ、早くからネット販売にも積極的に取り組んでいます。また林社長は異業種交流会Kyoohoo!?(キョフー)の会長も務めています。
――林社長はマルタカの他に、丸和商業株式会社の代表も務められているのですね?
はい。元は丸和商業が母体なのです。
丸和商業は風呂敷の製造・卸の会社なのですが、
販売ルートを新しく開拓するために立ち上げたのがマルタカです。
販売先を変えて、ふたつの会社の役割を分担しています。
丸和商業の創業は戦後の昭和24年。
先代の社長が亡くなったあと、当時、丸和商業に勤めていた私の父が会社を継ぐ形になりました。
――ずっと風呂敷をメインでやっているのですか?
マルタカに私が入社した頃は風呂敷以外にタオルや寝装品などギフト商品を多く扱っていました。
ギフトの分野と風呂敷でちょうど50%ずつくらいだったと思います。
でもうちはやっぱり風呂敷屋なので、自社の強い分野でたたかうべきだということで、
風呂敷に重点を置くようになりました。
ちょうど中国から安いタオルが入ってくるようになって、
値段ではとても適わなくなったというのもあります。
風呂敷中心に業態をシフトしていく上で、
当然、風呂敷ではどこへ行っても負けないという気概もあります。
――以前、風呂敷が日用品だった時代があったと聞いたことがあるのですが?
そうですね。なんでも風呂敷で包んでいた時代がありました。
残念なことなのですが、そうした戦前戦後の頃の日用品としての風呂敷は
もうなくなってしまったではないかと思います。
最近でこそ、いろいろな和物屋さんとかで風呂敷をみかけるようになりましたが、
一時はいったいどこで売っているの?というような感じでした。
ただ現在もお店に並んでいるのを見かけても、
町なかで風呂敷を使っている人は殆ど見ることがありません。
和の文化が見直されていることもあって、
最近は様々な方が風呂敷包み方考えて発表されています。
それに加えて、どういうシーンで風呂敷を使うことができるのか?
風呂敷で何かできないかと私たちも常に考えています。
たとえば結納のときに風呂敷を使うシーンはイメージできるのですが、
他のシーンでも、もっともっと使うイメージが出来なければなりません。
やっぱり風呂敷をもっと生活の中で使ってもらいたいですね。
■株式会社マルタカHP 「京都・いーふろしきや」
■丸和商業株式会社HP
■株式会社マルタカ 林利治 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年05月14日
歩くことで京都をより感じていただきたいですね。
第17回 株式会社井助商店 代表取締役 沖野俊之 vol.3

――沖野社長の経歴について教えてください。
私は京都の出身ではなく神戸で生まれ育ちました。
京都大学時代に井助商店の現在の会長の長女と知り合って付き合うようになりました。
就職は神戸に戻って住友金属さんに入社して、その時代に結婚しました。
妻には妹しか居なかったこともあって、私が30歳のときに、
井助商店を継がないかという話しがありました。
ゆくゆくはそういう話もあるのかな、程度には考えていたのですが、
その当時の私にとっては思いがけず急な話だったので、
1年位考えたのですが、会社を経営するということにも興味があったので、
31歳のときに井助商店に入社しました。
――老舗を継ぐというのはたいへんだったのでは?
はじめはやっぱり不安の方が大きかったですね。
入社当初、これまでの仕事とはまったく違う営業に対する不安もありました。
大学時代の友人はほとんどがサラリーマンをしていたので、
経営の立場で何かあったときに相談するひとが周りに居ませんでした。
また京都特有のことだと感じるのですが、やはり横の繋がりというのが強くて、
最初は入りづらいというか、入れるのかなという心配がありました。
それでも段々と堀社長のような同年代の方と知り合うようになって、
今ではとても居心地がよくなりました。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を沖野社長が案内する場合、どこに案内しますか?
月並みですが、この前、久しぶりに金閣寺へ行ったのですが、やっぱりいいですよね。
金閣寺を含めた景色がすごくて圧倒されました。
あと私は桂の方に住んでいるので、嵐山の方もおすすめです。
せっかくなのでぜひ嵐山の奥の方まで散策して欲しいですね。
ずっと歩いて行くと竹やぶがあって、段々とひとの少ない鄙びた静かなところになり、
たいへん風情があります。
他にも清水寺から高台寺や祇園の方へ歩くのもいいですね。
四条通も烏丸から河原町にかけても少し北にあがると
最近できた新しい店が多くておもしろいですよね。
京都では観光名所を車で移動して慌しく廻るよりも、
ちょっと時間をかけてその周辺を歩くのが楽しいと思います。
歩くことで京都をより感じていただきたいですね。
――それでは、次ぎに紹介していただく林社長はどんな方ですか?
温厚で押し付けがましくない方です。Kyoohoo!?(キョフー)の会長をやっておられるのですが、
会員みんなの意見をちゃんと聞いてひとつのものを作り上げていくところがあって、
たいへん信頼できます。
私より少し年上なので、兄貴的なところもあり、
ネット通販にも積極的になので、よく情報交換をしています。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2009年4月3日取材)
*********************************
 株式会社井助商店
株式会社井助商店
京都市下京区柳馬場通五条上る柏屋町344
代表取締役 沖野俊之
電話:(075)361-5281
FAX:(075)361-5285
HP:http://www.isuke.co.jp/
■株式会社井助商店 沖野俊之 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――沖野社長の経歴について教えてください。
私は京都の出身ではなく神戸で生まれ育ちました。
京都大学時代に井助商店の現在の会長の長女と知り合って付き合うようになりました。
就職は神戸に戻って住友金属さんに入社して、その時代に結婚しました。
妻には妹しか居なかったこともあって、私が30歳のときに、
井助商店を継がないかという話しがありました。
ゆくゆくはそういう話もあるのかな、程度には考えていたのですが、
その当時の私にとっては思いがけず急な話だったので、
1年位考えたのですが、会社を経営するということにも興味があったので、
31歳のときに井助商店に入社しました。
――老舗を継ぐというのはたいへんだったのでは?
はじめはやっぱり不安の方が大きかったですね。
入社当初、これまでの仕事とはまったく違う営業に対する不安もありました。
大学時代の友人はほとんどがサラリーマンをしていたので、
経営の立場で何かあったときに相談するひとが周りに居ませんでした。
また京都特有のことだと感じるのですが、やはり横の繋がりというのが強くて、
最初は入りづらいというか、入れるのかなという心配がありました。
それでも段々と堀社長のような同年代の方と知り合うようになって、
今ではとても居心地がよくなりました。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を沖野社長が案内する場合、どこに案内しますか?
月並みですが、この前、久しぶりに金閣寺へ行ったのですが、やっぱりいいですよね。
金閣寺を含めた景色がすごくて圧倒されました。
あと私は桂の方に住んでいるので、嵐山の方もおすすめです。
せっかくなのでぜひ嵐山の奥の方まで散策して欲しいですね。
ずっと歩いて行くと竹やぶがあって、段々とひとの少ない鄙びた静かなところになり、
たいへん風情があります。
他にも清水寺から高台寺や祇園の方へ歩くのもいいですね。
四条通も烏丸から河原町にかけても少し北にあがると
最近できた新しい店が多くておもしろいですよね。
京都では観光名所を車で移動して慌しく廻るよりも、
ちょっと時間をかけてその周辺を歩くのが楽しいと思います。
歩くことで京都をより感じていただきたいですね。
――それでは、次ぎに紹介していただく林社長はどんな方ですか?
温厚で押し付けがましくない方です。Kyoohoo!?(キョフー)の会長をやっておられるのですが、
会員みんなの意見をちゃんと聞いてひとつのものを作り上げていくところがあって、
たいへん信頼できます。
私より少し年上なので、兄貴的なところもあり、
ネット通販にも積極的になので、よく情報交換をしています。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2009年4月3日取材)
*********************************
京都市下京区柳馬場通五条上る柏屋町344
代表取締役 沖野俊之
電話:(075)361-5281
FAX:(075)361-5285
HP:http://www.isuke.co.jp/
■株式会社井助商店 沖野俊之 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年05月13日
「漆黒」とは、独特の艶やかで濃い漆の黒
第17回 株式会社井助商店 代表取締役 沖野俊之 vol.2

――最近は海外のギフトショーにも参加されているそうですね。
はい。(財)京都産業21が主催する、
京都の中小企業が集まったKyoohoo!?(キョフー)という異業種交流会があるのですが、
そこの取り組みの1つとして、工芸関連の会社で
毎年ニューヨークの国際ギフトショーに出展しています。
あまり知られてはいないのですが、実は漆器のことを英語でジャパン(japan)と言います。
実際にはジャパニーズ・ラッカー・ウェアと説明することの方が多いのですが、
それだけ漆は日本に特有のものなのです。
ニューヨークのメトロポリタン美術館へ行くと
日本のコーナーには鎧甲や着物と並んで漆器が多く展示されていました。
木工製品に漆のようなものを塗る文化は欧米にはありません。
中国や東南アジアにあるくらいではないでしょうか。
 今年のニューヨーク国際ギフトショーにあわせてKyoohoo!?(キョフー)と京都造形大のコラボレーションとしてサクラ柄の小箱や手鏡を製作しました。
今年のニューヨーク国際ギフトショーにあわせてKyoohoo!?(キョフー)と京都造形大のコラボレーションとしてサクラ柄の小箱や手鏡を製作しました。
学生さんにはニューヨークで出展するというのとは関係なく、本当に自分らが欲しいものをというコンセプトでデザインを依頼しました。パステル調のかわいい製品ができあがり非常に満足しています。但し、その製品は塗りに漆を使ったものではなく、化学塗料を使っています。
ニューヨークでも売れるものを、と考えているので流通コストも含めて考えると
漆を使うとどうしても高価になり過ぎてしまいます。
今回の企画に関しては最初から化学塗料を使うことを前提にしていました。
また漆でパステル調の色合いを出すことはできません。
漆は黒以外は顔料を混ぜて着色するのですが、
元々無色透明ではないので、淡い色合いは出ないのです。
漆の黒だけは、漆に鉄分を混ぜて「漆黒」と呼ばれる独特の艶やかで濃い黒を出すのです。
――京都の活性化について考えておられることはありますか?
ニューヨークへ行って感じたのですが、
私たちが考えているほどは京都は海外の方に知られていないのではと感じることがありました。
例えば、私もイギリスだとロンドン以外のことはよく知らないですし、
アメリカでも知っている都市の数は限られています。
もっと京都は海外に向けていろいろな情報を発信していくべきだと思います。
今でも海外からたくさんの方が観光に訪れていますが、
京都の持つ魅力の潜在能力を考えると、
もっと海外からの観光客を増やすことができるのではないでしょうか。
京都=日本と言うとおこがましいかも知れませんが、
京都が日本を代表する気持ちで海外に対してもっとアピールする必要はあると思います。
――井助商店の経営理念はどのようなものなのですか?
 誠心誠意という言葉を大切にしています。
誠心誠意という言葉を大切にしています。
常に誰に対しても同じように誠意を持って対応するということですね。仕入れさんであっても、大きいお客さんも小さいお客さんも、また社員に対しても、きちんと気持ちを持って分け隔てなく接しないといけないと考えています。
当社は創業180年を超えて地方へ行くとすごい老舗のように言われますが、前回の堀金箔粉さんはまもなく創業300年ですし、京都では特に珍しいものではありません。
ただ100年200年と事業を続けるのは本当にたいへんなことです。
ITバブルの時期を経てみると余計に感じます。
流行に乗ることは大切なのですが、それだけではいけません。
長く続いているところでも、事件や事故があると会社を続けることができなくなってしまいます。
■株式会社井助商店HP
■財団法人 京都産業21HP
■京都造形芸術大学HP
■株式会社井助商店 沖野俊之 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――最近は海外のギフトショーにも参加されているそうですね。
はい。(財)京都産業21が主催する、
京都の中小企業が集まったKyoohoo!?(キョフー)という異業種交流会があるのですが、
そこの取り組みの1つとして、工芸関連の会社で
毎年ニューヨークの国際ギフトショーに出展しています。
あまり知られてはいないのですが、実は漆器のことを英語でジャパン(japan)と言います。
実際にはジャパニーズ・ラッカー・ウェアと説明することの方が多いのですが、
それだけ漆は日本に特有のものなのです。
ニューヨークのメトロポリタン美術館へ行くと
日本のコーナーには鎧甲や着物と並んで漆器が多く展示されていました。
木工製品に漆のようなものを塗る文化は欧米にはありません。
中国や東南アジアにあるくらいではないでしょうか。
 今年のニューヨーク国際ギフトショーにあわせてKyoohoo!?(キョフー)と京都造形大のコラボレーションとしてサクラ柄の小箱や手鏡を製作しました。
今年のニューヨーク国際ギフトショーにあわせてKyoohoo!?(キョフー)と京都造形大のコラボレーションとしてサクラ柄の小箱や手鏡を製作しました。学生さんにはニューヨークで出展するというのとは関係なく、本当に自分らが欲しいものをというコンセプトでデザインを依頼しました。パステル調のかわいい製品ができあがり非常に満足しています。但し、その製品は塗りに漆を使ったものではなく、化学塗料を使っています。
ニューヨークでも売れるものを、と考えているので流通コストも含めて考えると
漆を使うとどうしても高価になり過ぎてしまいます。
今回の企画に関しては最初から化学塗料を使うことを前提にしていました。
また漆でパステル調の色合いを出すことはできません。
漆は黒以外は顔料を混ぜて着色するのですが、
元々無色透明ではないので、淡い色合いは出ないのです。
漆の黒だけは、漆に鉄分を混ぜて「漆黒」と呼ばれる独特の艶やかで濃い黒を出すのです。
――京都の活性化について考えておられることはありますか?
ニューヨークへ行って感じたのですが、
私たちが考えているほどは京都は海外の方に知られていないのではと感じることがありました。
例えば、私もイギリスだとロンドン以外のことはよく知らないですし、
アメリカでも知っている都市の数は限られています。
もっと京都は海外に向けていろいろな情報を発信していくべきだと思います。
今でも海外からたくさんの方が観光に訪れていますが、
京都の持つ魅力の潜在能力を考えると、
もっと海外からの観光客を増やすことができるのではないでしょうか。
京都=日本と言うとおこがましいかも知れませんが、
京都が日本を代表する気持ちで海外に対してもっとアピールする必要はあると思います。
――井助商店の経営理念はどのようなものなのですか?
常に誰に対しても同じように誠意を持って対応するということですね。仕入れさんであっても、大きいお客さんも小さいお客さんも、また社員に対しても、きちんと気持ちを持って分け隔てなく接しないといけないと考えています。
当社は創業180年を超えて地方へ行くとすごい老舗のように言われますが、前回の堀金箔粉さんはまもなく創業300年ですし、京都では特に珍しいものではありません。
ただ100年200年と事業を続けるのは本当にたいへんなことです。
ITバブルの時期を経てみると余計に感じます。
流行に乗ることは大切なのですが、それだけではいけません。
長く続いているところでも、事件や事故があると会社を続けることができなくなってしまいます。
■株式会社井助商店HP
■財団法人 京都産業21HP
■京都造形芸術大学HP
■株式会社井助商店 沖野俊之 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年05月12日
漆はワインのように産出する地域によって特色があります
第17回 株式会社井助商店 代表取締役 沖野俊之 vol.1

堀金箔粉株式会社の堀社長から、「ほんとにユニークで明るくアイデアにあふれている方です。新しい取り組みにも積極的で京都文化もたいへん愛されています」と紹介をいただいた井助商店の沖野社長です。井助商店は江戸後期の創業、元々は漆器や工芸品に使う漆の製造・卸の会社です。近年は漆だけでなく漆器の販売も手がけています。
――江戸時代の後期に漆の精製・販売を生業として創業されたそうですね?
はい。江戸時代後期の創業です。文政年間(1818年~1829年)に、この地で創業しています。
漆の精製というのは、漆の木からとったそのままの樹液を濾過したり、水分を取り除いたりします。
また漆は自然のものなので、ワインのように漆を産出する地域によって特色があります。
粘度が高いとか乾きが早いとかの違いですね。
当然、年によっても微妙な違いがあるので、
それをどうブレンドするかが各漆屋さんのテクニックです。
漆は、乾くスピードや粘度によって、漆器の上塗りに向いているなど、それぞれ用途が違ってきます。
特に当社は金箔の下に塗る箔下漆が好評頂いています。
他にも漆の代替品としてカシュー塗料・ウレタン塗料などのも多く取り扱っています。
木製品に塗る塗料なのですが、漆に比べて、安価でまた早く乾くなどの特徴があります。
また京都は元々染色関連の会社が多いのですが、
以前は染色の材料の1つとして漆が接着剤として使われていた為、
現在でも染色に使う漆以外の資材も販売しています。
それと漆器の販売が事業の柱になっています。
――漆器の販売はどういう経緯で始められたのですか?
漆を納品していた漆器屋さんから京都で売ってくれないかという依頼があって、
最初は事務所の玄関先に並べるところから小売をスタートさせました。
今でも実店舗はここにある小売店だけです。
あとは全国の百貨店で開催されている京都物産展に積極的に参加して販売をしています。
一年間に24~5回は参加しています。
併せて最近はホームページを通じてのインターネット販売にも力を入れています。
2007年には京都商工会議所のホームページコンテストで最優秀賞を受賞したのですが、
通常のインターネット販売に加えて、
最近は百貨店の物産展で興味をもってくれた方からネットを通じて問い合わせや注文も増えました。
逆にホームページを見た地方の方が地元の百貨店の物産展に訪れて頂いています。
相乗効果は大きいですね。
何年か前だと物産展に来られるのは50代や60代の方が多く、
インターネットが有効かどうか半信半疑だったのですが、
今はその年代の方でも普通にインターネットを通じて注文を頂くようになっています。
■株式会社井助商店HP
■京都ホームページコンテスト2007
■株式会社井助商店 沖野俊之 【1】 >> 【2】 >> 【3】

堀金箔粉株式会社の堀社長から、「ほんとにユニークで明るくアイデアにあふれている方です。新しい取り組みにも積極的で京都文化もたいへん愛されています」と紹介をいただいた井助商店の沖野社長です。井助商店は江戸後期の創業、元々は漆器や工芸品に使う漆の製造・卸の会社です。近年は漆だけでなく漆器の販売も手がけています。
――江戸時代の後期に漆の精製・販売を生業として創業されたそうですね?
はい。江戸時代後期の創業です。文政年間(1818年~1829年)に、この地で創業しています。
漆の精製というのは、漆の木からとったそのままの樹液を濾過したり、水分を取り除いたりします。
また漆は自然のものなので、ワインのように漆を産出する地域によって特色があります。
粘度が高いとか乾きが早いとかの違いですね。
当然、年によっても微妙な違いがあるので、
それをどうブレンドするかが各漆屋さんのテクニックです。
漆は、乾くスピードや粘度によって、漆器の上塗りに向いているなど、それぞれ用途が違ってきます。
特に当社は金箔の下に塗る箔下漆が好評頂いています。
他にも漆の代替品としてカシュー塗料・ウレタン塗料などのも多く取り扱っています。
木製品に塗る塗料なのですが、漆に比べて、安価でまた早く乾くなどの特徴があります。
また京都は元々染色関連の会社が多いのですが、
以前は染色の材料の1つとして漆が接着剤として使われていた為、
現在でも染色に使う漆以外の資材も販売しています。
それと漆器の販売が事業の柱になっています。
――漆器の販売はどういう経緯で始められたのですか?
漆を納品していた漆器屋さんから京都で売ってくれないかという依頼があって、
最初は事務所の玄関先に並べるところから小売をスタートさせました。
今でも実店舗はここにある小売店だけです。
あとは全国の百貨店で開催されている京都物産展に積極的に参加して販売をしています。
一年間に24~5回は参加しています。
併せて最近はホームページを通じてのインターネット販売にも力を入れています。
2007年には京都商工会議所のホームページコンテストで最優秀賞を受賞したのですが、
通常のインターネット販売に加えて、
最近は百貨店の物産展で興味をもってくれた方からネットを通じて問い合わせや注文も増えました。
逆にホームページを見た地方の方が地元の百貨店の物産展に訪れて頂いています。
相乗効果は大きいですね。
何年か前だと物産展に来られるのは50代や60代の方が多く、
インターネットが有効かどうか半信半疑だったのですが、
今はその年代の方でも普通にインターネットを通じて注文を頂くようになっています。
■株式会社井助商店HP
■京都ホームページコンテスト2007
■株式会社井助商店 沖野俊之 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年04月03日
京都は町もお寺や神社も自然も文化も全部あります。
第16回 堀金箔粉株式会社 代表取締役 堀智行 vol.3

――堀社長の経歴について教えてください。
大学を卒業してすぐに堀金箔粉に入社しました。
姉がひとりいるのですが、男は私だけだったので、
自分が継ぐという意識はあったのですが、
高校の頃はあらかじめ決められたような気がしてなんとなく嫌なものでした。
それが大学生になると、自分はそういうふうに生まれてきたのかなぁと考えるようになりました。
子どもの頃から父や周りのものに言われていたので、
いつの間にか洗脳されてしまったのかもしれません(笑)。
入社以降、倉庫の管理から営業まで業務はだいたい経験しました。
特に営業は長かったので、今も営業にはただ売上をあげろ、
というような言い方はしなくなりました。
数字だけが大切なのではなく、何を売るのか、どんなものを作ればいいのか、
やはり仕組みを作っていくことが大事なのだと思っています。
父からは早く社長になるようにと言われていたのですが、
社長に就任したのは平成16年のことです。私が34歳のときですね。
最初にも言ったように弊社は再来年、創業300年の節目を迎えます。
このタイミングで自分が社長であるということはすごくラッキーなことです。
ただ300年続いたといってもそれは終着点ではなく、通過点でしかありません。
やはり次ぎの世代にしっかりと残していきたいですね。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を堀社長が案内する場合、どこに案内しますか?
そうですね・・・、京都はほんとに何処もいいですよね。
どこそこに案内すると決めるのではなく、
例えばすぐそこの御幸町通りを三条から四条まで歩くとか、
三条通りを歩くだけでも、京都にしかないものが揃っています。
それだけで京都らしさを味わえると思いますよ。
京都は町もお寺や神社も自然も文化も全部あって、
それが京都のよさではないでしょうか。
ただ、最近は自然ではない作られた京都が多くなってきたように感じることもあります。
すごくわざとらしい京都弁で対応されたりすると、ちょっと違うなぁと思います。
あと誰かを案内するというのではないのですが、
自分がしたいのは、鴨川の河原でのんびりと昼寝をしたいですね。
春ですし、一日中、ぼーっとできたら、ええやろうなぁ。
――それでは、次ぎに紹介していただく沖野社長はどんな方ですか?
ほんとにユニークで明るい方です。私より少し年上なのですが、
実はキャラがかぶっていると言われます(笑)。
アイデアにあふれていて新しい取り組みもされています。
京都文化もたいへん愛されているので、いろいろな話がきけると思いますよ。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2009年3月3日取材)
*********************************
 堀金箔粉株式会社
堀金箔粉株式会社
京都市中京区御池通御幸町東入大文字町356
代表取締役 堀智行
電話:(075)231-5327
FAX:(075)231-5357
HP:http://www.horikin.co.jp/
■堀金箔粉株式会社 堀智行 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――堀社長の経歴について教えてください。
大学を卒業してすぐに堀金箔粉に入社しました。
姉がひとりいるのですが、男は私だけだったので、
自分が継ぐという意識はあったのですが、
高校の頃はあらかじめ決められたような気がしてなんとなく嫌なものでした。
それが大学生になると、自分はそういうふうに生まれてきたのかなぁと考えるようになりました。
子どもの頃から父や周りのものに言われていたので、
いつの間にか洗脳されてしまったのかもしれません(笑)。
入社以降、倉庫の管理から営業まで業務はだいたい経験しました。
特に営業は長かったので、今も営業にはただ売上をあげろ、
というような言い方はしなくなりました。
数字だけが大切なのではなく、何を売るのか、どんなものを作ればいいのか、
やはり仕組みを作っていくことが大事なのだと思っています。
父からは早く社長になるようにと言われていたのですが、
社長に就任したのは平成16年のことです。私が34歳のときですね。
最初にも言ったように弊社は再来年、創業300年の節目を迎えます。
このタイミングで自分が社長であるということはすごくラッキーなことです。
ただ300年続いたといってもそれは終着点ではなく、通過点でしかありません。
やはり次ぎの世代にしっかりと残していきたいですね。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を堀社長が案内する場合、どこに案内しますか?
そうですね・・・、京都はほんとに何処もいいですよね。
どこそこに案内すると決めるのではなく、
例えばすぐそこの御幸町通りを三条から四条まで歩くとか、
三条通りを歩くだけでも、京都にしかないものが揃っています。
それだけで京都らしさを味わえると思いますよ。
京都は町もお寺や神社も自然も文化も全部あって、
それが京都のよさではないでしょうか。
ただ、最近は自然ではない作られた京都が多くなってきたように感じることもあります。
すごくわざとらしい京都弁で対応されたりすると、ちょっと違うなぁと思います。
あと誰かを案内するというのではないのですが、
自分がしたいのは、鴨川の河原でのんびりと昼寝をしたいですね。
春ですし、一日中、ぼーっとできたら、ええやろうなぁ。
――それでは、次ぎに紹介していただく沖野社長はどんな方ですか?
ほんとにユニークで明るい方です。私より少し年上なのですが、
実はキャラがかぶっていると言われます(笑)。
アイデアにあふれていて新しい取り組みもされています。
京都文化もたいへん愛されているので、いろいろな話がきけると思いますよ。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2009年3月3日取材)
*********************************
京都市中京区御池通御幸町東入大文字町356
代表取締役 堀智行
電話:(075)231-5327
FAX:(075)231-5357
HP:http://www.horikin.co.jp/
■堀金箔粉株式会社 堀智行 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年04月02日
金は主役(=商品)を引き立たせる名脇役(=素材)なのです。
第16回 堀金箔粉株式会社 代表取締役 堀智行 vol.2

――京都から職人がいなくなるなど、やはり伝統産業としては厳しいのでしょうか?
はい、金箔や金粉を使う産業は減少しています。たとえば金仏壇の市場は規模が縮小しています。
さらに金仏壇自体も海外で作られるようになっており、
そうした金仏壇にはやはり海外の金箔が使われます。
そこを追っかけてもしようがありません。
しかし、金仏壇の市場が縮小しているそのとなりには
お寺の納骨堂などの新しい市場が成長しています。
新しい家を建てても金仏壇を置かない家庭が増えている中で、
わざわざ遠方にあるお墓にいかずとも、
お寺の納骨堂にお参りすればいいようになってきています。
仕事の都合で引越しをしても、お寺にご先祖のお世話を任せられます。
成熟した市場のとなりには必ず成長市場があります。
前回の山田繊維さんの和装関係の例でも、
エコやファッション性に目を向けることによって成長産業になります。
時代とともに変化する市場に対して敏感に対応していく必要性は強く感じますね。
会社として取り組んでいるのは、金箔や金粉を使っているところに材料を販売するのではなく、
一緒に“ものづくり”をするということです。
仏壇関係、呉服、帯、陶器、漆器と京都は金箔や金粉の消費地でもあるのですが、
それぞれに高い技術を持っているので、力をあわせて新しい“ものづくり”に取り組んでいます。
京都の伝統産業はどこも苦しいのですが、そこから新しく発信できるものがないか模索しています。
――ホームページを見ると仏壇仏具などはほんの一部で、金や金箔を使うだけでなく、その技術を応用して展開している事業が多く紹介されていますね。
 ホームページを見てそういう風に感じていただくのは嬉しいですね。金属、箔、粉にこだわり、新たな商品展開を模索しているところです。
ホームページを見てそういう風に感じていただくのは嬉しいですね。金属、箔、粉にこだわり、新たな商品展開を模索しているところです。
金属を1万分の1ミリにまで薄くする技術というのは伝統的な技から生まれてきています。薄い金属ということが商品の価値になり、最新の電気部品の接点に使われたりもしています。
今も取引先は工芸品などの伝統産業が多いのですが、食品から美容まで様々な業種のお客さんとの付き合いが広がってきました。
会社が300年続いている信用から新しい情報が集まる側面もあり、そこは感謝しています。
実はこの御池通に面した店舗も以前は事務所としての機能しかなかったのですが、
情報発信をしていきたいと思い2002年に改装して今のような店を構えました。
PR用に金箔を貼った自転車や大きな置時計を置いています。
インパクトがあるので、この前で写真を撮っていく方もけっこういます。
商品を買っていただくだけでなく、この店舗を見ていただき取引がはじまった企業さんもあります。
 ――堀金箔粉の経営理念はどのようなものなのですか?
――堀金箔粉の経営理念はどのようなものなのですか?
経営理念は、「本業に忠実であれ」をはじめとして、いくつかあるのですが、特に大切にしているのは「信用をモットーにする」ことと、「三方よしの精神」ですね。得意先、仕入先、社員がよりよくなるような会社にしたいですね。
金を使うことによって、いろいろな商品の価値を高めることができます。金自体が主役ではなく、あくまで金は主役(=商品)を引き立たせる名脇役(=素材)なのです。
お客さまに十分に儲けていただいているので、その取引が続き、その結果当社は300年続いたのだと考えています。
短期間で一時的に大きな利益をあげることよりも永く続く商売を大切にしています。取引先が健全に事業を行い、儲けていただければ、さらに拡大する分野も生まれます。それがまた取引量や取引先の拡大に繋がっていきます。
■山田繊維株式会社HP
■堀金箔粉株式会社HP
■堀金箔粉株式会社 堀智行 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――京都から職人がいなくなるなど、やはり伝統産業としては厳しいのでしょうか?
はい、金箔や金粉を使う産業は減少しています。たとえば金仏壇の市場は規模が縮小しています。
さらに金仏壇自体も海外で作られるようになっており、
そうした金仏壇にはやはり海外の金箔が使われます。
そこを追っかけてもしようがありません。
しかし、金仏壇の市場が縮小しているそのとなりには
お寺の納骨堂などの新しい市場が成長しています。
新しい家を建てても金仏壇を置かない家庭が増えている中で、
わざわざ遠方にあるお墓にいかずとも、
お寺の納骨堂にお参りすればいいようになってきています。
仕事の都合で引越しをしても、お寺にご先祖のお世話を任せられます。
成熟した市場のとなりには必ず成長市場があります。
前回の山田繊維さんの和装関係の例でも、
エコやファッション性に目を向けることによって成長産業になります。
時代とともに変化する市場に対して敏感に対応していく必要性は強く感じますね。
会社として取り組んでいるのは、金箔や金粉を使っているところに材料を販売するのではなく、
一緒に“ものづくり”をするということです。
仏壇関係、呉服、帯、陶器、漆器と京都は金箔や金粉の消費地でもあるのですが、
それぞれに高い技術を持っているので、力をあわせて新しい“ものづくり”に取り組んでいます。
京都の伝統産業はどこも苦しいのですが、そこから新しく発信できるものがないか模索しています。
――ホームページを見ると仏壇仏具などはほんの一部で、金や金箔を使うだけでなく、その技術を応用して展開している事業が多く紹介されていますね。
金属を1万分の1ミリにまで薄くする技術というのは伝統的な技から生まれてきています。薄い金属ということが商品の価値になり、最新の電気部品の接点に使われたりもしています。
今も取引先は工芸品などの伝統産業が多いのですが、食品から美容まで様々な業種のお客さんとの付き合いが広がってきました。
会社が300年続いている信用から新しい情報が集まる側面もあり、そこは感謝しています。
実はこの御池通に面した店舗も以前は事務所としての機能しかなかったのですが、
情報発信をしていきたいと思い2002年に改装して今のような店を構えました。
PR用に金箔を貼った自転車や大きな置時計を置いています。
インパクトがあるので、この前で写真を撮っていく方もけっこういます。
商品を買っていただくだけでなく、この店舗を見ていただき取引がはじまった企業さんもあります。
経営理念は、「本業に忠実であれ」をはじめとして、いくつかあるのですが、特に大切にしているのは「信用をモットーにする」ことと、「三方よしの精神」ですね。得意先、仕入先、社員がよりよくなるような会社にしたいですね。
金を使うことによって、いろいろな商品の価値を高めることができます。金自体が主役ではなく、あくまで金は主役(=商品)を引き立たせる名脇役(=素材)なのです。
お客さまに十分に儲けていただいているので、その取引が続き、その結果当社は300年続いたのだと考えています。
短期間で一時的に大きな利益をあげることよりも永く続く商売を大切にしています。取引先が健全に事業を行い、儲けていただければ、さらに拡大する分野も生まれます。それがまた取引量や取引先の拡大に繋がっていきます。
■山田繊維株式会社HP
■堀金箔粉株式会社HP
■堀金箔粉株式会社 堀智行 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年04月01日
小豆大の金の地金が畳一枚の大きさになります。
第16回 堀金箔粉株式会社 代表取締役 堀智行 vol.1

山田繊維株式会社の山田社長から、「ものすごく正直やしで素直な方です。もちろん仕事に関してはたいへんシビアで、業界では高品質な材料として広く認知されているのですが、さらにいいものにするために常に努力をされています」と紹介をいただいた堀金箔粉の堀社長です。
堀金箔粉株式会社は“ほりきん”の名で知られ、まもなく創業300年を迎える老舗です。金箔・金粉を江戸時代から扱いながら、最近はその技術を応用し新しい分野にも挑戦しています。
――創業は江戸時代とうかがいました。創業当時から金箔や金粉を扱っていたのですか?
はい。江戸時代の正徳元年、1711年に創業しました。再来年には創業300年を迎えます。
私は10代目にあたります。創業時から金箔や金粉を扱っていました。
江戸時代に金は配給制だったので、幕府から配給を受けた金の地金を、
金箔や金粉に加工し、販売をしていました。初代は金を加工する職人でした。
江戸時代の京都は江戸、会津、金沢と並ぶ金箔や金粉の産地でした。
やはり大きな寺社仏閣が多く需要が高かったのでしょう。
金の地金から金箔を作ることを、箔を打つといいます。
箔を打つ作業はたいへん大きな音と騒音の問題、跡継ぎの問題があって
残念ながら3年前に京都に職人はいなくなりました。
特に後継者問題は大きいですね。技術を習得するのに長い期間が必要ですし、
技術を得たとしてもそれに見合った加工賃が得られるのかというと、難しいのが現状です。
金の地金を叩いて金を伸ばしていく作業はかっては職人さんが向いあって
金槌で叩いていたのですが、今は機械でハンマーを落として伸ばします。
伸びた金を移しかえ、また叩くという作業が9工程くらいあって、
その作業が分業制になっています。今は金沢に箔を打つ職人さんが多いですね。
<*上記写真は京都に最後に残った職人さんが使っていた機械です。>
――金の地金を金箔に加工するときどのくらいの大きさにまで伸ばすのですか?
仕入れた地金が、職人さんの手によって金箔になります。
それを金箔のままや、金粉にした状態でお客さんに供給しています。
職人の手によって小豆大の金の地金は畳一枚の大きさになります。
その厚さは1万分の1ミリくらいで、伸ばした金箔は向こう側が透けてみえるほど薄くなります。
薄いからこそ加工がしやすく、たとえば金箔を貼る漆とのくい付きもよくなります。
厚いと剥れやすくなるので、薄いということは非常に大切です。
ところが加工しやすくなるのですが、薄くなればなるほど扱いが難しくなります。
息をするだけで飛んでしまうのです。
■堀金箔粉株式会社HP
■堀金箔粉株式会社 堀智行 【1】 >> 【2】 >> 【3】

山田繊維株式会社の山田社長から、「ものすごく正直やしで素直な方です。もちろん仕事に関してはたいへんシビアで、業界では高品質な材料として広く認知されているのですが、さらにいいものにするために常に努力をされています」と紹介をいただいた堀金箔粉の堀社長です。
堀金箔粉株式会社は“ほりきん”の名で知られ、まもなく創業300年を迎える老舗です。金箔・金粉を江戸時代から扱いながら、最近はその技術を応用し新しい分野にも挑戦しています。
――創業は江戸時代とうかがいました。創業当時から金箔や金粉を扱っていたのですか?
はい。江戸時代の正徳元年、1711年に創業しました。再来年には創業300年を迎えます。
私は10代目にあたります。創業時から金箔や金粉を扱っていました。
江戸時代に金は配給制だったので、幕府から配給を受けた金の地金を、
金箔や金粉に加工し、販売をしていました。初代は金を加工する職人でした。
江戸時代の京都は江戸、会津、金沢と並ぶ金箔や金粉の産地でした。
やはり大きな寺社仏閣が多く需要が高かったのでしょう。
金の地金から金箔を作ることを、箔を打つといいます。
箔を打つ作業はたいへん大きな音と騒音の問題、跡継ぎの問題があって
残念ながら3年前に京都に職人はいなくなりました。
特に後継者問題は大きいですね。技術を習得するのに長い期間が必要ですし、
技術を得たとしてもそれに見合った加工賃が得られるのかというと、難しいのが現状です。
金の地金を叩いて金を伸ばしていく作業はかっては職人さんが向いあって
金槌で叩いていたのですが、今は機械でハンマーを落として伸ばします。
伸びた金を移しかえ、また叩くという作業が9工程くらいあって、
その作業が分業制になっています。今は金沢に箔を打つ職人さんが多いですね。
<*上記写真は京都に最後に残った職人さんが使っていた機械です。>
――金の地金を金箔に加工するときどのくらいの大きさにまで伸ばすのですか?
仕入れた地金が、職人さんの手によって金箔になります。
それを金箔のままや、金粉にした状態でお客さんに供給しています。
職人の手によって小豆大の金の地金は畳一枚の大きさになります。
その厚さは1万分の1ミリくらいで、伸ばした金箔は向こう側が透けてみえるほど薄くなります。
薄いからこそ加工がしやすく、たとえば金箔を貼る漆とのくい付きもよくなります。
厚いと剥れやすくなるので、薄いということは非常に大切です。
ところが加工しやすくなるのですが、薄くなればなるほど扱いが難しくなります。
息をするだけで飛んでしまうのです。
■堀金箔粉株式会社HP
■堀金箔粉株式会社 堀智行 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年03月11日
自分たちのポジションを決めなあかん。
第15回 山田繊維株式会社 代表取締役 山田芳生 vol.3
――山田社長の経歴について教えてください。
大学を卒業して、アパレル大手のワールドに入社しました。
就職活動をはじめるときには、会社を継ぐことは決めていたので、
同じ繊維関係の会社にターゲットを絞り、就職活動をしました。
実は就職活動を始める前の私はほんとうに遊ぶことしか考えていないような感じで、
会社を継ぐよりも、軽い気持ちでショップやレストランなど自分で事業を起こしたいと考えていました。
ところが3回生の終わりになり就職活動をはじめるようになって、どうしようかなと悩んでいたときに、
かなり年上の先輩に「ほんまに自分でやりたいものがあるとしたら、
親父さんの会社をお前が自分でちゃんと経営ができれば、
そこで成功すれば、自分のやりたいことができる一番の近道ちゃうか」とアドバイスを受けて、
「そうか!」と納得したんですよ。
山田繊維という会社をちゃんと自分の土台にできれば、好きなことできる。
そういう邪まな気持ちが少なからずあったのですが、当時はそれですっきりしました。
自分で一から事業をはじめるにしても、土台があると強い。だから土台をしっかりさせよう。
そのための就職をしようと決心しました。

――山田繊維へはいつ入社されたのですか?
ワールドに入社したときはバブルの全盛の頃で、営業の仕事をしていました。
華やかな世界で刺激的でしたが、ほんとうに忙しい毎日でした。
それで5年たったときに東京に支店を出す話しがあり、
当時、社長だった父に「お前も東京にいけ」と言われ、「ええよ」という感じで山田繊維に入りました。
最初はワールドとの違いにカルチャーショックを受けました。
東京に支店を出したものの、風呂敷のマーケットは縮小傾向にあるような厳しい状況でしたし、
なんとかせなあかんけど、どうしていいかわからないような状態でした。
当時、風呂敷とあわせて和雑貨も扱っていたのですが、
最初は雑貨に光明を見出そうとしました。
ちょうど雑貨店、和雑貨店というのが増えていた頃で雑貨販売の大手さんと話しができるようになり、
取引先も増え、これならいけるんちゃうやろかと思ったのですが、
いろいろな問題があり、何年かたって雑貨は難しいという結論に至りました。
そこで、やはり自分たちのポジションを決めなあかん。
やっぱり風呂敷やろ、ということに気がつき、
もっと風呂敷について研究しないといけないのでは、
となったのが2000年くらいのことでした。
まず風呂敷の講習会をはじめました。最初は無料でやりますよと、
こちらから頼んで講習会を開催させてもらいました。
講習会では風呂敷の使い方はもちろん、
日本の伝統文化が凝縮されている柄や色についても話をするようになりました。
社長に就任したのはそうした活動が軌道にのりはじめた2004年のことです。
そういう蓄積があったのでアンテナショップ「むす美」がオープンしたときに
スムーズに風呂敷を提案することができました。
風呂敷と和雑貨の取り扱いが半々だった頃もあったのですが、
今は8対2くらいの割合になっています。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を山田社長が案内する場合、どこに案内しますか?
私は日本で唯一残っている唐紙屋の「唐長」さんへ案内したいと思います。
唐紙というのは壁紙や襖に使う紙のことです。
昔からある建築物にはたいていどこにいっても唐紙が使われています。
二条城や京都御所にもありますし、古くから残っている寺院にはほとんど唐紙が使われています。
「唐長」さんはモダンなインテリアのひとつとして唐紙を提案している会社です。
400年続く「唐長」さんの現在の主、千田堅吉さんは11代目になります。
奥さまとお子様が3人おられるのですが、皆さんが、唐紙や京都の文化を大切にしながら、
新しい世界を吸収し、唐紙をさらに価値のあるものにするために仕事に取り組んでいます。
目につくところでは四条烏丸のCOCON烏丸に外壁に使われている雲の模様が
唐長さんの持っていた柄です。
日本を代表する建築家の隈研吾さんが、
「ぜひ唐長さんの柄を使わせて欲しい」と頼まれたそうです。
そのCOCON烏丸には「唐長」さんのカードショップがはいっています。
そして三条両替町にあるショールーム。修学院には工房があって、
そこも見学できるようになっています。その3箇所にぜひ案内したいですね。
唐長さんが持っているコンテンツはたいへん素晴らしいものです。
それだけでなくご主人をはじめとする家族の方々からも京都の文化を強く感じます。
――それでは、次ぎに紹介していただく堀社長はどんな方ですか?
糸偏(繊維関係)の会社が続いたので、次は金属の会社を紹介させていただきます。
堀社長はものすごく正直やしで素直な方です。「困ったなあ、
かなわんなあ」というのも正直に言うようなところがあって、そういうところがすごく好ましい方です。
もちろん仕事に関してはたいへんシビアで、
業界では高品質な材料として広く認知されているのですが、
さらにいいものにするために常に努力をされています。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2009年2月4日取材)
■唐長HP
*********************************
 山田繊維株式会社
山田繊維株式会社
京都市中京区新町通二条南入頭町18
代表取締役 山田芳生
電話:(075)256-0123
FAX:(075)256-0256
HP:http://www.ymds.co.jp/
「むす美」HP:http://www.kyoto-musubi.com/
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――山田社長の経歴について教えてください。
大学を卒業して、アパレル大手のワールドに入社しました。
就職活動をはじめるときには、会社を継ぐことは決めていたので、
同じ繊維関係の会社にターゲットを絞り、就職活動をしました。
実は就職活動を始める前の私はほんとうに遊ぶことしか考えていないような感じで、
会社を継ぐよりも、軽い気持ちでショップやレストランなど自分で事業を起こしたいと考えていました。
ところが3回生の終わりになり就職活動をはじめるようになって、どうしようかなと悩んでいたときに、
かなり年上の先輩に「ほんまに自分でやりたいものがあるとしたら、
親父さんの会社をお前が自分でちゃんと経営ができれば、
そこで成功すれば、自分のやりたいことができる一番の近道ちゃうか」とアドバイスを受けて、
「そうか!」と納得したんですよ。
山田繊維という会社をちゃんと自分の土台にできれば、好きなことできる。
そういう邪まな気持ちが少なからずあったのですが、当時はそれですっきりしました。
自分で一から事業をはじめるにしても、土台があると強い。だから土台をしっかりさせよう。
そのための就職をしようと決心しました。
――山田繊維へはいつ入社されたのですか?
ワールドに入社したときはバブルの全盛の頃で、営業の仕事をしていました。
華やかな世界で刺激的でしたが、ほんとうに忙しい毎日でした。
それで5年たったときに東京に支店を出す話しがあり、
当時、社長だった父に「お前も東京にいけ」と言われ、「ええよ」という感じで山田繊維に入りました。
最初はワールドとの違いにカルチャーショックを受けました。
東京に支店を出したものの、風呂敷のマーケットは縮小傾向にあるような厳しい状況でしたし、
なんとかせなあかんけど、どうしていいかわからないような状態でした。
当時、風呂敷とあわせて和雑貨も扱っていたのですが、
最初は雑貨に光明を見出そうとしました。
ちょうど雑貨店、和雑貨店というのが増えていた頃で雑貨販売の大手さんと話しができるようになり、
取引先も増え、これならいけるんちゃうやろかと思ったのですが、
いろいろな問題があり、何年かたって雑貨は難しいという結論に至りました。
そこで、やはり自分たちのポジションを決めなあかん。
やっぱり風呂敷やろ、ということに気がつき、
もっと風呂敷について研究しないといけないのでは、
となったのが2000年くらいのことでした。
まず風呂敷の講習会をはじめました。最初は無料でやりますよと、
こちらから頼んで講習会を開催させてもらいました。
講習会では風呂敷の使い方はもちろん、
日本の伝統文化が凝縮されている柄や色についても話をするようになりました。
社長に就任したのはそうした活動が軌道にのりはじめた2004年のことです。
そういう蓄積があったのでアンテナショップ「むす美」がオープンしたときに
スムーズに風呂敷を提案することができました。
風呂敷と和雑貨の取り扱いが半々だった頃もあったのですが、
今は8対2くらいの割合になっています。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を山田社長が案内する場合、どこに案内しますか?
私は日本で唯一残っている唐紙屋の「唐長」さんへ案内したいと思います。
唐紙というのは壁紙や襖に使う紙のことです。
昔からある建築物にはたいていどこにいっても唐紙が使われています。
二条城や京都御所にもありますし、古くから残っている寺院にはほとんど唐紙が使われています。
「唐長」さんはモダンなインテリアのひとつとして唐紙を提案している会社です。
400年続く「唐長」さんの現在の主、千田堅吉さんは11代目になります。
奥さまとお子様が3人おられるのですが、皆さんが、唐紙や京都の文化を大切にしながら、
新しい世界を吸収し、唐紙をさらに価値のあるものにするために仕事に取り組んでいます。
目につくところでは四条烏丸のCOCON烏丸に外壁に使われている雲の模様が
唐長さんの持っていた柄です。
日本を代表する建築家の隈研吾さんが、
「ぜひ唐長さんの柄を使わせて欲しい」と頼まれたそうです。
そのCOCON烏丸には「唐長」さんのカードショップがはいっています。
そして三条両替町にあるショールーム。修学院には工房があって、
そこも見学できるようになっています。その3箇所にぜひ案内したいですね。
唐長さんが持っているコンテンツはたいへん素晴らしいものです。
それだけでなくご主人をはじめとする家族の方々からも京都の文化を強く感じます。
――それでは、次ぎに紹介していただく堀社長はどんな方ですか?
糸偏(繊維関係)の会社が続いたので、次は金属の会社を紹介させていただきます。
堀社長はものすごく正直やしで素直な方です。「困ったなあ、
かなわんなあ」というのも正直に言うようなところがあって、そういうところがすごく好ましい方です。
もちろん仕事に関してはたいへんシビアで、
業界では高品質な材料として広く認知されているのですが、
さらにいいものにするために常に努力をされています。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2009年2月4日取材)
■唐長HP
*********************************
京都市中京区新町通二条南入頭町18
代表取締役 山田芳生
電話:(075)256-0123
FAX:(075)256-0256
HP:http://www.ymds.co.jp/
「むす美」HP:http://www.kyoto-musubi.com/
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年03月10日
DVD「ふろしきレシピ」をリリースしました
第15回 山田繊維株式会社 代表取締役 山田芳生 vol.2

――今、風呂敷ブームというか、エコ的な観点から、風呂敷が見直されてきていますね
はい。ブームというにはまだ小さなものですが、
今までとは違うマーケットで風呂敷が売れています。
新しいマーケット、新しい顧客の開拓という部分で平成17年に東京でオープンした
アンテナショップ「むす美」のはたした役割は大きいですね。
実は今日(2月4日)が「むす美」のオープン記念日なのです。
毎年、公募展を開催しているのですが、昨日、東京でその授与式をやってきたところです。
今年は「ふろしき愛用フォト部門」「ふろしきエピソード部門」「手作りふろしき部門」の
三つの部門で117点の応募がありました。

――「むす美」がオープンしたとき他に風呂敷専門のショップはなかったそうですね?
そうですね。メーカーである弊社が専門店を運営する目的は、
小売に進出するということではなく、メーカーとして、
直接ユーザーと接することでいろいろ意味で緊張感をもち、
もっと質の高い風呂敷を提供するための情報収集と
風呂敷の使い方などの情報発信をしたいという考えがありました。
ただ正直なところ、最初はたった一軒のショップで情報発信ができるとは思っていませんでした。
ところがオープンしてみる当初、考えていた以上に風呂敷というものが
世の中にとっては非常に珍しいものであったようです。
オープンのレセプションを開いたところNHKが取材にきてくれて、
そのとき第1回の講習会を2月23日(風呂敷の日です)に
この「むす美」で開くと案内させていただきました。
その放送をみた多数のプレスや雑誌から講習会の取材オファーが届きました。
それ以降、多いときは月10件くらい取材がはいっていました。
今でも毎月、5件程の取材を受けています。

当時はちょうど小池百合子さんが環境大臣でした。
クールビズ・ウォームビズというのがあって、「次ぎは風呂敷よ」と
小池さんが言っていたときに「むす美」はオープン前の工事中でした。
それで、オープンして間もなく東京の三越で風呂敷のファッションショーを開催したときに
小池さんにコメントをいただいたりして、エコと風呂敷というものがうまく結びつきました。
風呂敷は工夫してものを大切に使うという面をもっています。
カバンや紙袋に比べて広い用途で使うことができます。
なにより使ったあとはコンパクトにまとめることができるので場所をとりません。
そういうところがエコロジーの考え方と共感したのでしょう。
しかし風呂敷が日本の伝統文化であり、環境にいいからと言っても、
それだけでは簡単に風呂敷を使ってもらえるものでもありません。
それ以上に、ほんまにかわいいとか、かっこいいと思ってもらえる、
ほんまにこれやったら使いたいと思ってもらえるような風呂敷を提案していかないと。
それで各イベントや講習会では環境にいいんですけど、
そんな理屈じゃなくて風呂敷をこうやって使ったらいいと思いませんか、
というような提案を続けています。
――風呂敷の結び方やつかい方を動画にまとめたDVDをリリースされたそうですね。
 はい。ちょうど「ふろしきレシピ」というDVDをリリースしたばかりです。
はい。ちょうど「ふろしきレシピ」というDVDをリリースしたばかりです。
自分で風呂敷を使うひとは問題ないのですが、風呂敷を誰かにプレゼントするとき、その相手は風呂敷の使い方や結び方を知らないかもしれません。そういうとき、風呂敷の使い方から結び方まで映像で案内できるDVDをあわせてプレゼントしてあげるといいかなと思いました。
風呂敷に特化して考えていると、いろいろアイデアが湧いてきます。和文化というと大層ですが、風呂敷が現代の生活のなかで生きているものにし続けたいですね。それこそが我々の使命であり、仕事であると今は考えています。
■山田繊維株式会社HP
■むす美HP
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】

――今、風呂敷ブームというか、エコ的な観点から、風呂敷が見直されてきていますね
はい。ブームというにはまだ小さなものですが、
今までとは違うマーケットで風呂敷が売れています。
新しいマーケット、新しい顧客の開拓という部分で平成17年に東京でオープンした
アンテナショップ「むす美」のはたした役割は大きいですね。
実は今日(2月4日)が「むす美」のオープン記念日なのです。
毎年、公募展を開催しているのですが、昨日、東京でその授与式をやってきたところです。
今年は「ふろしき愛用フォト部門」「ふろしきエピソード部門」「手作りふろしき部門」の
三つの部門で117点の応募がありました。

――「むす美」がオープンしたとき他に風呂敷専門のショップはなかったそうですね?
そうですね。メーカーである弊社が専門店を運営する目的は、
小売に進出するということではなく、メーカーとして、
直接ユーザーと接することでいろいろ意味で緊張感をもち、
もっと質の高い風呂敷を提供するための情報収集と
風呂敷の使い方などの情報発信をしたいという考えがありました。
ただ正直なところ、最初はたった一軒のショップで情報発信ができるとは思っていませんでした。
ところがオープンしてみる当初、考えていた以上に風呂敷というものが
世の中にとっては非常に珍しいものであったようです。
オープンのレセプションを開いたところNHKが取材にきてくれて、
そのとき第1回の講習会を2月23日(風呂敷の日です)に
この「むす美」で開くと案内させていただきました。
その放送をみた多数のプレスや雑誌から講習会の取材オファーが届きました。
それ以降、多いときは月10件くらい取材がはいっていました。
今でも毎月、5件程の取材を受けています。

当時はちょうど小池百合子さんが環境大臣でした。
クールビズ・ウォームビズというのがあって、「次ぎは風呂敷よ」と
小池さんが言っていたときに「むす美」はオープン前の工事中でした。
それで、オープンして間もなく東京の三越で風呂敷のファッションショーを開催したときに
小池さんにコメントをいただいたりして、エコと風呂敷というものがうまく結びつきました。
風呂敷は工夫してものを大切に使うという面をもっています。
カバンや紙袋に比べて広い用途で使うことができます。
なにより使ったあとはコンパクトにまとめることができるので場所をとりません。
そういうところがエコロジーの考え方と共感したのでしょう。
しかし風呂敷が日本の伝統文化であり、環境にいいからと言っても、
それだけでは簡単に風呂敷を使ってもらえるものでもありません。
それ以上に、ほんまにかわいいとか、かっこいいと思ってもらえる、
ほんまにこれやったら使いたいと思ってもらえるような風呂敷を提案していかないと。
それで各イベントや講習会では環境にいいんですけど、
そんな理屈じゃなくて風呂敷をこうやって使ったらいいと思いませんか、
というような提案を続けています。
――風呂敷の結び方やつかい方を動画にまとめたDVDをリリースされたそうですね。
 はい。ちょうど「ふろしきレシピ」というDVDをリリースしたばかりです。
はい。ちょうど「ふろしきレシピ」というDVDをリリースしたばかりです。自分で風呂敷を使うひとは問題ないのですが、風呂敷を誰かにプレゼントするとき、その相手は風呂敷の使い方や結び方を知らないかもしれません。そういうとき、風呂敷の使い方から結び方まで映像で案内できるDVDをあわせてプレゼントしてあげるといいかなと思いました。
風呂敷に特化して考えていると、いろいろアイデアが湧いてきます。和文化というと大層ですが、風呂敷が現代の生活のなかで生きているものにし続けたいですね。それこそが我々の使命であり、仕事であると今は考えています。
■山田繊維株式会社HP
■むす美HP
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】