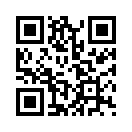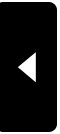2009年03月09日
ものがなく不便な時代に風呂敷はたいへん便利なものでした
第15回 山田繊維株式会社 代表取締役 山田芳生 vol.1

京朋株式会社の室木社長から、たいへんおしゃれでスマートな方と
紹介をいただいた山田繊維の山田社長です。
山田繊維株式会社は風呂敷を中心した和雑貨の製造メーカーです。
原宿に出店したアンテナショップ「むす美」が各メディアで取り上げられるなど、
“ふろしき”の新しい使い方を提案しています。
――創業は戦前の昭和12年ということですが、当時から風呂敷を中心に扱われていたのですか?
私の祖父が創業した当時は風呂敷や綿の反物など、綿素材のものを中心に扱っていました。
祖父は岐阜の農家の次男だったのですが、商売が好きだったので京都に丁稚として出てきて、
それからのれんわけをして独立しました。
ところが、それからすぐに戦争が始まったので、岐阜の田舎へ疎開することになります。
疎開先ではパンや文房具など、とにかく商売になるものであればなんでも売っていました。
というより商売をすること自体難しい時代だったのでしょう。
いろいろ役にたてることがあればということで、なんでも屋みたいな感じだったようです。
戦争が終わり、また京都で商売をしたいということで昭和20何年かに京都に戻り再スタートを切り、
昭和34年に山田繊維という会社組織を立ち上げることとなりました。
そのとき祖父は丁稚奉公に出していた私の父を家に戻し、
従業員をあわせて5~6名の会社でした。
そのときの取扱い商品は100%風呂敷でした。
――前回、室木社長に呉服は70年代に売上のピークを迎えたとうかがったのですが、風呂敷も同じような状況だったのですか?
いえ。会社の創業当時の方が風呂敷は売れていました。正確なデータはないのですが、
風呂敷は戦後まもなく売上のピークを迎えていたのではないでしょうか。
もしかすると戦前の方が売れていたかも知れません。
今、風呂敷を買おうと思ったら、百貨店の呉服売り場などを思い浮かべますよね。
ところが祖父が創業した当時、風呂敷は鍋や釜、軍手などと一緒に
日用雑貨品として売られていました。
もちろん当時も婚礼やセレモニーではシルクなどの高級素材をつかった風呂敷が
使われていたのですが、一般的に風呂敷といえば日用雑貨品でした。
ものがなく不便な時代には、なんでも包むことができ、手に提げたり、
大きな荷物になるとそのまま背中に背負うことができる風呂敷はたいへん便利なものでした。
ところが戦後、社会的なインフラが整備されると、
わざわざ自分で荷物を提げて持っていくようなことがだんだん少なくなりました。
何を運ぶにも自家用車に積み込むようになり、カバンもどんどん便利になってきます。
教科書や弁当を風呂敷に包んでいた時代と比べると、
風呂敷の流通が極端に減ったのは容易に想像ができますよね。
誰もが使うような日用雑貨品ではなくなったのです。
■山田繊維株式会社HP
■むす美HP
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】

京朋株式会社の室木社長から、たいへんおしゃれでスマートな方と
紹介をいただいた山田繊維の山田社長です。
山田繊維株式会社は風呂敷を中心した和雑貨の製造メーカーです。
原宿に出店したアンテナショップ「むす美」が各メディアで取り上げられるなど、
“ふろしき”の新しい使い方を提案しています。
――創業は戦前の昭和12年ということですが、当時から風呂敷を中心に扱われていたのですか?
私の祖父が創業した当時は風呂敷や綿の反物など、綿素材のものを中心に扱っていました。
祖父は岐阜の農家の次男だったのですが、商売が好きだったので京都に丁稚として出てきて、
それからのれんわけをして独立しました。
ところが、それからすぐに戦争が始まったので、岐阜の田舎へ疎開することになります。
疎開先ではパンや文房具など、とにかく商売になるものであればなんでも売っていました。
というより商売をすること自体難しい時代だったのでしょう。
いろいろ役にたてることがあればということで、なんでも屋みたいな感じだったようです。
戦争が終わり、また京都で商売をしたいということで昭和20何年かに京都に戻り再スタートを切り、
昭和34年に山田繊維という会社組織を立ち上げることとなりました。
そのとき祖父は丁稚奉公に出していた私の父を家に戻し、
従業員をあわせて5~6名の会社でした。
そのときの取扱い商品は100%風呂敷でした。
――前回、室木社長に呉服は70年代に売上のピークを迎えたとうかがったのですが、風呂敷も同じような状況だったのですか?
いえ。会社の創業当時の方が風呂敷は売れていました。正確なデータはないのですが、
風呂敷は戦後まもなく売上のピークを迎えていたのではないでしょうか。
もしかすると戦前の方が売れていたかも知れません。
今、風呂敷を買おうと思ったら、百貨店の呉服売り場などを思い浮かべますよね。
ところが祖父が創業した当時、風呂敷は鍋や釜、軍手などと一緒に
日用雑貨品として売られていました。
もちろん当時も婚礼やセレモニーではシルクなどの高級素材をつかった風呂敷が
使われていたのですが、一般的に風呂敷といえば日用雑貨品でした。
ものがなく不便な時代には、なんでも包むことができ、手に提げたり、
大きな荷物になるとそのまま背中に背負うことができる風呂敷はたいへん便利なものでした。
ところが戦後、社会的なインフラが整備されると、
わざわざ自分で荷物を提げて持っていくようなことがだんだん少なくなりました。
何を運ぶにも自家用車に積み込むようになり、カバンもどんどん便利になってきます。
教科書や弁当を風呂敷に包んでいた時代と比べると、
風呂敷の流通が極端に減ったのは容易に想像ができますよね。
誰もが使うような日用雑貨品ではなくなったのです。
■山田繊維株式会社HP
■むす美HP
■山田繊維株式会社 山田芳生 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年01月23日
何気ないところに滲み出ているものこそが本当の京都らしい。
第14回 京朋株式会社 代表取締役 室木英人 vol.3

――京都の文化についてどう思われますか?
父は東京生まれだったため、私は京都生まれの京都育ちにも関わらず、
会社に入るまではずっと関東弁を話していました。家のなかでは標準語だったのですよ。
父は生粋の江戸っ子で、そういう家庭に育った影響もあったのでしょうか、
私は「一見さんお断り」、「ぶぶ漬けでもどうですか?(早く帰って欲しい)」に代表される
京都の文化がとても苦手でした。
ところが、京都に残り会社を継ぎ、ビジネスというより商売(あきない)に携わるようになり、
昔から京都に居られる方たちと深くお付き合いするようになって、
その文化の意味するところがよく理解できるようになりました。
「一見(いちげん)さんお断り」は決して排除の論理ではなく、
その店の雰囲気や馴染みのお客様を守るためにできたものなのです。
例えば、一見(いちげん)の人が店で騒いだりすると、馴染みのお客さんが迷惑するし、
お店の雰囲気が悪くなって評判がさがります。
「ぶぶ漬けでもどうですか?」も直接的に物事を伝えることは無粋であり、
間接的にものごとを伝えて、それを理解することで
相手との距離がより密接になるということが背景にあり、
一概に否定するべきものではないと、今は考えています。
そうした京都の文化を育んだ京都の自然や寺社仏閣も含めた町並みは、
世界に誇るべきもので、今後、日本の人口が減少するなかで、
世界に打って出られる数少ないコンテンツのひとつだと思います。
だからこそ、もっと戦略的に京都の良さを打ち出していく必要がありますし、
そのとき、着物を有効な観光資源として、
大きな武器になるので今まで以上にアピールしていく必要があると思います。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を室木社長が案内する場合、どこに案内しますか?
実は清水寺に行ったのも20歳を過ぎてからで、
金閣寺も行ったことがあるかないかはっきり覚えていないくらいなのですよ。
京都の華々しい観光地はどちらかといえば、少し苦手で・・・。
私は育ちが嵯峨嵐山方面なので、もちろん桜や紅葉の時期の嵐山もいいのですが、
それ以外のシーズンの嵐山や、昔住んでいた大覚寺の近くがすごく落ち着いていて好きですね。
大覚寺の近くの広沢池と大沢池、民家が並ぶ小道や田んぼのあぜ道を歩くと、
ちいさなお地蔵さんがあったりして、なにげないところなのですが、
京都の良い意味でゆったりとした空気を感じることができます。
観光地らしい観光地よりは、
何気ないところに滲み出ているものこそが本当の京都らしいところだと思います。
あとは、もちろん弊社のアンテナショップ「コエトイロ -coetoiro-」ですね(笑)。
――それでは、次ぎに紹介していただく山田社長はどんな方ですか?
風呂敷や和雑貨を専門に扱っておられる会社の代表なのですが、
たいへん知的な方で個人的にも尊敬しています。
弊社のアンテナショップは山田社長が原宿で出店したお店もヒントになっています。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年12月18日取材)
■大覚寺HP
*********************************
 京朋株式会社
京朋株式会社
京都市中京区六角通室町西入
代表取締役 室木英人
電話:(075)222-1211
FAX:(075)221-3350
HP:http://www.kimono-kyoho.co.jp/
「コエトイロ -coetoiro-」HP:http://coetoiro.jp/
■京朋株式会社 室木英人 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――京都の文化についてどう思われますか?
父は東京生まれだったため、私は京都生まれの京都育ちにも関わらず、
会社に入るまではずっと関東弁を話していました。家のなかでは標準語だったのですよ。
父は生粋の江戸っ子で、そういう家庭に育った影響もあったのでしょうか、
私は「一見さんお断り」、「ぶぶ漬けでもどうですか?(早く帰って欲しい)」に代表される
京都の文化がとても苦手でした。
ところが、京都に残り会社を継ぎ、ビジネスというより商売(あきない)に携わるようになり、
昔から京都に居られる方たちと深くお付き合いするようになって、
その文化の意味するところがよく理解できるようになりました。
「一見(いちげん)さんお断り」は決して排除の論理ではなく、
その店の雰囲気や馴染みのお客様を守るためにできたものなのです。
例えば、一見(いちげん)の人が店で騒いだりすると、馴染みのお客さんが迷惑するし、
お店の雰囲気が悪くなって評判がさがります。
「ぶぶ漬けでもどうですか?」も直接的に物事を伝えることは無粋であり、
間接的にものごとを伝えて、それを理解することで
相手との距離がより密接になるということが背景にあり、
一概に否定するべきものではないと、今は考えています。
そうした京都の文化を育んだ京都の自然や寺社仏閣も含めた町並みは、
世界に誇るべきもので、今後、日本の人口が減少するなかで、
世界に打って出られる数少ないコンテンツのひとつだと思います。
だからこそ、もっと戦略的に京都の良さを打ち出していく必要がありますし、
そのとき、着物を有効な観光資源として、
大きな武器になるので今まで以上にアピールしていく必要があると思います。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を室木社長が案内する場合、どこに案内しますか?
実は清水寺に行ったのも20歳を過ぎてからで、
金閣寺も行ったことがあるかないかはっきり覚えていないくらいなのですよ。
京都の華々しい観光地はどちらかといえば、少し苦手で・・・。
私は育ちが嵯峨嵐山方面なので、もちろん桜や紅葉の時期の嵐山もいいのですが、
それ以外のシーズンの嵐山や、昔住んでいた大覚寺の近くがすごく落ち着いていて好きですね。
大覚寺の近くの広沢池と大沢池、民家が並ぶ小道や田んぼのあぜ道を歩くと、
ちいさなお地蔵さんがあったりして、なにげないところなのですが、
京都の良い意味でゆったりとした空気を感じることができます。
観光地らしい観光地よりは、
何気ないところに滲み出ているものこそが本当の京都らしいところだと思います。
あとは、もちろん弊社のアンテナショップ「コエトイロ -coetoiro-」ですね(笑)。
――それでは、次ぎに紹介していただく山田社長はどんな方ですか?
風呂敷や和雑貨を専門に扱っておられる会社の代表なのですが、
たいへん知的な方で個人的にも尊敬しています。
弊社のアンテナショップは山田社長が原宿で出店したお店もヒントになっています。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年12月18日取材)
■大覚寺HP
*********************************
京都市中京区六角通室町西入
代表取締役 室木英人
電話:(075)222-1211
FAX:(075)221-3350
HP:http://www.kimono-kyoho.co.jp/
「コエトイロ -coetoiro-」HP:http://coetoiro.jp/
■京朋株式会社 室木英人 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年01月22日
着物を着ること自体に価値を作っていきたい。
第14回 京朋株式会社 代表取締役 室木英人 vol.2
――「コエトイロ -coetoiro-」は室木社長の発案とうかがったのですが?
 はい。マーケットリサーチと商品開発を考えて出店しました。
はい。マーケットリサーチと商品開発を考えて出店しました。
そもそも入社したときからずっとアンテナショップについては考えていました。ただ、店のコンセプト・マーチャンダイジング・店舗の設計から接客に到るまで、実際の運営は当社の30歳前後の女性スタッフたちに全て任せています。
着物業界は和装離れもあり、かなり厳しい状態です。振袖でトップシェアを誇るといっても、規模がかなり縮小しています。
今の産業とお客さまのニーズが噛みあっていないところがあるので、小売で得たノウハウを商品開発に活かして、既存のお客様との取引の活性化に繋げたいと考えています。
少し前にアンティーク着物がはやったのですが、新作の着物市場にはまったく影響がありませんでした。アンティーク着物に興味を持ったひとが、どうして新作の着物に興味を持ってくれないのか?
「着物が好き?嫌い?」と訊けばたいていの方が「好き」と答え、
「着物を着たい?着たくない?」と訊くとほとんどのひとが「着たい」と答えます。
ところが「実際に着物を着ていますか?」と訊ねるとほとんどの方が着ていません。
そこには値段が高いとか、着付けができない、
着物を着ていくシーンがないとか様々な問題があります。
成人式、結婚式に以外に着物を着る機会を増やすなど、
着物を着るシーンを作ることも、もちろんなのですが、
着物を着ること自体に価値を作っていきたいと思っています。
例えば、着物を着ていくシーンだから着物を着るのではなく、
着物を着ていくことにより、そこにシーンが生まれるような価値を提案したいですね。

――室木社長は27歳とたいへんお若いのですが、ご経歴を教えてください。
元々、次男だったので会社を継ぐことは一切、頭にありませんでした。
私は恥ずかしながら高校を中退した後に大検をとって、立命館大学に入学したのですが、
就職活動も普通に行い、東京の会社に務める予定でした。
ところが父の健康問題や兄から私へ後継者のバトンタッチが急にきまった為、
内定先に謝って、2006年4月に新卒で京朋に入社しました。
入社した年に父の癌が再発したために、2007年夏に専務になり、
その年末に社長交代を行う予定だったのですが、
間に合わず父は年末になくなり、2007年の12月に社長に就任しました。
着物業界にすすむつもりは、大学を卒業するまでまったくなかったので、
まだまだ勉強が必要です。素材にしろ、染色過程の工程にしろ、
何百パターンもあって、組み合わせは無数になります。着物は奥が深いですね。
当然、自分が着物に携わるようになって着物を着る機会が増えました。
着物を着ると背筋が伸び、言葉遣いがかわります。
強く意識しなくても、自然にそう変わるところがすごく好きですし、
着物には日本人のDNAに訴えかけるものがあると思いますね。
――京朋の社名は「京都の友禅を愛する多くの朋友とともに」という由来があるのだそうですね。
はい。社名には創業者の思いがこもっています。
現在でも「京朋は、京都が誇る染色技術を守り育てながら、誠実で優れた意匠の着物をつくり、
関わりあうすべての人に感動や満足を提供できる企業を目指します。」
というミッションをすべての活動の根底においています。
リッツ・カールトンホテルのクレドカードにヒントを得た
京朋ベーシック「京朋社員9つの約束」という行動指針を常に持ち歩き、
毎朝その中の項目についてひとりずつスピーチをしています。
私の言葉でいいかえると、
今の忙しい時代だからこそ感じることができる着物を着る喜び、楽しみ、充実感を
ひとりでも多くのお客様に提供することが、これからの我々の最大のミッションだと考えています。
また方針については、よくプロダクトアウトかマーケットインかという議論がありますが、
マーケットインだけではメーカーとして開発能力が伸びませんし、
プロダクトアウトだけであっても、それは自己満足にしかすぎません。
マーケットを意識し、受け入れられる素養のある商品を開発した上で、
新しいマーケットを作り出す、マーケットメイクを目指し、
できるだけ魅力のある商品をプロダクトアウトの形で作っていきたいと考えています。
 「コエトイロ -coetoiro-」
「コエトイロ -coetoiro-」
http://coetoiro.jp/
京都市中京区新京極通四条上る
中之町577-21 柳小路
営業時間:11:00~19:00
月曜定休(祝日の場合は翌日)
TEL:075-241-4433
■コエトイロBLOG
■京朋株式会社HP
■京朋株式会社 室木英人 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――「コエトイロ -coetoiro-」は室木社長の発案とうかがったのですが?
そもそも入社したときからずっとアンテナショップについては考えていました。ただ、店のコンセプト・マーチャンダイジング・店舗の設計から接客に到るまで、実際の運営は当社の30歳前後の女性スタッフたちに全て任せています。
着物業界は和装離れもあり、かなり厳しい状態です。振袖でトップシェアを誇るといっても、規模がかなり縮小しています。
今の産業とお客さまのニーズが噛みあっていないところがあるので、小売で得たノウハウを商品開発に活かして、既存のお客様との取引の活性化に繋げたいと考えています。
少し前にアンティーク着物がはやったのですが、新作の着物市場にはまったく影響がありませんでした。アンティーク着物に興味を持ったひとが、どうして新作の着物に興味を持ってくれないのか?
「着物が好き?嫌い?」と訊けばたいていの方が「好き」と答え、
「着物を着たい?着たくない?」と訊くとほとんどのひとが「着たい」と答えます。
ところが「実際に着物を着ていますか?」と訊ねるとほとんどの方が着ていません。
そこには値段が高いとか、着付けができない、
着物を着ていくシーンがないとか様々な問題があります。
成人式、結婚式に以外に着物を着る機会を増やすなど、
着物を着るシーンを作ることも、もちろんなのですが、
着物を着ること自体に価値を作っていきたいと思っています。
例えば、着物を着ていくシーンだから着物を着るのではなく、
着物を着ていくことにより、そこにシーンが生まれるような価値を提案したいですね。
――室木社長は27歳とたいへんお若いのですが、ご経歴を教えてください。
元々、次男だったので会社を継ぐことは一切、頭にありませんでした。
私は恥ずかしながら高校を中退した後に大検をとって、立命館大学に入学したのですが、
就職活動も普通に行い、東京の会社に務める予定でした。
ところが父の健康問題や兄から私へ後継者のバトンタッチが急にきまった為、
内定先に謝って、2006年4月に新卒で京朋に入社しました。
入社した年に父の癌が再発したために、2007年夏に専務になり、
その年末に社長交代を行う予定だったのですが、
間に合わず父は年末になくなり、2007年の12月に社長に就任しました。
着物業界にすすむつもりは、大学を卒業するまでまったくなかったので、
まだまだ勉強が必要です。素材にしろ、染色過程の工程にしろ、
何百パターンもあって、組み合わせは無数になります。着物は奥が深いですね。
当然、自分が着物に携わるようになって着物を着る機会が増えました。
着物を着ると背筋が伸び、言葉遣いがかわります。
強く意識しなくても、自然にそう変わるところがすごく好きですし、
着物には日本人のDNAに訴えかけるものがあると思いますね。
――京朋の社名は「京都の友禅を愛する多くの朋友とともに」という由来があるのだそうですね。
はい。社名には創業者の思いがこもっています。
現在でも「京朋は、京都が誇る染色技術を守り育てながら、誠実で優れた意匠の着物をつくり、
関わりあうすべての人に感動や満足を提供できる企業を目指します。」
というミッションをすべての活動の根底においています。
リッツ・カールトンホテルのクレドカードにヒントを得た
京朋ベーシック「京朋社員9つの約束」という行動指針を常に持ち歩き、
毎朝その中の項目についてひとりずつスピーチをしています。
私の言葉でいいかえると、
今の忙しい時代だからこそ感じることができる着物を着る喜び、楽しみ、充実感を
ひとりでも多くのお客様に提供することが、これからの我々の最大のミッションだと考えています。
また方針については、よくプロダクトアウトかマーケットインかという議論がありますが、
マーケットインだけではメーカーとして開発能力が伸びませんし、
プロダクトアウトだけであっても、それは自己満足にしかすぎません。
マーケットを意識し、受け入れられる素養のある商品を開発した上で、
新しいマーケットを作り出す、マーケットメイクを目指し、
できるだけ魅力のある商品をプロダクトアウトの形で作っていきたいと考えています。
http://coetoiro.jp/
京都市中京区新京極通四条上る
中之町577-21 柳小路
営業時間:11:00~19:00
月曜定休(祝日の場合は翌日)
TEL:075-241-4433
■コエトイロBLOG
■京朋株式会社HP
■京朋株式会社 室木英人 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年01月21日
素材や染色作家さんをコーディネート、プロデュースします。
第14回 京朋株式会社 代表取締役 室木英人 vol.1

株式会社三才の斉藤専務から、着物の加工元卸業の最大手の会社に紆余曲折を経て
社長に就任された27歳の若き社長です、と紹介をいただいた京朋の室木社長です。
京朋株式会社は振袖では着物業界でもトップのシェアを誇り、
昨今は特に若い世代(20代後半~30代)の女性をターゲットにした
商品開発に力を注いでいます。
――創業は昭和30年ということですが、呉服、着物メーカーとしては比較的新しい会社なのですね。
はい。私の祖父であり、現相談役の大江茂が1955年に起こした会社です。
100年以上の歴史がある老舗が多い着物業界では、創業53年の歴史は新しい会社といえます。
創業当時、呉服は給料の何倍もするようなたいへん高価な商品でした。
祖父はもっとたくさんの女性に着物を着てもらいたいとの思いから、
大衆商品化を目指し、商品開発に全力を注いだ結果、
付下という大ヒット商品を世に送りだすことができました。
戦後の高度成長期とも重なり、ちょうど団塊の世代が成人し、
結婚する1970年前後にピークを迎えました。
当時は嫁入りのときに和ダンス一式といわれていた時代で、
その流れにもうまく乗って会社は急成長を遂げました。
その後も着物業界でキャラクターブランド商品の先駆けとなった「秋山庄太郎のきもの」などを
次々と発表し、業界に一大センセーションを巻き起こすなど、
祖父は積極的に事業展開を行いました。
――前回の株式会社三才の斉藤専務は着物デザイナーということでしたが、京朋は着物メーカーになるのですね?
はい。弊社は製造卸しの会社です。
メーカーとはいいますが、弊社が工場を持っているわけではありません。
着物を作るためにはまず、丹後地方や長浜の方で織られた白生地を扱う問屋さんから
生地を買い付けます。
着物は、紬などの先に糸を染めているものもありますが、
うちの場合は真っ白な状態の生地を買ってきます。
市内の染色工場で柄などを指示して染めてもらいます。
そうして染められた生地が加工されて製品になります。素材や染工場、染色作家さんには、
それぞれ特色があるので、そのカラーをうまく組み合わせて、どう引き出すかが我々の役目です。
要はコーディネーター、プロデュースする立場ですね。
製品は問屋を通して、小売店に並び、消費者の手に届くようになります。
現在は着物の流通も過渡期で流通形態が徐々に変化してきています。
着物のデザインについても、これまでは作家とよばれる着物デザイナーは社外に居たのですが、
弊社では社内にデザイン部署を作り、社内デザイナーによる商品の開発にも取り組んでいます。
2008年10月には四条河原町近くに「コエトイロ -coetoiro-」という
アンテナショップも出店しました。
■京朋株式会社HP
■「コエトイロ -coetoiro-」HP
■京朋株式会社 室木英人 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社三才の斉藤専務から、着物の加工元卸業の最大手の会社に紆余曲折を経て
社長に就任された27歳の若き社長です、と紹介をいただいた京朋の室木社長です。
京朋株式会社は振袖では着物業界でもトップのシェアを誇り、
昨今は特に若い世代(20代後半~30代)の女性をターゲットにした
商品開発に力を注いでいます。
――創業は昭和30年ということですが、呉服、着物メーカーとしては比較的新しい会社なのですね。
はい。私の祖父であり、現相談役の大江茂が1955年に起こした会社です。
100年以上の歴史がある老舗が多い着物業界では、創業53年の歴史は新しい会社といえます。
創業当時、呉服は給料の何倍もするようなたいへん高価な商品でした。
祖父はもっとたくさんの女性に着物を着てもらいたいとの思いから、
大衆商品化を目指し、商品開発に全力を注いだ結果、
付下という大ヒット商品を世に送りだすことができました。
戦後の高度成長期とも重なり、ちょうど団塊の世代が成人し、
結婚する1970年前後にピークを迎えました。
当時は嫁入りのときに和ダンス一式といわれていた時代で、
その流れにもうまく乗って会社は急成長を遂げました。
その後も着物業界でキャラクターブランド商品の先駆けとなった「秋山庄太郎のきもの」などを
次々と発表し、業界に一大センセーションを巻き起こすなど、
祖父は積極的に事業展開を行いました。
――前回の株式会社三才の斉藤専務は着物デザイナーということでしたが、京朋は着物メーカーになるのですね?
はい。弊社は製造卸しの会社です。
メーカーとはいいますが、弊社が工場を持っているわけではありません。
着物を作るためにはまず、丹後地方や長浜の方で織られた白生地を扱う問屋さんから
生地を買い付けます。
着物は、紬などの先に糸を染めているものもありますが、
うちの場合は真っ白な状態の生地を買ってきます。
市内の染色工場で柄などを指示して染めてもらいます。
そうして染められた生地が加工されて製品になります。素材や染工場、染色作家さんには、
それぞれ特色があるので、そのカラーをうまく組み合わせて、どう引き出すかが我々の役目です。
要はコーディネーター、プロデュースする立場ですね。
製品は問屋を通して、小売店に並び、消費者の手に届くようになります。
現在は着物の流通も過渡期で流通形態が徐々に変化してきています。
着物のデザインについても、これまでは作家とよばれる着物デザイナーは社外に居たのですが、
弊社では社内にデザイン部署を作り、社内デザイナーによる商品の開発にも取り組んでいます。
2008年10月には四条河原町近くに「コエトイロ -coetoiro-」という
アンテナショップも出店しました。
■京朋株式会社HP
■「コエトイロ -coetoiro-」HP
■京朋株式会社 室木英人 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2009年01月12日
縁と感性のまち「京都」で今年もつなげます
新年明けましておめでとうございます。
気がつけば2009年。早いものです。
ちょうど1年前、京都青年会議所メンバー中心に
京都の社長をブログで紹介しませんかという
企画提案をいただき、何度か詰めた結果、
このブログが立ち上がりました。
数珠紐は最初の投稿のみで、
全て担当の方が取材、編集をしていただきました。
ありがとうございました。
このブログを振り返ると・・・・
内容の濃さと会社への思いの重さを改めて
実感しました。
個人的なことでは、登場していただいたほとんどが
私が京都青年会議所に入会した頃には
中心メンバーとしてご活躍されていた方たちで
実際にお目にかかると背筋がピンと伸びて
緊張してしまうような顔ぶれです。
そんな中、やはり面白いのは人のつながりです。
12月の斉藤上太郎さんは昨年京都青年会議所で同じ
委員会でご一緒させていただきました。
また、京都青年会議所関係者ではない方でも
高校の野球部の大先輩の息子さん
(といっても私よりはるかに先輩ですが)の登場など
何らかの繋がりがあることに縁を感じてしまいました。
もちろん、多くの先輩にも京都青年会議所に在籍
されている時、またご卒業されてからも大変
お世話になっている方もおられます。
ご登場していただいた皆様にはこのブログに
ご協力していただき本当にありがとうございました。
そんな人の繋がりの側面だけでなく、学ばせて
いただいたこともあります。それは登場していただいた
多くの会社が老舗、あるいはご商売に歴史ありといった
ところが多く、京都のビジネスの特色の一部を見ることが
できたのではないかと思ってます。
巷では「100年に1度の経済危機」といわれてますが、
交換手段としての貨幣が価値そのものとして崇拝された
そんな価値観の終焉の象徴だと個人的に思ってます。
企業の目的は成功ではなく、持続だと思います。
企業という組織の持続はそこに集まる全ての人の
幸福があって初めて成り立つもの。
その結果として、利益が生み出されると思います。
京都の企業には関わっている人々の幸福を願った
ビジネスがあるからこそ持続してきたのではないかと
思うのです。
まさに人の繋がり、ご縁と共感を生む感性が
クローズアップされるものだと思います。
そういう意味でもこの京の社長の数珠つなぎは
京都ビジネス、京都モデルを検証する意義のある
ブログになっていくような気がします。
今年もそんな意義を感じつつ「京の社長」つないで
いきたいと思います。
あ、つなげているのは僕じゃなく、「京の社長」さんです。
僕はあくまでも・・・・・数珠紐です。
素敵な出会いとご縁を楽しみにしてます!
気がつけば2009年。早いものです。
ちょうど1年前、京都青年会議所メンバー中心に
京都の社長をブログで紹介しませんかという
企画提案をいただき、何度か詰めた結果、
このブログが立ち上がりました。
数珠紐は最初の投稿のみで、
全て担当の方が取材、編集をしていただきました。
ありがとうございました。
このブログを振り返ると・・・・
内容の濃さと会社への思いの重さを改めて
実感しました。
個人的なことでは、登場していただいたほとんどが
私が京都青年会議所に入会した頃には
中心メンバーとしてご活躍されていた方たちで
実際にお目にかかると背筋がピンと伸びて
緊張してしまうような顔ぶれです。
そんな中、やはり面白いのは人のつながりです。
12月の斉藤上太郎さんは昨年京都青年会議所で同じ
委員会でご一緒させていただきました。
また、京都青年会議所関係者ではない方でも
高校の野球部の大先輩の息子さん
(といっても私よりはるかに先輩ですが)の登場など
何らかの繋がりがあることに縁を感じてしまいました。
もちろん、多くの先輩にも京都青年会議所に在籍
されている時、またご卒業されてからも大変
お世話になっている方もおられます。
ご登場していただいた皆様にはこのブログに
ご協力していただき本当にありがとうございました。
そんな人の繋がりの側面だけでなく、学ばせて
いただいたこともあります。それは登場していただいた
多くの会社が老舗、あるいはご商売に歴史ありといった
ところが多く、京都のビジネスの特色の一部を見ることが
できたのではないかと思ってます。
巷では「100年に1度の経済危機」といわれてますが、
交換手段としての貨幣が価値そのものとして崇拝された
そんな価値観の終焉の象徴だと個人的に思ってます。
企業の目的は成功ではなく、持続だと思います。
企業という組織の持続はそこに集まる全ての人の
幸福があって初めて成り立つもの。
その結果として、利益が生み出されると思います。
京都の企業には関わっている人々の幸福を願った
ビジネスがあるからこそ持続してきたのではないかと
思うのです。
まさに人の繋がり、ご縁と共感を生む感性が
クローズアップされるものだと思います。
そういう意味でもこの京の社長の数珠つなぎは
京都ビジネス、京都モデルを検証する意義のある
ブログになっていくような気がします。
今年もそんな意義を感じつつ「京の社長」つないで
いきたいと思います。
あ、つなげているのは僕じゃなく、「京の社長」さんです。
僕はあくまでも・・・・・数珠紐です。
素敵な出会いとご縁を楽しみにしてます!
2008年12月15日
「和のスタイル」が中心にあります。
第13回 株式会社三才 専務取締役 斉藤上太郎 vol.3
――今後も着物以外のデザインに挑戦するほか、どのようなビジネスを展開していきたいとお考えですか?
 ほかのことに挑戦すれば挑戦するほど、京都ブランドの価値をありがたいと思いますし、着物をやっていてよかったと思いますね。
ほかのことに挑戦すれば挑戦するほど、京都ブランドの価値をありがたいと思いますし、着物をやっていてよかったと思いますね。
最近は着物雑誌より建築雑誌に声をかけてもらい取材されることが多くて、「いろんなことやっていますね」と言われるけれど、結局、「和のスタイル」が中心にあって、たくさんある枝葉の中から、これならプラスになる、これならやっていけると思ったことだけやっています。
「和のスタイル」に拘って掘り下げるときに基本が大事になりますよね。間違えてほりさげてしまうとチープになってしまいます。モダンジャポニズムを新しければよいという風に履き違えると難しいですね。
やっぱり着物は絹であるべきだと思います。ポリではどうしても安っぽくなります。しわをのばす為に、前の晩から衣文掛けや、ハンガーにかけるなど、手間をかけることも大切です。手間のかかる仕種も着物を着る楽しみのひとつですし、そういう手間を、着物を着るストーリーとして楽しめるようなマニアの方を増やしていきたいですね。
私どもは京都で活動し、生産しているので、他所の着物や、海外はもとより国内のほかの産地にも値段では勝負になりません。でも京都だからこそ勝てるポイントやアピールできるポイントもあって、そこを大切にしていきたいですね。私はチープじゃないものを提案したいと考えていますし、実際安い着物ではなく、ステキな着物が欲しいというお客さまが私のところへ来てくれています。
私はやっぱり自分の会社らしいことしかしていません。斉藤さんのとこならではとか、三才さんとこならやりそうやなあ、ということしかやっていません。逆に他所でもやれることをやろうとは思いませんし、これからも弊社にしかできないことをやっていきたいですね。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を斉藤専務が案内する場合、どこに案内しますか?
誰を案内するかによりますよね、男性なのか、女性なのかでかわりますよね(笑)。
そのなかでひとつといえば、黒谷さん、金戒光明寺からずっと歩いて、
真如堂へ抜けてという散歩道ですね。
いわゆる京都の観光コースではなく、生活と密着したエリアです。
立派な観光案内や解説はできないのですが、ずっとあの辺で育ったので、
ここに亀がいっぱいいて、この砂場でアリジゴクを掘ったことがあるとか、
自分のエピソードがたくさんあります。
そういうエピソードを話しながら、自分のルーツを辿る旅みたいな感じで案内したいですね。
――それでは、次ぎに紹介していただく室木社長はどんな方ですか?
きものの加工元卸業の最大手の会社に紆余曲折を経て社長に就任された27歳の若き社長です。
業界に旋風を起こした伝説的なカリスマ創業者・大江茂様(現相談役)のお孫さんにあたります。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年11月18日取材)
■金戒光明寺HP
■真如堂HP
*********************************
 株式会社三才
株式会社三才
京都市北区出雲路俵町43
専務取締役 斉藤上太郎
電話:(075)256-2011
FAX:(075)256-2013
HP:http://www.san-sai.com/(株式会社三才)
http://www.jotaro.net/(斉藤上太郎)
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――今後も着物以外のデザインに挑戦するほか、どのようなビジネスを展開していきたいとお考えですか?
最近は着物雑誌より建築雑誌に声をかけてもらい取材されることが多くて、「いろんなことやっていますね」と言われるけれど、結局、「和のスタイル」が中心にあって、たくさんある枝葉の中から、これならプラスになる、これならやっていけると思ったことだけやっています。
「和のスタイル」に拘って掘り下げるときに基本が大事になりますよね。間違えてほりさげてしまうとチープになってしまいます。モダンジャポニズムを新しければよいという風に履き違えると難しいですね。
やっぱり着物は絹であるべきだと思います。ポリではどうしても安っぽくなります。しわをのばす為に、前の晩から衣文掛けや、ハンガーにかけるなど、手間をかけることも大切です。手間のかかる仕種も着物を着る楽しみのひとつですし、そういう手間を、着物を着るストーリーとして楽しめるようなマニアの方を増やしていきたいですね。
私どもは京都で活動し、生産しているので、他所の着物や、海外はもとより国内のほかの産地にも値段では勝負になりません。でも京都だからこそ勝てるポイントやアピールできるポイントもあって、そこを大切にしていきたいですね。私はチープじゃないものを提案したいと考えていますし、実際安い着物ではなく、ステキな着物が欲しいというお客さまが私のところへ来てくれています。
私はやっぱり自分の会社らしいことしかしていません。斉藤さんのとこならではとか、三才さんとこならやりそうやなあ、ということしかやっていません。逆に他所でもやれることをやろうとは思いませんし、これからも弊社にしかできないことをやっていきたいですね。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を斉藤専務が案内する場合、どこに案内しますか?
誰を案内するかによりますよね、男性なのか、女性なのかでかわりますよね(笑)。
そのなかでひとつといえば、黒谷さん、金戒光明寺からずっと歩いて、
真如堂へ抜けてという散歩道ですね。
いわゆる京都の観光コースではなく、生活と密着したエリアです。
立派な観光案内や解説はできないのですが、ずっとあの辺で育ったので、
ここに亀がいっぱいいて、この砂場でアリジゴクを掘ったことがあるとか、
自分のエピソードがたくさんあります。
そういうエピソードを話しながら、自分のルーツを辿る旅みたいな感じで案内したいですね。
――それでは、次ぎに紹介していただく室木社長はどんな方ですか?
きものの加工元卸業の最大手の会社に紆余曲折を経て社長に就任された27歳の若き社長です。
業界に旋風を起こした伝説的なカリスマ創業者・大江茂様(現相談役)のお孫さんにあたります。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年11月18日取材)
■金戒光明寺HP
■真如堂HP
*********************************
京都市北区出雲路俵町43
専務取締役 斉藤上太郎
電話:(075)256-2011
FAX:(075)256-2013
HP:http://www.san-sai.com/(株式会社三才)
http://www.jotaro.net/(斉藤上太郎)
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年12月12日
世界のなかで弊社が踊れる踊り場を見つけました。
第13回 株式会社三才 専務取締役 斉藤上太郎 vol.2
――さきほど着姿を重視して着物をデザインしているという話しがあったのですが、他に大切にしていることはありますか?
 昔から「なんで着物を着ないんですか?」といったアンケートをすると、たいがい高いから、着られないから、着る場所がないからという答えが集まるのですが、そうではないと思うのです。
昔から「なんで着物を着ないんですか?」といったアンケートをすると、たいがい高いから、着られないから、着る場所がないからという答えが集まるのですが、そうではないと思うのです。
実際、今の日本の女性は美しくなるために月に十万くらい化粧品にお金をかけている方がたくさんいらっしゃいますし、スタイルがよくみえる何十万もするボディスーツや、足首が細くみえる5万円のパンストがよく売れたりしています。
やっぱりステキな着物を作らないと。「あのひとは洋服もステキやけど和服姿もステキやねぇ、私も和ダンスをあけてみようかな」と思わせたり、生活のリズムのなかで和の心を楽しむようなスタイルを提案していかないといけないと思います。ステキということがなにより説得力があって、そのために何をすべきなのかは常に考えています。
日本に古くから脈々と繋がる文化や技術は世界から非常にリスペクトされています。京都にいるとなかなかわからないのですが、外に出て客観的にみるとこんなにすごいことはなくて、今でも日常的にその国の伝統的な衣装を着る先進国は日本以外に見当たりません。少なくはなっているのですが、現在も着物で生活をされている方が大勢いらっしゃいます。世界の片田舎の島国で、独自の文化ができあがり、それが残っているということは実はすごいことなのです。
 日本の侘びさびや禅スタイルについては昔からジャポニズムとして、尊敬されていました。また近年はゲームやアニメ、コスプレを通じて、また日本マニアが増えてきていますが、それとは別にその文化の奥や背景を知りたい、取り入れたいという強い欲求があって、そのときに京都のほんものに頼みたいと言われることが多いです。
日本の侘びさびや禅スタイルについては昔からジャポニズムとして、尊敬されていました。また近年はゲームやアニメ、コスプレを通じて、また日本マニアが増えてきていますが、それとは別にその文化の奥や背景を知りたい、取り入れたいという強い欲求があって、そのときに京都のほんものに頼みたいと言われることが多いです。
だから私は今の日本っぽいものではなく、これからの新しいジャポニズムを作りたいと思っています。着物はもちろんインテリアもこれまであったものの焼き直しではなく、新しいジャポニズムスタイルの暮らしや、空間を提案していきたいですね。
文化や伝統を継承することはもちろん大切なことですが、それだけではなく今の感覚なり、時代性を取り入れ次の世代の禅スタイルや侘びさび、次ぎの世代につながる新しいジャポニズムスタイルの提案ができるのは京都では私のところだけだという自負はあります。だからそれを追求しようと思うし、それの一番になりたいと思っています。
※写真は「2008 Collection GOTHIC CAMELLIA」より
――「和を楽しむライフスタイルを提案したい」という理念に繋がると思うのですが、着物だけでなく、インテリアなどさまざまなデザインにも手がけられていますね。
インテリアなど、着物以外のことに取り組みはじめて4年目になります。
当時は古いマンションをホテルにリノベーションすることがはやった時期で、
そのホテルのロビーに置くソファに着物を張りたいという依頼がありました。
昔から西陣織を椅子に張ったりとか、
きれいな帯地をつかってランプシェードをつくったりしたらという発想はありました。
ただ、そういう織りや着物は基本的に工芸品なので、
朝から晩まで一日中、電気の明かりにさらされて、
色やけしたり、色がとんでしまうかも知れません。
それに西陣織が帯に向いていても、椅子にしたときに強度はどうなるのかという問題もありました。
最初は「高くつきますし、やれいわれたらやりますけどねえ」という返事しかできなかったのですが、
偶然そういう依頼がぽんぽんとふたつ続いて、本気で取り組んでみる気になりました。
まずはシルクをポリエステルに全部かえるところからはじめました。
糸の素材をかえるだけでも、織る際に静電気が起こって
糸がプチプチきれやすくなるなど、様々な問題が発生しました。
生地の強度についても、最初をどのあたりを基準にすればいいのかわかりませんでした。
ちょうどそのとき高級なイタリアの椅子のメーカーさんから、コラボしないかという話しがあって、
生地の強度についての基準をいただいたのです。
試行錯誤を重ねた結果、一回目に完成した生地にそこそこ強度があり、
クオリティの高いものをつくることができました。
これまでにない特殊な織物を使うことにより、
インテリアの分野にもデザインの幅を広げることが可能になりました。

「SOFA Collaborated with ROCKSTONE」
新しい生地をもとに、直接いろんなところへ販売したいと考えて、
まあ右も左もわからない状態で、ある見本市に出展しました。
開催者もHPをみたら着物しかないですけど、
何を出展されるのですかと問い合わせがあったくらいでした。
でも、見本市に出ることによって、世界の名だたるメーカーと
京都のいちメーカーが同じ立場にたつことができました。
視察だけではやはりわからない部分があって、出展し、横並びになることで、
ここがあかんのやなあとか、他にはない弊社の特徴を確認するなど、
いろいろな意見を頂くことにより、これまでにない見方のも発見がありました。
なにより世界の服飾・テキスタイルのなかで
弊社が踊れる踊り場がちゃんとあると理解できました。
二回目以降はもっとかしこくなって、狙いを定めて出展することにより、
お客さまに仕事をいただくようになりました。ずいぶんお金はかかったのですが・・・(笑)。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――さきほど着姿を重視して着物をデザインしているという話しがあったのですが、他に大切にしていることはありますか?
 昔から「なんで着物を着ないんですか?」といったアンケートをすると、たいがい高いから、着られないから、着る場所がないからという答えが集まるのですが、そうではないと思うのです。
昔から「なんで着物を着ないんですか?」といったアンケートをすると、たいがい高いから、着られないから、着る場所がないからという答えが集まるのですが、そうではないと思うのです。実際、今の日本の女性は美しくなるために月に十万くらい化粧品にお金をかけている方がたくさんいらっしゃいますし、スタイルがよくみえる何十万もするボディスーツや、足首が細くみえる5万円のパンストがよく売れたりしています。
やっぱりステキな着物を作らないと。「あのひとは洋服もステキやけど和服姿もステキやねぇ、私も和ダンスをあけてみようかな」と思わせたり、生活のリズムのなかで和の心を楽しむようなスタイルを提案していかないといけないと思います。ステキということがなにより説得力があって、そのために何をすべきなのかは常に考えています。
日本に古くから脈々と繋がる文化や技術は世界から非常にリスペクトされています。京都にいるとなかなかわからないのですが、外に出て客観的にみるとこんなにすごいことはなくて、今でも日常的にその国の伝統的な衣装を着る先進国は日本以外に見当たりません。少なくはなっているのですが、現在も着物で生活をされている方が大勢いらっしゃいます。世界の片田舎の島国で、独自の文化ができあがり、それが残っているということは実はすごいことなのです。
 日本の侘びさびや禅スタイルについては昔からジャポニズムとして、尊敬されていました。また近年はゲームやアニメ、コスプレを通じて、また日本マニアが増えてきていますが、それとは別にその文化の奥や背景を知りたい、取り入れたいという強い欲求があって、そのときに京都のほんものに頼みたいと言われることが多いです。
日本の侘びさびや禅スタイルについては昔からジャポニズムとして、尊敬されていました。また近年はゲームやアニメ、コスプレを通じて、また日本マニアが増えてきていますが、それとは別にその文化の奥や背景を知りたい、取り入れたいという強い欲求があって、そのときに京都のほんものに頼みたいと言われることが多いです。だから私は今の日本っぽいものではなく、これからの新しいジャポニズムを作りたいと思っています。着物はもちろんインテリアもこれまであったものの焼き直しではなく、新しいジャポニズムスタイルの暮らしや、空間を提案していきたいですね。
文化や伝統を継承することはもちろん大切なことですが、それだけではなく今の感覚なり、時代性を取り入れ次の世代の禅スタイルや侘びさび、次ぎの世代につながる新しいジャポニズムスタイルの提案ができるのは京都では私のところだけだという自負はあります。だからそれを追求しようと思うし、それの一番になりたいと思っています。
※写真は「2008 Collection GOTHIC CAMELLIA」より
――「和を楽しむライフスタイルを提案したい」という理念に繋がると思うのですが、着物だけでなく、インテリアなどさまざまなデザインにも手がけられていますね。
インテリアなど、着物以外のことに取り組みはじめて4年目になります。
当時は古いマンションをホテルにリノベーションすることがはやった時期で、
そのホテルのロビーに置くソファに着物を張りたいという依頼がありました。
昔から西陣織を椅子に張ったりとか、
きれいな帯地をつかってランプシェードをつくったりしたらという発想はありました。
ただ、そういう織りや着物は基本的に工芸品なので、
朝から晩まで一日中、電気の明かりにさらされて、
色やけしたり、色がとんでしまうかも知れません。
それに西陣織が帯に向いていても、椅子にしたときに強度はどうなるのかという問題もありました。
最初は「高くつきますし、やれいわれたらやりますけどねえ」という返事しかできなかったのですが、
偶然そういう依頼がぽんぽんとふたつ続いて、本気で取り組んでみる気になりました。
まずはシルクをポリエステルに全部かえるところからはじめました。
糸の素材をかえるだけでも、織る際に静電気が起こって
糸がプチプチきれやすくなるなど、様々な問題が発生しました。
生地の強度についても、最初をどのあたりを基準にすればいいのかわかりませんでした。
ちょうどそのとき高級なイタリアの椅子のメーカーさんから、コラボしないかという話しがあって、
生地の強度についての基準をいただいたのです。
試行錯誤を重ねた結果、一回目に完成した生地にそこそこ強度があり、
クオリティの高いものをつくることができました。
これまでにない特殊な織物を使うことにより、
インテリアの分野にもデザインの幅を広げることが可能になりました。

「SOFA Collaborated with ROCKSTONE」
新しい生地をもとに、直接いろんなところへ販売したいと考えて、
まあ右も左もわからない状態で、ある見本市に出展しました。
開催者もHPをみたら着物しかないですけど、
何を出展されるのですかと問い合わせがあったくらいでした。
でも、見本市に出ることによって、世界の名だたるメーカーと
京都のいちメーカーが同じ立場にたつことができました。
視察だけではやはりわからない部分があって、出展し、横並びになることで、
ここがあかんのやなあとか、他にはない弊社の特徴を確認するなど、
いろいろな意見を頂くことにより、これまでにない見方のも発見がありました。
なにより世界の服飾・テキスタイルのなかで
弊社が踊れる踊り場がちゃんとあると理解できました。
二回目以降はもっとかしこくなって、狙いを定めて出展することにより、
お客さまに仕事をいただくようになりました。ずいぶんお金はかかったのですが・・・(笑)。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年12月11日
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案しています。
第13回 株式会社三才 専務取締役 斉藤上太郎 vol.1

株式会社福永念珠舗の福永荘三社長から、古き良きものを知り大切にしながら、なによりも豊かな感性で新しい着物を作り上げている着物デザイナーです、と紹介をいただいた株式会社三才の斉藤上太郎専務取締役です。株式会社三才は鴨川の出雲路橋の近く、閑静な住宅街にあり、「斉藤三才」「斉藤上太郎」の二大ブランドを主体としたキモノ・和装品のトータルな製造・企画を行っている会社です。
――株式会社三才は斉藤専務の祖父が創業されたそうですね。
はい。私の祖父、先代の三才が染色加工業として昭和8年に創業しました。
着物を染めるいわゆる染屋ですね。戦時中は休業している時期もあったのですが、
戦後の昭和24年に再開して、現在は私の父が三才の名前を継いで、社長に就任しています。
基本的に着物は着物屋さんや染屋さんが作って、
帯は帯屋さんが作ってという風に完全な分業制のため、
着物と帯の組み合わせをトータルで考えてデザインをすることはありませんでした。
結果的になんでもあわせやすい着物や帯が多くなり、同じような柄の着物や帯ばかりでした。
そういったなかで父の三才が着物のデザインをはじめました。
ものづくりの世界では着物に限らずデザインをする作家と、
ものをつくる職人はわかれているのですが、
父は着物をワンピース、帯をベルトとして考え、
こういう柄のワンピースに合うのはこういうベルトという感じで同じ柄でデザインするなど、
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案したはじめての作家でした。
たとえば日本人は小柄で背が低いので、帯で着物を上下にわけるより、
着物と同系や同色、同柄のデザインで一体化させ
すきっとしたスタイルをみせた方がよりおしゃれな着姿になります。
父や弊社の工場はそういう提案をするのが同業の中でも早く、
僕もそういう形でデザインをしています。
――斉藤専務は27歳の若さで作家としてデビューされたのですね。
そうですね。京都造形芸術大学の前身の京都芸短を20歳で卒業して、すぐに三才に入社しました。
でも最初は親父に洋服をやらせてくれ頼み、着物ではなくアパレルをやっていました。
当時はまだバブルの頃で会社にも余裕があったのだと思います。
「やれるものならやってみいや」と言われまして、
アパレルのブランドを立ち上げて、デザインから取引先の開拓まで全部自分でやりました。
最初は高級ブティックに飛び込みで営業もしました。
ほかにも洋服の素材として絹以外の様々なコットンやレーヨン、ポリを触ったのは
よい経験になりました。組成も理解できるようになりました。
着物は工芸品という側面もあるのですが、洋服というのはやはり工業製品であって、
例えば洗濯に耐えられる強度があるのか、というところから着物とは違う問題があるのです。
そういうことも含めて独学でトライしたことは、すごいプラスになっています。
まあ、たいした儲けもあがらなかったのですが、
大きなメーカーさんとも付き合いができたし、自信になりました。
結局、7年ほどアパレルの方で頑張っていたのですが、
27歳のときにそろそろ着物をせえへんかと言われたんですね。
当時、27歳といえばまだまだ作家の前例がない年齢で、
今でこそ30歳前後の作家がいるのですが、10年前といえば、
私の上は40代のなかばくらいの方でした。
着物作家としてデビューするときに、着物業界のさる御方に
「着物と洋服の二束の草鞋を履くことはあいならん」と言われました。
そのときアパレルの方は、次ぎの展開を考えると、直営店を出店したり、
人を増やしたり、本気で続けるのであれば、かなり費用もかかることだったので、
その方に後押しをして頂いたのは渡りに船だと思い完全に着物に切り替えることにしました。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社福永念珠舗の福永荘三社長から、古き良きものを知り大切にしながら、なによりも豊かな感性で新しい着物を作り上げている着物デザイナーです、と紹介をいただいた株式会社三才の斉藤上太郎専務取締役です。株式会社三才は鴨川の出雲路橋の近く、閑静な住宅街にあり、「斉藤三才」「斉藤上太郎」の二大ブランドを主体としたキモノ・和装品のトータルな製造・企画を行っている会社です。
――株式会社三才は斉藤専務の祖父が創業されたそうですね。
はい。私の祖父、先代の三才が染色加工業として昭和8年に創業しました。
着物を染めるいわゆる染屋ですね。戦時中は休業している時期もあったのですが、
戦後の昭和24年に再開して、現在は私の父が三才の名前を継いで、社長に就任しています。
基本的に着物は着物屋さんや染屋さんが作って、
帯は帯屋さんが作ってという風に完全な分業制のため、
着物と帯の組み合わせをトータルで考えてデザインをすることはありませんでした。
結果的になんでもあわせやすい着物や帯が多くなり、同じような柄の着物や帯ばかりでした。
そういったなかで父の三才が着物のデザインをはじめました。
ものづくりの世界では着物に限らずデザインをする作家と、
ものをつくる職人はわかれているのですが、
父は着物をワンピース、帯をベルトとして考え、
こういう柄のワンピースに合うのはこういうベルトという感じで同じ柄でデザインするなど、
着姿を重視した着物をデザイナーの感覚で提案したはじめての作家でした。
たとえば日本人は小柄で背が低いので、帯で着物を上下にわけるより、
着物と同系や同色、同柄のデザインで一体化させ
すきっとしたスタイルをみせた方がよりおしゃれな着姿になります。
父や弊社の工場はそういう提案をするのが同業の中でも早く、
僕もそういう形でデザインをしています。
――斉藤専務は27歳の若さで作家としてデビューされたのですね。
そうですね。京都造形芸術大学の前身の京都芸短を20歳で卒業して、すぐに三才に入社しました。
でも最初は親父に洋服をやらせてくれ頼み、着物ではなくアパレルをやっていました。
当時はまだバブルの頃で会社にも余裕があったのだと思います。
「やれるものならやってみいや」と言われまして、
アパレルのブランドを立ち上げて、デザインから取引先の開拓まで全部自分でやりました。
最初は高級ブティックに飛び込みで営業もしました。
ほかにも洋服の素材として絹以外の様々なコットンやレーヨン、ポリを触ったのは
よい経験になりました。組成も理解できるようになりました。
着物は工芸品という側面もあるのですが、洋服というのはやはり工業製品であって、
例えば洗濯に耐えられる強度があるのか、というところから着物とは違う問題があるのです。
そういうことも含めて独学でトライしたことは、すごいプラスになっています。
まあ、たいした儲けもあがらなかったのですが、
大きなメーカーさんとも付き合いができたし、自信になりました。
結局、7年ほどアパレルの方で頑張っていたのですが、
27歳のときにそろそろ着物をせえへんかと言われたんですね。
当時、27歳といえばまだまだ作家の前例がない年齢で、
今でこそ30歳前後の作家がいるのですが、10年前といえば、
私の上は40代のなかばくらいの方でした。
着物作家としてデビューするときに、着物業界のさる御方に
「着物と洋服の二束の草鞋を履くことはあいならん」と言われました。
そのときアパレルの方は、次ぎの展開を考えると、直営店を出店したり、
人を増やしたり、本気で続けるのであれば、かなり費用もかかることだったので、
その方に後押しをして頂いたのは渡りに船だと思い完全に着物に切り替えることにしました。
■株式会社三才HP
■斉藤上太郎HP
■株式会社三才 斉藤上太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】
2008年11月13日
おもてなしは当たり前のサービスではありません。
第12回 株式会社福永念珠舗 福永荘三社長 vol.3

――社長の経歴にについて教えてください。
七代目の祖母の横で9歳の頃から数珠を作り始めました。
「上手にできたなあ、あんたは跡取りさんやねぇ」
と頭を撫でられ褒めて頂いていたことを覚えています。
祖母がもっている千代紙の貼られた箱の中にはいったほのかに甘い菓子や、
仕事台の横には寒い季節にかじかんだ手を温めるために置いていた
手火鉢の上で焼いたくれたお餅に引き寄せられ、祖母の傍に寄り、
見よう見まねで数珠作りをしていました。
それで、中学時代までにはある程度のことはできていたのですが、
友達と外で遊ぶ方がおもしろくなって数珠を作ることから離れていた時代もありました。
特に高校・大学時代はクロスカントリースキー競技をずっと続けていて、
卒業の折にはスキーショップからサービスマンとして誘われていました。
私としては、選手としての契約ではなくても、選手の育成に関わることができれば、
また雪山に行けると考えていました。
ところがいざ就職という時分になって、同級生たちが希望する会社に入社することの難しさをしり、
数珠を作ってお客様に感謝して頂ける家業のすばらしさに気づきました。
また、八代目の父親から「いままで好きなことをやってきたのだから、
わしのいうとおり丁稚奉公に行ってこい」と言われ、跡継ぎの道を進むことにしました。
父の知り合いの関係で愛知にある仏壇屋に修行にいき、
3年間仏壇の販売と製造をさせて頂きました。
それで、京都に戻って来てから、父の弟子に入り30歳の時に技を認めて頂き専務役に、
また、父の体の都合もあり35歳で社長に就任しました。
――京都の活性化ついてはどのようにお考えですか?
今年も12月に開催される京都検定にも通じるのですが、
京都人が京都のことをよく知るということが大切だと思います。
そして京都を訪れるひとを心からおもてなしすることです。
京都は周囲を山に囲まれた盆地なので、京都に入るには山や峠を越えないと入れませんでした。
「おこしやす」という言葉は山を越えてようこそ来てくれはったという意味があります。
京都を訪れる方が、また京都に来たいという気持ちを持っていただくように、
心からのおもてなしをする。
おもてなしは当たり前のサービスではありません。
ひとりひとりが自信をもって京都のよさを伝えることです。
それだけの伝統と、ほんものが今も生きている京の町なのですから。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を福永社長が案内する場合、どこに案内しますか?
う~ん、悩みますねぇ。京都にはたくさんいい所があるからね。
それに訪れられるひとりひとり求めているものが違うだろうし。
京都で食を楽しみたいひと、その場所を楽しんだり、ほっこりしたいひと…。
あえていうなら東本願寺周辺です。
京都の玄関口、京都駅の近くは周辺に観光スポットが多くないので見逃されがちですが、
いかに大きな寺院であるのか、ぜひ足を運んで山門をくぐって欲しいですね。
観光寺院ではないので、誰でも無料で入れます。
御影堂は木造建築物では世界最大なのです。
今、瓦の葺き替えをしているのですが、
瓦を外すと瓦の重さと土の重さで数メートル高くなったそうです。
また、東本願寺の東向かいにある渉成園(しょうせいえん)もおすすめです。
園内で四季が楽しめるように庭が造られており、
それぞれの季節や趣を感じることのできる茶室がたくさんあります。
みなさんはこんなところにこんな庭園があったのと驚かれることでしょう。
――それでは、次ぎに紹介していただく斉藤さまはどんな方ですか?
着物のデザイナーでもある彼は、古き良きものを知り、大切にしています。
そして、何よりも豊かな感性で新しい着物を作り上げています。
まだまだ彼は若いのですが、私は「温故知新」を彼に感じています。
ふだんからのライフスタイルも憎らしいぐらいお洒落ですし、
ラグビーを愛するスポーツマンでもあります。
一度会えば、彼の魅力がわかって頂けると思います。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年10月7日取材)
■東本願寺HP ~渉成園~
*********************************
 株式会社福永念珠舗
株式会社福永念珠舗
京都市下京区東本願寺前 上珠数屋町角340
代表取締役九代目社長 福永荘三
電話:(075)343-0541
FAX:(075)351-0018
HP:http://www.juzz.net/
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――社長の経歴にについて教えてください。
七代目の祖母の横で9歳の頃から数珠を作り始めました。
「上手にできたなあ、あんたは跡取りさんやねぇ」
と頭を撫でられ褒めて頂いていたことを覚えています。
祖母がもっている千代紙の貼られた箱の中にはいったほのかに甘い菓子や、
仕事台の横には寒い季節にかじかんだ手を温めるために置いていた
手火鉢の上で焼いたくれたお餅に引き寄せられ、祖母の傍に寄り、
見よう見まねで数珠作りをしていました。
それで、中学時代までにはある程度のことはできていたのですが、
友達と外で遊ぶ方がおもしろくなって数珠を作ることから離れていた時代もありました。
特に高校・大学時代はクロスカントリースキー競技をずっと続けていて、
卒業の折にはスキーショップからサービスマンとして誘われていました。
私としては、選手としての契約ではなくても、選手の育成に関わることができれば、
また雪山に行けると考えていました。
ところがいざ就職という時分になって、同級生たちが希望する会社に入社することの難しさをしり、
数珠を作ってお客様に感謝して頂ける家業のすばらしさに気づきました。
また、八代目の父親から「いままで好きなことをやってきたのだから、
わしのいうとおり丁稚奉公に行ってこい」と言われ、跡継ぎの道を進むことにしました。
父の知り合いの関係で愛知にある仏壇屋に修行にいき、
3年間仏壇の販売と製造をさせて頂きました。
それで、京都に戻って来てから、父の弟子に入り30歳の時に技を認めて頂き専務役に、
また、父の体の都合もあり35歳で社長に就任しました。
――京都の活性化ついてはどのようにお考えですか?
今年も12月に開催される京都検定にも通じるのですが、
京都人が京都のことをよく知るということが大切だと思います。
そして京都を訪れるひとを心からおもてなしすることです。
京都は周囲を山に囲まれた盆地なので、京都に入るには山や峠を越えないと入れませんでした。
「おこしやす」という言葉は山を越えてようこそ来てくれはったという意味があります。
京都を訪れる方が、また京都に来たいという気持ちを持っていただくように、
心からのおもてなしをする。
おもてなしは当たり前のサービスではありません。
ひとりひとりが自信をもって京都のよさを伝えることです。
それだけの伝統と、ほんものが今も生きている京の町なのですから。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、初めて京都を訪れる方を福永社長が案内する場合、どこに案内しますか?
う~ん、悩みますねぇ。京都にはたくさんいい所があるからね。
それに訪れられるひとりひとり求めているものが違うだろうし。
京都で食を楽しみたいひと、その場所を楽しんだり、ほっこりしたいひと…。
あえていうなら東本願寺周辺です。
京都の玄関口、京都駅の近くは周辺に観光スポットが多くないので見逃されがちですが、
いかに大きな寺院であるのか、ぜひ足を運んで山門をくぐって欲しいですね。
観光寺院ではないので、誰でも無料で入れます。
御影堂は木造建築物では世界最大なのです。
今、瓦の葺き替えをしているのですが、
瓦を外すと瓦の重さと土の重さで数メートル高くなったそうです。
また、東本願寺の東向かいにある渉成園(しょうせいえん)もおすすめです。
園内で四季が楽しめるように庭が造られており、
それぞれの季節や趣を感じることのできる茶室がたくさんあります。
みなさんはこんなところにこんな庭園があったのと驚かれることでしょう。
――それでは、次ぎに紹介していただく斉藤さまはどんな方ですか?
着物のデザイナーでもある彼は、古き良きものを知り、大切にしています。
そして、何よりも豊かな感性で新しい着物を作り上げています。
まだまだ彼は若いのですが、私は「温故知新」を彼に感じています。
ふだんからのライフスタイルも憎らしいぐらいお洒落ですし、
ラグビーを愛するスポーツマンでもあります。
一度会えば、彼の魅力がわかって頂けると思います。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年10月7日取材)
■東本願寺HP ~渉成園~
*********************************
 株式会社福永念珠舗
株式会社福永念珠舗京都市下京区東本願寺前 上珠数屋町角340
代表取締役九代目社長 福永荘三
電話:(075)343-0541
FAX:(075)351-0018
HP:http://www.juzz.net/
■株式会社福永念珠舗 福永荘三 【1】 >> 【2】 >> 【3】