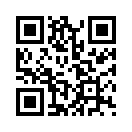2008年08月22日
明治6年、寺町三条で自分と妻の名をとり三嶋亭を創業しました
■第9回 株式会社三嶋亭 三嶌太郎社長 vol.1

株式会社笹屋伊織の田丸道哉社長から、
歴史を守るということともに商売に関しては非常に熱心にやる方です、
と紹介をいただいた株式会社三嶋亭の三嶌太郎社長です。
株式会社三嶋亭は明治6年の創業。 文明開化の味を伝えるすき焼きの老舗です。
――創業は明治6年ということですが、初代はどういう方だったのですか?
はい。初代の三嶌兼吉は江戸時代の鎖国がとけた文明開化の頃、
御所務めをさせて頂いておりました。
初代は、はからいがあって妻の“てい”と長崎へ行き、そこで牛肉を食べる文化に触れ、修行をし、
明治6年に京都に戻り、この寺町三条の地で自分と妻の名をとり「三嶋亭」を創業しました。
今も営業を続けるこの建物は、創業時に建てられたもので、一部増築部分はあるのですが、
今年で135年目の木造3階建てになります。
当時より、すき焼きの専門店としてスタートし、牛肉の販売も併設していました。
といっても、明治のはじめまでは牛肉を食べるというのは仏教の戒律でタブーとされていたので、
まだまだ牛肉を買って、家で調理をすることは少なかったようです。
また服や家に匂いがつくというので、当店のようなお店に来て食べることから
徐々に肉を食べる文化が普及していきました。
稀に家で食べるときも、仏壇や神棚に紙を張って匂いがつかないようにしたり、
庭先で食べたりしていたそうです。
――まさに文明開化の時代だったんですね。
そうですね。鎖国が解け、外国からいろいろな文化が京の町にも入ってきました。
やはりハイカラな商人が最初のお客さんだったようですが、
当初は昔から馴染みのある調味料のお味噌も加えて食べていたようです。
古いメニューが残っているのですが、醤油とお砂糖ベースにお味噌とはっきりと書いてあります。
当時の道具も残っていて、当時はもちろんガスも電気もないので、炭を使っていました。
焼いた炭の上に鍋を置いて調理していました。
現在のように電熱器を使用するようになったのは昭和初期の頃からです。
――創業からずっと寺町三条で商売をされているんですね?
東海道五十三次の終着点である三条大橋からも近いこの場所は
当時より京の中心であり非常に賑わいのあるところでした。
今は四条通から河原町通を北上する祇園祭りの山鉾巡行も
昭和30年代までは寺町通りを通っていたんですよ。
弊社のホームページにも当時の写真を掲載しています。
ちょうどこの三条寺町の所で辻まわしをして、三条通りを西に向いて戻っていきました。
角のスペースは狭いので、引き手が商店のなかまで入って引っ張っていたそうです。
とにかく迫力があって凄かったようです。
■三嶋亭HP
■株式会社三嶋亭 三嶌太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社笹屋伊織の田丸道哉社長から、
歴史を守るということともに商売に関しては非常に熱心にやる方です、
と紹介をいただいた株式会社三嶋亭の三嶌太郎社長です。
株式会社三嶋亭は明治6年の創業。 文明開化の味を伝えるすき焼きの老舗です。
――創業は明治6年ということですが、初代はどういう方だったのですか?
はい。初代の三嶌兼吉は江戸時代の鎖国がとけた文明開化の頃、
御所務めをさせて頂いておりました。
初代は、はからいがあって妻の“てい”と長崎へ行き、そこで牛肉を食べる文化に触れ、修行をし、
明治6年に京都に戻り、この寺町三条の地で自分と妻の名をとり「三嶋亭」を創業しました。
今も営業を続けるこの建物は、創業時に建てられたもので、一部増築部分はあるのですが、
今年で135年目の木造3階建てになります。
当時より、すき焼きの専門店としてスタートし、牛肉の販売も併設していました。
といっても、明治のはじめまでは牛肉を食べるというのは仏教の戒律でタブーとされていたので、
まだまだ牛肉を買って、家で調理をすることは少なかったようです。
また服や家に匂いがつくというので、当店のようなお店に来て食べることから
徐々に肉を食べる文化が普及していきました。
稀に家で食べるときも、仏壇や神棚に紙を張って匂いがつかないようにしたり、
庭先で食べたりしていたそうです。
――まさに文明開化の時代だったんですね。
そうですね。鎖国が解け、外国からいろいろな文化が京の町にも入ってきました。
やはりハイカラな商人が最初のお客さんだったようですが、
当初は昔から馴染みのある調味料のお味噌も加えて食べていたようです。
古いメニューが残っているのですが、醤油とお砂糖ベースにお味噌とはっきりと書いてあります。
当時の道具も残っていて、当時はもちろんガスも電気もないので、炭を使っていました。
焼いた炭の上に鍋を置いて調理していました。
現在のように電熱器を使用するようになったのは昭和初期の頃からです。
――創業からずっと寺町三条で商売をされているんですね?
東海道五十三次の終着点である三条大橋からも近いこの場所は
当時より京の中心であり非常に賑わいのあるところでした。
今は四条通から河原町通を北上する祇園祭りの山鉾巡行も
昭和30年代までは寺町通りを通っていたんですよ。
弊社のホームページにも当時の写真を掲載しています。
ちょうどこの三条寺町の所で辻まわしをして、三条通りを西に向いて戻っていきました。
角のスペースは狭いので、引き手が商店のなかまで入って引っ張っていたそうです。
とにかく迫力があって凄かったようです。
■三嶋亭HP
■株式会社三嶋亭 三嶌太郎 【1】 >> 【2】 >> 【3】