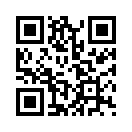2008年08月04日
「春風や どら焼さげて 東寺道」
■第8回 株式会社笹屋伊織 田丸道哉社長 vol.1

株式会社たん熊北店の栗栖正博社長から、
野球とゴルフが趣味で経営の才覚ももっている文武両道の文化人と、
紹介をいただいた株式会社笹屋伊織の田丸道哉社長です。
株式会社笹屋伊織は弘法さんのどら焼が有名な京菓子の老舗です。
――創業は江戸中期ということですが、元は伊勢の菓子職人だったそうですね?
はい。初代の笹屋伊兵衛は伊勢の田丸出身で、創業は1716年、享保元年になります。
全てが定かになっているわけではないのですが、当時、伊勢神宮や
北畠親房の田丸城の菓子職人をやっていたということです。
それで、その腕前が評価され、京都御所に招聘される形で、
京の地に移り、暖簾をかかげることになりました。
そういうルーツがあるので、明治の戸籍改変時に、
出身地の田丸から田丸性を名乗るようになりました。
御所との取引に加えて、茶道家元や神社仏閣のご用を勤めるようになりました。
特に神社仏閣は伏見のお稲荷さん、吉田神社、醍醐寺、泉涌寺、長岡京の揚谷寺など、
特に京都の南部エリアの寺社の御用達を代々、勤めさせて頂いています。
――神社仏閣とお菓子というのはどういう関係になるのですか?
お茶と同様にお寺とお菓子も密接に関係があります。
たとえばお供え物ですね。昔は白雪羹(はくせんこう)といって
お干菓子の大きいような中に餡がはいったものをお出ししていました。
「おしもん」と我々の世界では言うのですが、お参りされた方はそのおさがりを頂いて帰ります。
今も伏見のお稲荷さんでご祈祷された方は、弊店の羊羹を持ち帰っていただくようになっています。
――笹屋伊織さんといえば、「どら焼」が有名ですよね。
「どら焼」は明治初期に五代目伊兵衛が考案したお菓子です。
東寺のお坊さんから副食として何か作ってくれないかという依頼がありました。
お寺に使い古された大きな銅鑼があって、その銅鑼を直接、薪か炭かで熱して、
その上で生地を焼いて、くるくると餡に巻いて食べさせたところ、
美味しいと評判になったということです。
もともと東寺さんから注文が入ったときだけお作りしていたのですが、
昔からコミュニケーションの場所としてお寺にたくさんの人が集まっていましたので、
お坊さんから町の人へと評判になって、
やがて一般に向けても販売しないのかという声が大きくなりました。
「どら焼」は作るのにたいへん手間が掛かるものなので、
毎月21日の弘法さんの命日に合わせて、月に1日だけ作るようになりました。
現在では毎月20、21、22日の3日間売り出しています。
8代目のときに七条堀川から現在の本店が建つこの場所に移転してきました。
市電が通っていた頃は駅もすぐ近くにあって、そこから東寺へお参り行き、
帰りに「どら焼」を買っていくひとが多かったということです。
東寺のおみやげとして「どら焼」をぶらさげて帰るのが京都の風物詩であった時代もあり、
「春風や どら焼さげて 東寺道」という俳句も詠まれました。
■笹屋伊織HP
■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】

株式会社たん熊北店の栗栖正博社長から、
野球とゴルフが趣味で経営の才覚ももっている文武両道の文化人と、
紹介をいただいた株式会社笹屋伊織の田丸道哉社長です。
株式会社笹屋伊織は弘法さんのどら焼が有名な京菓子の老舗です。
――創業は江戸中期ということですが、元は伊勢の菓子職人だったそうですね?
はい。初代の笹屋伊兵衛は伊勢の田丸出身で、創業は1716年、享保元年になります。
全てが定かになっているわけではないのですが、当時、伊勢神宮や
北畠親房の田丸城の菓子職人をやっていたということです。
それで、その腕前が評価され、京都御所に招聘される形で、
京の地に移り、暖簾をかかげることになりました。
そういうルーツがあるので、明治の戸籍改変時に、
出身地の田丸から田丸性を名乗るようになりました。
御所との取引に加えて、茶道家元や神社仏閣のご用を勤めるようになりました。
特に神社仏閣は伏見のお稲荷さん、吉田神社、醍醐寺、泉涌寺、長岡京の揚谷寺など、
特に京都の南部エリアの寺社の御用達を代々、勤めさせて頂いています。
――神社仏閣とお菓子というのはどういう関係になるのですか?
お茶と同様にお寺とお菓子も密接に関係があります。
たとえばお供え物ですね。昔は白雪羹(はくせんこう)といって
お干菓子の大きいような中に餡がはいったものをお出ししていました。
「おしもん」と我々の世界では言うのですが、お参りされた方はそのおさがりを頂いて帰ります。
今も伏見のお稲荷さんでご祈祷された方は、弊店の羊羹を持ち帰っていただくようになっています。
――笹屋伊織さんといえば、「どら焼」が有名ですよね。
「どら焼」は明治初期に五代目伊兵衛が考案したお菓子です。
東寺のお坊さんから副食として何か作ってくれないかという依頼がありました。
お寺に使い古された大きな銅鑼があって、その銅鑼を直接、薪か炭かで熱して、
その上で生地を焼いて、くるくると餡に巻いて食べさせたところ、
美味しいと評判になったということです。
もともと東寺さんから注文が入ったときだけお作りしていたのですが、
昔からコミュニケーションの場所としてお寺にたくさんの人が集まっていましたので、
お坊さんから町の人へと評判になって、
やがて一般に向けても販売しないのかという声が大きくなりました。
「どら焼」は作るのにたいへん手間が掛かるものなので、
毎月21日の弘法さんの命日に合わせて、月に1日だけ作るようになりました。
現在では毎月20、21、22日の3日間売り出しています。
8代目のときに七条堀川から現在の本店が建つこの場所に移転してきました。
市電が通っていた頃は駅もすぐ近くにあって、そこから東寺へお参り行き、
帰りに「どら焼」を買っていくひとが多かったということです。
東寺のおみやげとして「どら焼」をぶらさげて帰るのが京都の風物詩であった時代もあり、
「春風や どら焼さげて 東寺道」という俳句も詠まれました。
■笹屋伊織HP
■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】
Posted by 京の社長と数珠紐 at 12:00│Comments(0)
│株式会社笹屋伊織 田丸道哉