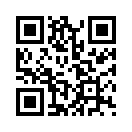2008年08月06日
ピッチャーでいえばワンポイントリリーフみたいなものです。
■第8回 株式会社笹屋伊織 田丸道哉社長 vol.3

――社長は何代目になるのですか?
私は10代目になります。大学が東京の青山学院で、
卒業と同時に大阪の鶴屋八幡さんというお店の東京麹町支店に就職し、
そのあと笹屋伊織の東京支店に入りました。
32歳のときに京都に戻り、代表には39歳のときに就任しました。
今は違うところに住んでいますが、元々ここで生まれ育ち、お菓子を作っているのを毎日観て、
お客様の対応のお手伝いをしたりしていたので、
知らず知らずのうちに家業を継ぐ意識を持つようになっていました。
――子どもの頃は和菓子屋にどういうイメージを持っておられたのですか?
和菓子屋に年末年始はないものですから昔はお正月が嫌でたまりませんでした。
いわゆる一般的な年末年始は全くありませんでした。
忙しいし、かまってもらえないし、初詣もいかない。
そういう中でも否応なく継ぐ要素はあったのでしょうね。
――企業を経営していく上では、大切にしていることは何ですか?
昨今、食にまつわる事故や事件がたくさんありましたが、
やはり根本理念として、お客様の信頼は大切にしたいですね。
「笹屋伊織さんやから安心やな」と言っていただける。
「笹屋伊織さんのお菓子が好きやから」と代々お菓子を買いに来て頂く。
そういう信頼を裏切らないように、正直な商売をしていくということです。
今風にいうと、きちっとしたコンプライアンスに沿った経営をしていくのは当然です。
利はあまり取れないかもしれないが、我々の商売は長く続けないといけない。
長く続いていることに意義があるのです。
また一子相伝ということで、代々つたわっている和菓子の技法を当然まもり続けないといけない。
次ぎの世代に続けていくということが、技術的なものとして大事なことです。
ピッチャーでいえばワンポイントリリーフみたいなものです。
私も「笹屋伊織」の長い歴史の中のほんの数十年かをリリーフでやっているだけで、
その後何代も続いていけるような道筋を作っていく。セーブも勝利もつかなくていいのです。
きっちりホールドして、次ぎに繋いでいくことが大切なのです。
京都の老舗は、どこでも皆さんそういう考え方をしていると思います。
表現方法は違っても中身に流れるものは一本だと思います。
――京都の活性化についてはどのようにお考えですか?
平安遷都1200年のときにも言われたのですが、
京都の町全体がひとつのパビリオンならないといけないと思います。
京都全体が高さ規制をして、町家などの古い町並みを保存することが必要なのではないでしょうか。
昔ながらの京都らしさを守っていく。それが一番大事な基本だと思います。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、
初めて京都を訪れる方を田丸社長が案内する場合、どこに案内しますか?
結局、町全体がひとつのパビリオンをいう考え方をしたとき高台寺の辺りなのかなと思います。
石塀小路や二年坂、産寧坂を歩いていただき京都らしさを一番感じていただく。
京都のイメージに最もマッチするのではないでしょうか。
あとピンポイントということであれば醍醐寺の桜は是非とも観ていただきたいですね。
醍醐寺は庭も広くて素晴らしいですし、宝物殿として霊宝館も見ものです。
――それでは、次ぎに紹介していただく三嶌社長はどんな方ですか?
歴史を守るということと、共に商売に関しては非常に熱心な方です。
僕よりずっとお若いですが見習うところが多いですよ。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年6月25日取材)
■高台寺HP
■醍醐寺HP
*********************************
 株式会社笹屋伊織
株式会社笹屋伊織
京都市下京区七条通大宮西入南側
代表取締役 田丸道哉
電話:(075)371-3334
FAX:(075)343-9151
HP:http://www.sasayaiori.com/
■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】
――社長は何代目になるのですか?
私は10代目になります。大学が東京の青山学院で、
卒業と同時に大阪の鶴屋八幡さんというお店の東京麹町支店に就職し、
そのあと笹屋伊織の東京支店に入りました。
32歳のときに京都に戻り、代表には39歳のときに就任しました。
今は違うところに住んでいますが、元々ここで生まれ育ち、お菓子を作っているのを毎日観て、
お客様の対応のお手伝いをしたりしていたので、
知らず知らずのうちに家業を継ぐ意識を持つようになっていました。
――子どもの頃は和菓子屋にどういうイメージを持っておられたのですか?
和菓子屋に年末年始はないものですから昔はお正月が嫌でたまりませんでした。
いわゆる一般的な年末年始は全くありませんでした。
忙しいし、かまってもらえないし、初詣もいかない。
そういう中でも否応なく継ぐ要素はあったのでしょうね。
――企業を経営していく上では、大切にしていることは何ですか?
昨今、食にまつわる事故や事件がたくさんありましたが、
やはり根本理念として、お客様の信頼は大切にしたいですね。
「笹屋伊織さんやから安心やな」と言っていただける。
「笹屋伊織さんのお菓子が好きやから」と代々お菓子を買いに来て頂く。
そういう信頼を裏切らないように、正直な商売をしていくということです。
今風にいうと、きちっとしたコンプライアンスに沿った経営をしていくのは当然です。
利はあまり取れないかもしれないが、我々の商売は長く続けないといけない。
長く続いていることに意義があるのです。
また一子相伝ということで、代々つたわっている和菓子の技法を当然まもり続けないといけない。
次ぎの世代に続けていくということが、技術的なものとして大事なことです。
ピッチャーでいえばワンポイントリリーフみたいなものです。
私も「笹屋伊織」の長い歴史の中のほんの数十年かをリリーフでやっているだけで、
その後何代も続いていけるような道筋を作っていく。セーブも勝利もつかなくていいのです。
きっちりホールドして、次ぎに繋いでいくことが大切なのです。
京都の老舗は、どこでも皆さんそういう考え方をしていると思います。
表現方法は違っても中身に流れるものは一本だと思います。
――京都の活性化についてはどのようにお考えですか?
平安遷都1200年のときにも言われたのですが、
京都の町全体がひとつのパビリオンならないといけないと思います。
京都全体が高さ規制をして、町家などの古い町並みを保存することが必要なのではないでしょうか。
昔ながらの京都らしさを守っていく。それが一番大事な基本だと思います。
――最後になりましたが、魅力のある場所は京都にたくさんあると思うのですが、
初めて京都を訪れる方を田丸社長が案内する場合、どこに案内しますか?
結局、町全体がひとつのパビリオンをいう考え方をしたとき高台寺の辺りなのかなと思います。
石塀小路や二年坂、産寧坂を歩いていただき京都らしさを一番感じていただく。
京都のイメージに最もマッチするのではないでしょうか。
あとピンポイントということであれば醍醐寺の桜は是非とも観ていただきたいですね。
醍醐寺は庭も広くて素晴らしいですし、宝物殿として霊宝館も見ものです。
――それでは、次ぎに紹介していただく三嶌社長はどんな方ですか?
歴史を守るということと、共に商売に関しては非常に熱心な方です。
僕よりずっとお若いですが見習うところが多いですよ。
――今日は忙しいなか、本当にありがとうございました。
(2008年6月25日取材)
■高台寺HP
■醍醐寺HP
*********************************
京都市下京区七条通大宮西入南側
代表取締役 田丸道哉
電話:(075)371-3334
FAX:(075)343-9151
HP:http://www.sasayaiori.com/
■株式会社笹屋伊織 田丸道哉 【1】 >> 【2】 >> 【3】
Posted by 京の社長と数珠紐 at 12:00│Comments(0)
│株式会社笹屋伊織 田丸道哉